目次
1. 栄養ないはウソ!冬瓜の栄養価と効果効能とは
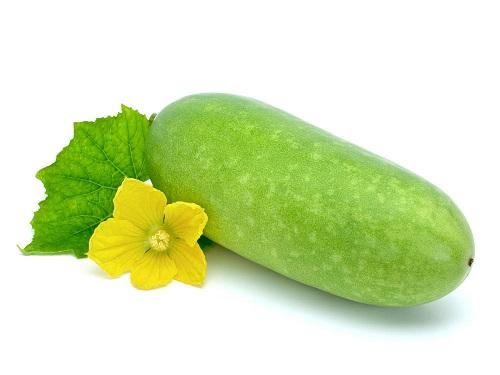
夏野菜の代表格である冬瓜には、夏バテ防止に役立つ栄養素が多く含まれている。加えて利尿作用も強いので、むくみ対策にも適した食材である。
冬瓜の栄養成分
冬瓜は、水分が多くて低カロリーな野菜として知られている。また、少量ではあるが、ビタミン類やミネラル類などもバランスよく含んでいることが特徴である。そんな冬瓜の栄養価を、文部科学省の「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参考に確認しておこう。
冬瓜100gあたりの栄養価
エネルギー:15kcal
たんぱく質:0.5g
脂質:0.1g
炭水化物:3.8g
たんぱく質:0.5g
脂質:0.1g
炭水化物:3.8g
脂肪酸
- 飽和脂肪酸:0.01g
- 一価不飽和脂肪酸:0.02g
- 多価不飽和脂肪酸:0.04g
ビタミン
- βカロテン:0μg
- ビタミンD:0μg
- ビタミンE:0.1mg
- ビタミンK:1μg
- ビタミンB1:0.01mg
- ビタミンB2:0.01mg
- ナイアシン:0.4mg
- ビタミンB6:0.03mg
- ビタミンB12:0μg
- 葉酸:26μg
- パントテン酸:0.21mg
- ビオチン:0.2μg
- ビタミンC:39mg
ミネラル
- ナトリウム:1mg
- カリウム:200mg
- カルシウム:19mg
- マグネシウム:7mg
- リン:18mg
- 鉄:0.2mg
- 亜鉛:0.1mg
- 銅:0.02mg
- マンガン:0.02mg
- ヨウ素:7μg
- セレン:0μg
- クロム:0μg
- モリブデン:4μg
食物繊維:1.3g
(水溶性食物繊維:0.4g)
(不溶性食物繊維:0.9g)
(不溶性食物繊維:0.9g)
冬瓜の注目の栄養と効果:カリウム
むくみ解消に効果があるといわれているのがカリウムだ。冬瓜に含まれる栄養素の中でも、カリウムの含有量が多い。たくさんの水分とともに、ミネラル類のカリウムも摂取できるので夏バテ防止の強い味方になりそうだ。
冬瓜の注目の栄養と効果:ビタミンC
美容成分ともいわれるビタミンCも冬瓜に多く含まれている。加熱しなければ、グレープフルーツにも負けないほどのビタミンCを含んでいるので驚きだ。抗酸化作用やメラニンの生成を抑制する働きがあるので、肌のケアなどを期待できる。
冬瓜の注目の栄養と効果:サポニン
冬瓜の注目すべき栄養素にサポニンは欠かせない。サポニンには油を溶かす働きがあり、コレステロールや中性脂肪を減少させる効果がある。ブドウ糖と脂肪が結合するのを防ぐ働きもあるので、肥満予防も期待されている。
2. 冬瓜のカロリーや糖質

冬瓜はカロリーが低いと分かったが、ほかの瓜と比べてみるとカロリーや糖質はどうだろうか。以下では、それぞれの100gあたりのカロリーと糖質量を一覧で紹介する。
冬瓜:15kcal・2.5g
きゅうり:13kcal・1.9g
はやとうり:20kcal・3.7g
にがうり:15kcal・1.3g
しろうり:15kcal・2.1g
きゅうり:13kcal・1.9g
はやとうり:20kcal・3.7g
にがうり:15kcal・1.3g
しろうり:15kcal・2.1g
どの野菜を見ても、カロリーや糖質が低いと分かる。瓜は水分を多く含むためカロリーが低く、糖質も低いのである。
3. 冬瓜の栄養が豊富な旬は夏

冬瓜の産地として有名なのは暑さが厳しい沖縄県。次に在来種もある愛知県と続いている。沖縄県の中でも主な産地として知られるのが、宮古島市と伊江村だ。生産時期は長く、12~6月上旬と一年の半分にもなっている。ここでは、旬の栄養豊富な冬瓜を食べるための正しい選び方や保存方法を紹介しよう。
旬の冬瓜の選び方
冬瓜の最盛期は6~9月頃だが、冷暗所などで保存された冬瓜は冬までもつといわれている。冬瓜の完熟サインは、表面に現れる白い粉。スーパーで白い粉(ブルーム)が現れた冬瓜を見かけたら美味しい証拠だ。琉球種のものは粉をふかないので、重量感があり鮮やかな緑色のものを選択するのがよい。
冬瓜の上手な保存方法
保存する場合は、腐りやすいワタの部分を除いてラップに包んで冷蔵庫で保存する。カットしていない状態であれば常温で数ヶ月保存できるが、カットした場合は水分が蒸発しやすいので冷蔵庫に入れて数日以内に食べるのがおすすめだ。カットしたあとに長期保存したいときは、冷凍するとよい。食べやすいサイズにカットして冷凍すれば、栄養を逃がすことなく保存できる。
4. 冬瓜の栄養を余さずいただく調理法

冬瓜は栄養豊富だと分かったが、栄養を余さず美味しく食べるにはどうすればよいのだろうか。美味しい食べ方や、加熱する際のポイントを見ていこう。
加熱せず生で食べる
冬瓜は加熱して食べると、栄養素の一部が壊れてしまう。また、カリウムやビタミンCは水溶性の成分のため、水に浸けたり茹でたりすると水に溶け出してしまうのだ。そのため、栄養を余さず食べるのであれば、生でいただくのがおすすめだ。生で食べる際は皮を厚めにむいたあと、ワタを取って食べやすいサイズにスライスする。さらに、軽く塩をふってしばらくおいておけば、アクが抜けて美味しく食べられる。
汁も残さず食べる
味が淡白な冬瓜は味がよくしみ込むので、煮物やスープ系の料理と相性がバツグンだ。
- 冬瓜と鶏肉のスープ
- 豚肉と冬瓜の煮物
- 鶏そぼろと冬瓜のあんかけ
しかし、汁物にするとカリウムやビタミンCがスープ内に流出するため、汁ごと一緒に楽しむのがおすすめだ。味をやや薄めにしておくと、汁ごと食べても塩辛くならずに美味しく食べられるだろう。また、下茹でなどをしたいときは短時間でサッと済ませるとよい。
5. 冬瓜の中身以外の栄養価は?

冬瓜は皮やワタをとり、中身を食べる人が多いだろう。しかし、残った皮やワタの栄養も気になるところである。ここでは、冬瓜の皮・種・ワタの栄養や食べ方をそれぞれ紹介しよう。
冬瓜の皮の栄養
じつは冬瓜の種や皮は薬用として使われるほど、栄養価が高い。皮には中身とほぼ同じ栄養が含まれるが、実と皮の間には豊富な栄養があるので皮ごと食べるのがおすすめだ。皮は洗ってから千切りにし、ごま油をひいたフライパンで炒めて味を付ければきんぴらになる。中身とは違うシャキシャキとした食感がクセになる一品だ。
冬瓜の種の栄養
種も皮と同じく、豊富な栄養素が含まれている。含まれる栄養は実と同じなので、利尿作用や抗酸化作用が期待できる。種は基本的にワタと一緒に食べるのがおすすめで、実から取り出したあとに調味酢で和えて酢の物などにすると美味しい。
冬瓜のワタの栄養
ワタは好みの具材と一緒に出汁で煮てから味噌を加え、味噌汁にして食べるとよい。味噌汁にする際は、種も一緒に加えてOKだ。ワタにも同様に栄養は含まれているが、傷みやすいため早めに食べよう。
6. 冬瓜の豆知識

ここまで冬瓜の栄養や食べ方などを紹介してきたが、最後に冬瓜についての豆知識を見ていこう。名前の由来や種類を知って、冬瓜を食べるときに思い出してみてほしい。
冬瓜の名前の由来
水分量が多いことから減量中でも注目されている冬瓜。原産地はインドやジャワといわれており、江戸時代には一般的に食される食材として知られていた。漢方としても日本で知られており、昔の薬物辞典にもその名が登場する野菜である。なぜ夏が旬なのに冬瓜と呼ばれているかというと、夏に収穫した冬瓜が冬まで長期間保存できるからとされている。
冬瓜の種類
日本で知られる冬瓜の種類は以下のとおりである。
- 長とうがん 細長い形の冬瓜
- 丸とうがん 丸い形の冬瓜
- 琉球種 完熟の証拠である白い粉(ブルーム)をふかない冬瓜
- 小冬瓜 使いきりサイズのミニ冬瓜
上記の種類以外にも、地域ならではの在来種もある。スーパーに売られているのはカットされたものも多い。
結論
今回は冬瓜の栄養について詳しく紹介したが、中身だけでなく皮やワタも美味しく食べられるとは驚きだった。冬瓜はまるごと美味しく食べられるだけでなく、栄養も豊富なのでぜひいろいろな調理法で食べてみてほしい。また、長期保存も可能なのでまるごと購入して種やワタも味わってみてはいかがだろうか。







