1. 日本で最初にチョコレートを食べた日本人

江戸時代に書かれた「寄合町諸事書上控帳」に、オランダや中国と貿易が行っていた長崎へ、チョコレートが伝えられたとの記録が残っている。寄合町とは、長崎の有名な遊女町である。寛政9(1797)年3月晦日(末日)に寄合町の大和路という遊女がチョコレートをもらったとの記述がある。ちなみに寄合町諸事書上控帳の中では、チョコレートは「しょくらあと」と書かれている。記録によると、出島の阿蘭陀人(オランダ人)からもらった品物の中に「しょくらあと6つ」が含まれていたことがわかる。
これが記録として残っている日本初のチョコレートだ。出島のオランダ人は、帰国の際に布団や道具などを遊女に与えることも多く、チョコレートもそのような過程で遊女に渡ったと考えられている。
チョコレートは異国の珍品だったのだ。
これが記録として残っている日本初のチョコレートだ。出島のオランダ人は、帰国の際に布団や道具などを遊女に与えることも多く、チョコレートもそのような過程で遊女に渡ったと考えられている。
チョコレートは異国の珍品だったのだ。
2. 文献にも出てくるチョコレート
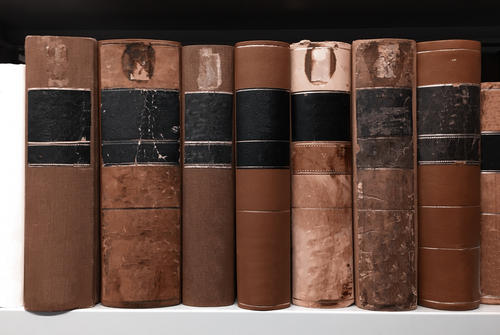
「寄合町諸事書上控帳」以降、様々な文献にチョコレートは登場するようになる。
- 長崎見聞録
寛政12(1800)年に刊行された「長崎聞見録」。
これは、医術や動植物に詳しい、京都の人廣川獬という人物が、6年に渡って長崎を遊学した際に見聞きしたこと、調べたことをまとめた文献である。
この中に「しょくらと」「しょくらとを」という記述が複数ある。 - 徳川昭武幕末滞欧日記
慶應3(1867)年、パリで万国博覧会が開催された。徳川昭武幕末滞欧日記は、この博覧会に幕府代表として訪れた水戸藩主徳川昭武(15代将軍徳川慶喜の弟)が、各地を訪れた後にパリで留学生活を送っていた際の日記である。
万国博覧会の翌年の慶應4(1868)年8月3日にチョコレート(ココア)の記述がある。徳川昭武はシェルブールのホテルで朝8時にココアを飲んだとのこと。これまで、品物として文献にチョコレートの記述があるものはあったが、体験談として書かれたものはこれが初めてだ。
また、これが江戸時代で最後のチョコレートの記録となった。
3. 販売や製造の歴史

日本でチョコレートが商品として売られた最初の記録は、明治10(1877)年11月1日の東京報知新聞に残っている。
ここでは、「新製猪口齢糖(しんせいちょこれいとう)」という名前で広告が掲載されている。
当時、チョコレートは「猪口齢糖」や「貯古齢糖」と書かれていた。
その後、明治32(1899)年、森永商店(現森永製菓)が、輸入したチョコレートを使ったクリームチョコレートの生産を開始。これが日本のチョコレート生産の工業化の始まりである。
明治37(1904)年10月には、この製品の広告を報知新聞紙に掲載した。
明治42(1909)年には、森永が日本で初めての板チョコの生産・販売を開始。この頃、板チョコの価格は1ポンド(約454g)あたり70銭ほどであった。これは、アンパンが70個も買える値段で、当時のチョコレートがいかに高級だったかがわかる。
大正2(1913)年には、不二家洋菓子舗(現在の不二家)が、大正3(1914)年には芥川松風堂(現在の芥川製菓)がチョコレートの製造・販売を開始した。
また、日本でカカオ豆からチョコレートを作る一貫製造が始まったのは大正7(1918)年のことで、森永製菓がミルクチョコレートの販売を開始した。
ここでは、「新製猪口齢糖(しんせいちょこれいとう)」という名前で広告が掲載されている。
当時、チョコレートは「猪口齢糖」や「貯古齢糖」と書かれていた。
その後、明治32(1899)年、森永商店(現森永製菓)が、輸入したチョコレートを使ったクリームチョコレートの生産を開始。これが日本のチョコレート生産の工業化の始まりである。
明治37(1904)年10月には、この製品の広告を報知新聞紙に掲載した。
明治42(1909)年には、森永が日本で初めての板チョコの生産・販売を開始。この頃、板チョコの価格は1ポンド(約454g)あたり70銭ほどであった。これは、アンパンが70個も買える値段で、当時のチョコレートがいかに高級だったかがわかる。
大正2(1913)年には、不二家洋菓子舗(現在の不二家)が、大正3(1914)年には芥川松風堂(現在の芥川製菓)がチョコレートの製造・販売を開始した。
また、日本でカカオ豆からチョコレートを作る一貫製造が始まったのは大正7(1918)年のことで、森永製菓がミルクチョコレートの販売を開始した。
結論
チョコレートを日本で最初に食べたのが、長崎の遊女とは意外に思った方もおられるかもしれない。今でこそ情報の発信は東京というイメージだが、長年鎖国によって外界から閉ざされていた日本にとって、当時は長崎こそが最先端だったのかもしれない。
昭和に入るとチョコレートメーカーが増加し、チョコレートは一般庶民にも浸透していくが、戦線拡大とともに、カカオ豆の輸入制限や製造中止に陥り、しばらくはチョコレートが手に入りづらい世の中になってしまった。
日本でのチョコレートの生産が再開されたのは、昭和26(1951)年とされており、以来種類も製造法も様々な研究を重ねられ、今日のチョコレートがあるのだ。
昭和に入るとチョコレートメーカーが増加し、チョコレートは一般庶民にも浸透していくが、戦線拡大とともに、カカオ豆の輸入制限や製造中止に陥り、しばらくはチョコレートが手に入りづらい世の中になってしまった。
日本でのチョコレートの生産が再開されたのは、昭和26(1951)年とされており、以来種類も製造法も様々な研究を重ねられ、今日のチョコレートがあるのだ。







