1. サニーレタスに含まれる栄養素
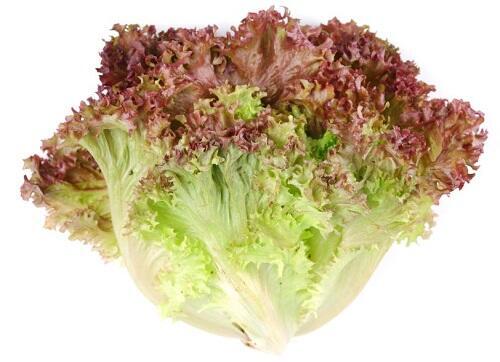
野菜に含まれる栄養素といえばビタミンだ。ビタミンの種類は非常に多く、野菜の種類によって含まれるビタミンは異なるが、サニーレタスの場合はカロテン、ビタミンC、ビタミンEが多く含まれている。ちなみにカロテンとはα-カロテンとβ-カロテン、クリプトキサンチンを総称したもので、これらの栄養素は体内でビタミンAに変換される。つまりビタミンAと同様の働きをする栄養素だが、なかでもβ-カロテンは働きがもっとも強いため食品成分表では「β-カロテン当量」という形でカロテンの量が表されている。また、ビタミンEは「トコフェロール」という成分の総称だが、ここではもっとも働きの強いα-トコフェロールの値を参照する。
サニーレタスの主な栄養素(100g)
- β-カロテン当量:2000μg
- α-トコフェロール:1.2mg
- ビタミンC:17mg
カロテン(ビタミンA)とビタミンE、ビタミンCは抗酸化作用のある栄養素として知られている。細胞が酸化すると細胞の老化などに繋がってしまうが、抗酸化作用のあるビタミンを摂ることで防ぐことができる。ビタミン類には加熱や水に弱いものが多いが、サニーレタスは生の状態で食べることができるためビタミン類の損失が少なく済む。
2. サニーレタスとほかのレタスと比較してみる

一般的にレタスといえばキャベツのように丸まったものを思い浮かべるだろう。しかし、サニーレタスのように丸まっていないタイプのレタスも増えてきている。レタスの種類は非常に多くあり、ここでは文部科学省から発行されている日本標準食品成分表に記載されているレタス類の栄養成分と比較してみる。サニーレタスに多く含まれているビタミン類と比較すると以下のようになる。どれも100gあたりである。
レタスの栄養素
- β-カロテン当量:240μg
- α-トコフェロール:0.3mg
- ビタミンC:5mg
サラダ菜の栄養素
- β-カロテン当量:2200μg
- α-トコフェロール:1.4mg
- ビタミンC:14mg
リーフレタス
- β-カロテン当量:2300μg
- α-トコフェロール:1.3mg
- ビタミンC:21mg
コスレタスの栄養素
- β-カロテン当量:510μg
- α-トコフェロール:0.7mg
- ビタミンC:8mg
サンチュの栄養素
- β-カロテン当量:3800μg
- α-トコフェロール:0.7mg
- ビタミンC:13mg
サラダ菜とリーフレタスはサニーレタスと同じくらいのビタミン量が含まれているが、レタスとコスレタスは少ないことが分かる。同じレタス類でもかなりの差があるが、レタス類のなかでもサニーレタスはバランスよくビタミン類が含まれているといえる。栄養不足が気になるときは、サニーレタスがおすすめだ。
3. サニーレタスは調理すると栄養量は変わる?

サニーレタスは生で食べられるが、それだけでは飽きてしまうことがあるだろう。そんなときには炒め物に加えてみるのがおすすめだ。加熱することでサラダのときよりもシャキシャキ感が減るものの彩りもよく、またほかの食材と味がぶつかることもないため美味しく食べることができる。ただし、先述の通り、加熱することで栄養素は多少失われるだろう。
加熱により失われる栄養素
失われる栄養素の1つが、サニーレタスにも多く含まれるビタミンCだ。水溶性ビタミンに分類されるビタミンCは水に溶けやすく、熱にも弱いという特徴をもつ。残念ながら加熱したサニーレタスの栄養素量は食品成分表に記載されていないため定かではないが、生のサニーレタスよりも加熱したほうがビタミンCの量は少なくなっている。一方で、カロテンやビタミンEは脂溶性ビタミンに分類され、油に溶けやすいという特徴をもつ。つまり、油と組み合わせると効率よく取り込むことができるため、油を使う炒め物とは実は相性がよい。このように失われる栄養素がある一方で、取り込みやすくなる栄養素もあるため一概に加熱するとよい、悪いとは判断できない。
結論
彩り鮮やかなサニーレタスには抗酸化作用の強いカロテンとビタミンE、ビタミンCが多く含まれている。これらの栄養素はすべてのレタスに多く含まれているわけではないため、ビタミンを多く摂りたいときはぜひサニーレタスを選ぼう。また、炒め物にサニーレタスを使う際にビタミンCは失われてしまうが、カロテンとビタミンEは逆に効率よく取り込むことができるようになるので一長一短だ。







