目次
- 乾燥大豆(国産):33.8g(※1)
- 蒸し大豆:16.6g(※2)
- 茹で大豆:14.8g(※3)
- 大豆水煮:12.9g(※4)
- 牛サーロイン肉:17.4g(※5)
- 豚肩ロース肉:17.1g(※6)
- 鶏もも肉:16.6g(※7)
- 油揚げ(生):23.4g(※20)
- 納豆:糸引き16.5g(※21)、挽きわり16.6g(※22)
- 豆腐:木綿7.0g(※23)、絹ごし5.3g(※24)
- おから(生):6.1g(※25)
- 豆乳:3.6g(※26)
- ※1~7、20~出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04023_7
- ※2:豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/蒸し大豆/黄大豆 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04081_7
- ※3:豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/黄大豆/国産/ゆで https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04024_7
- ※4:豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/水煮缶詰/黄大豆 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04028_7
- ※5:肉類/<畜肉類>/うし/[輸入牛肉]/サーロイン/脂身つき/生 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11071_7
- ※6:肉類/<畜肉類>/ぶた/[大型種肉]/かたロース/脂身つき/生 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11119_7
- ※7:肉類/<鳥肉類>/にわとり/[若どり・主品目]/もも/皮つき/生 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11221_7
- ※20:豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/油揚げ/生 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04040_7
- ※21:豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04046_7
- ※22:豆類/だいず/[納豆類]/挽きわり納豆 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04047_7
- ※23:豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04032_7
- ※24:豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹ごし豆腐 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04033_7
- ※25:豆類/だいず/[その他]/おから/生 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04051_7
- ※26:豆類/だいず/[その他]/豆乳/豆乳 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=4_04052_7
- ※8、14~16出典:一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所 栄養素の説明 https://www.orthomolecular.jp/nutrition/amino/
- ※9出典:一般社団法人日本生活習慣病予防協会 大豆など「植物性タンパク質」が寿命を延ばす 動物性の3%を置き換えただけで死亡リスクが低下 http://www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2020/010261.php
- ※10出典:公益財団法人日本食肉消費総合センター「食肉に含まれるタンパク質の特徴は?」 http://www.jmi.or.jp/qanda/bunrui4/q_078.html
- ※11出典:独立行政法人農畜産業振興機構「畜産の必要性について考える」 https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_001382.html
- ※12、17出典:農林水産省
- ※12:「大豆ミート食品類の日本農林規格の制定」p7 https://www.maff.go.jp/j/jas/attach/pdf/211214-10.pdf
- ※17:「ビタミンと食物繊維」 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/topics3_04.html
- ※13出典:一般財団法人教職員生涯福祉財団「プロテイン」 https://www.kyosyokuinzaidan.jp/column/mimiyori/protein.html
- ※18出典:キューサイ株式会社「新提案!ダブルたんぱくのチカラ」 https://corporate.kyusai.co.jp/w-protein/chapter4-2.html
- ※19出典:食品安全委員会 大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A https://www.fsc.go.jp/sonota/daizu_isoflavone.html
1. 大豆のタンパク質含有量

大豆に含まれるタンパク質はどのくらいの量なのか、公式な資料をもとに見ていこう。
乾燥大豆や水煮のタンパク質量
「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」によると、大豆100gあたりに含まれるタンパク質量は下記の通りである。
大豆は肉と同等のタンパク質を含む
大豆のタンパク質量は、下記の肉類と近い数値である。
肉の種類によってもタンパク質量は異なるが、大豆は肉と同等のタンパク質を含む食品といえるだろう。
2. 大豆タンパク質の特徴や効果
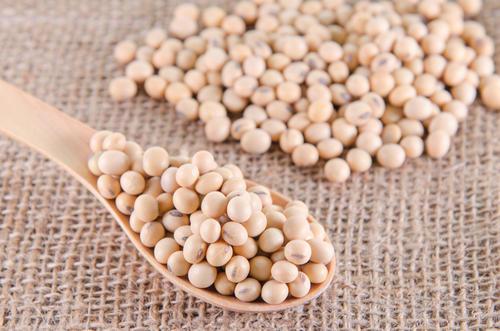
大豆に含まれるタンパク質には、どのような特徴があるのだろうか。また、ほかの代表的な栄養素についても紹介する。
動物性タンパク質ではなく植物性タンパク質
タンパク質には、肉や魚、乳製品など動物性食品に含まれるものと、大豆を含む豆や野菜、穀類など植物性食品に含まれるものの2種類がある。
タンパク質はアミノ酸で構成されており、そのバランスがよいものほど良質なタンパク質とされている。一般的には動物性タンパク質のほうがアミノ酸バランスがよく、体内で利用されやすいという特徴がある。(※8)
しかし、動物性食品のとりすぎは脂質やカロリーの過剰摂取につながりやすいという面もある。植物性食品はアミノ酸バランスが劣るものの、脂質が少ないものが多く、食物繊維や抗酸化物質などを含むなどメリットもある。そのため、動物性食品と植物性食品を組み合わせて、どちらのタンパク質もバランスよく摂取することが望ましい。(※9)
アミノ酸の成分バランスがよい
動物性タンパク質と比較すると、植物性タンパク質はアミノ酸のバランスが悪いものがほとんどだ。しかし、大豆は例外である。9種類の必須アミノ酸のバランスを表した指標をアミノ酸スコアというが、大豆は満点の100点であり、卵や肉、魚と同等なのだ。大豆は、植物性食品でも良質なタンパク質を含む食品といえる。(※8)
大豆タンパク質は吸収率もよい
タンパク質の吸収率は、動物性が97%、植物性が84%といわれている(※10)。
また、2013年に国連食糧農業機関(FAO)により、タンパク質の消化のされやすさ、体内での利用のされやすさを数値化した「消化性必須アミノ酸スコア(DIAAS)」が作成された。DIAASを食品ごとに比較すると、肉や卵、乳製品などは100%以上と高く、小麦やトウモロコシなどは40%台である。しかし、植物性食品でも大豆は99%以上と高く、動物性食品に近い数値である(※11、12)。
大豆タンパク質の吸収スピードは遅い
牛乳由来のホエイプロテインなどは消化吸収が早い。このような吸収の早いタンパク質と比較すると、大豆タンパク質の効率は劣る。しかし、吸収スピードが遅いと腹持ちがよく、食べ過ぎを防げるなどのメリットもある。(※13)
大豆はタンパク質以外の栄養も豊富
大豆には、タンパク質のほかカリウムやカルシウム、マグネシウム、鉄などのミネラル類や、ビタミンEやビタミンB群、食物繊維が多く含まれている(※1~4)。
とくに、筋トレやダイエットで運動を持続的に行う際には、貧血予防に欠かせない鉄やエネルギー代謝を促すビタミンB群、抗酸化作用があり血行促進や疲労回復に役立つビタミンEの摂取が効果的だ。また、便秘予防や腸内環境の改善に役立つ食物繊維は、ダイエットに効果的な栄養素である。(※14~17)
3. 大豆タンパク質の筋トレへの取り入れ方

大豆タンパク質は筋トレに用いられることも多い。その場合、より効果を得やすくするために、下記のポイントをおさえておこう。
筋トレ後ではなく就寝前に摂取
大豆タンパク質は吸収スピードが遅いため、筋トレの直前や直後に摂取しても効果は出にくい。そこで、就寝前に摂取するのがおすすめだ。就寝中にゆっくりと時間をかけて吸収されることで、筋肉の合成に役立つ。(※13)
乳タンパクと同時に摂取
キューサイ株式会社の研究(※18)によると、大豆タンパクと乳タンパクを同時に摂ると、タンパク質の吸収に持続性が認められたという。吸収速度の遅い大豆タンパクと、早い乳タンパクを組み合わせることで、より体内でタンパク質が利用されやすくなるのだ。筋トレが目的の場合は、大豆タンパクと乳タンパクを1:1で同時摂取すると、より効果が期待できる。
4. 大豆タンパク質とりすぎのデメリット
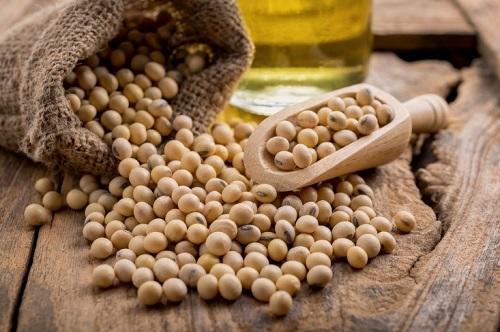
大豆はさまざまな栄養素を含み、良質なタンパク質も摂取できる健康的な食品である(※1~4、8)。しかしその一方で、過剰摂取には下記のようなデメリットがあるため、注意が必要だ。
イソフラボンのとりすぎになる
大豆には大豆イソフラボンが含まれている。女性ホルモンのエストロゲンと化学構造が似ている成分で、有用な面もあるが過剰摂取すると健康被害のリスクを高める可能性も示唆されている。そのため、大豆イソフラボンアグリコン(体内で糖の部分が分離したもの)には一日の摂取目安量の上限値が70~75mgと定められている。大豆100gあたりには平均約140mg含まれているが、煮大豆は約72mg、納豆は約74mg、豆腐は約20mgと、大豆製品の種類や製法によっても異なる。たとえば昼に煮大豆50g、夜に納豆50gを食べた場合でも上限値に達するため、食べすぎには注意が必要である。(※19)
また、大豆(※1)は100gあたり372kcal、脂質量19.7gと、カロリーも脂質も決して低くはない。食べすぎるとイソフラボンだけでなくカロリーや脂質も過剰摂取してしまうため、注意が必要だ。
摂取量の目安
大豆を含む豆類の摂取量は、一日100gが目標とされている(※19)。大豆イソフラボンアグリコンの上限値も考慮しながら、さまざまな豆類や大豆製品を組み合わせて摂取することが望ましい。タンパク質は大豆からだけでなく、動物性食品も含むさまざまな食品からバランスよく摂取しよう。
5. 大豆タンパク質を含む食品

大豆のほかにも、さまざまな大豆製品に大豆タンパク質が含まれている。代表的な食品を、100gあたりのタンパク質含有量とともに紹介する。
油揚げ(※20)はタンパク質を多く含むが、100gあたり377kcalで脂質量も34.4gと多く、一度に食べられる量は限られる。納豆(※21、22)は蒸し大豆(※2)とほぼ同じタンパク質量だ。大豆製品のタンパク質含有量は種類によってもかなり差があるため、不足する場合はほかの食品から補おう。
結論
大豆には植物性タンパク質が多く含まれる。大豆のタンパク質は、動物性タンパク質と同等にアミノ酸スコアの高い良質なものだ。また、ミネラルやビタミン、食物繊維など健康維持に効果的な栄養素も豊富である。大豆イソフラボンなどの過剰摂取には気を付けつつ、ほかの食品と組み合わせながら上手に利用しよう。
(参考文献)







