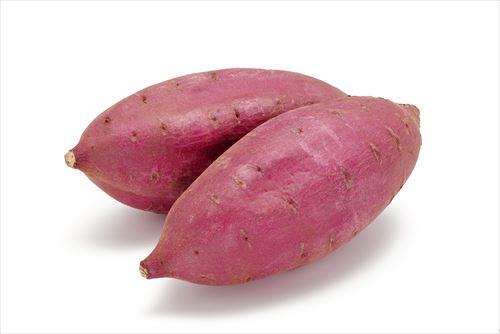目次
- 最初から断面に黒ずみや黒い斑点がある。
- 皮に張りがなく柔らかい。
- 黒カビが生えている(ヤラピンの変色と似ているが、黒カビはフワフワしたものが付着している)
- カビ臭さや酸っぱいニオイがする。
- ※1参照:日本いも類研究会「Q さつまいもを切るとでてくる白い「お汁」はなんでしょうか。」 https://www.jrt.gr.jp/q_a/spqa_shiru/
- ※2参照:JAなめがた「さつまいもの保存方法」 https://ja-ns.or.jp/
- ※3参照:千葉県農林水産部担い手支援課技術振興室「新品種活用による産地育成を目指したサツマイモの高品質生産技術・販売促進支援の手引き」 https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/seikafukyu/documents/h26-6_satumaimo_seisanhanbai.pdf
1. さつまいもは黒い状態になっても食べられる

さつまいもは黒く変色しても、食べられる場合と食べられない場合がある。ここでは、黒く変色しても食べられる状態について解説していこう。
黒い蜜が出ている
さつまいもの表面に黒い蜜のようなものが付着している場合がある。これはさつまいもに含まれる『ヤラピン』と呼ばれる白い液体が表面ににじみ出て変色したものと考えられている。ヤラピンはさつまいもに含まれている成分なので食べても問題ないが、気になる場合は取り除こう。(※1)
黒い斑点がある
さつまいもの断面に黒い斑点のように変色しているときがあるが、これもさつまいもに含まれているヤラピンの変色が原因と考えられている。食べても問題はなく、調理前であればよく洗い流してから使うとよいだろう。
加熱後の変色
さつまいもは加熱後に黒く変色する場合がある。これは、さつまいもに含有するクロロゲン酸が変色したものだ。また、クロロゲン酸はポリフェノール一種で身体に害はないため食べても問題はない。(※2)
2. さつまいもの黒い変色を防ぐ方法

ここでは、さつまいもの黒い変色を防ぐ方法を解説していこう。
水に漬け込む
さつまいもを切ってすぐに水に漬けることで、変色を防ぐことができる。ボウルなどに水を張って皮をむかずに輪切りにした状態で10~15分程度、色がかわらなくなるまで漬け込むようにしよう。また、漬けるだけでも変色は防げるが、手で揉み込むことで時間短縮とアクを取ることができるのでおすすめだ。
皮付近を取り除く
変色する原因であるヤラピンは皮の近くに多く含まれているため、皮をできるだけ取り除くことで変色を防げるのだ。
適温で保存する
さつまいもは常温で保存するのが基本で13~16度が適温といわれている。暑さよりも寒さに弱く、低温で保存した場合低温障害になり傷んでしまう可能性がある。また、20℃以上になると発芽してしまう可能性もあるので、適温で管理しよう。
3. さつまいもが黒い状態で食べられない場合

さつまいもの変色を防ぐ方法が分かったところで、今度は食べられない場合の変色について解説していこう。
傷んでいる状態
さつまいもが傷んでいる状態は以下の通りだ。
最初から黒ずみや黒い斑点がある場合は、ヤラピンの変色と似ているが低温障害によって傷んでいる可能性があるので、カビやニオイなどと一緒に判断することでより安全にさつまいもを味わえるだろう。(※3)
結論
さつまいもに含まれるヤラピンやクロロゲン酸といった成分の影響によって、さつまいもの表面や断面が黒く変色する。変色しても身体に害があるわけではないので食べても問題はない。しかし低温障害などで似たような状態が起こるので注意が必要だ。この記事を参考にさつまいもの黒い変色を防ぎ美味しくいただいてみてはいかがだろうか。
(参考文献)