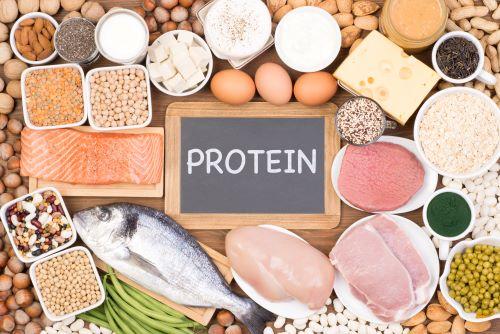目次
1. タンパク質の摂りすぎによる影響

三大栄養素のひとつとして身体を維持するのに欠かせないタンパク質。身体によいものであってもたくさん摂ればいいというわけではない。ここではタンパク質を摂りすぎることで身体にどのような影響があるのか解説する。
過剰摂取について
結論からいうと、タンパク質の摂りすぎによる健康障害は報告されていない。
一日のタンパク質必要量は年齢や性別、生活習慣によって異なり、それぞれにタンパク質平均必要量が設定されている。ところが摂取の目安量は明記されているものの、タンパク質の摂りすぎによる健康上の被害が報告されていないことから、現時点では上限値は設けられていない。
また、摂取エネルギーに対する植物性タンパク質の摂取割合が多いほど死亡リスクが低下する、という研究結果(※1)も明らかにされており、タンパク質の摂りすぎによる身体への悪影響はないといえるだろう。
アメリカでは動物性タンパク質の摂取量が多いほど死亡リスクが上がるとの報告もあるが、少なくとも日本の研究においては動物性タンパク質の摂取量と死亡リスクに関連はないと考えられている。
ただし動物性タンパク質には脂質やカロリーも多く含まれていることから、タンパク質を摂りすぎるとニキビなどの肌荒れや太る原因にもなり得る。もし肌荒れなどのサインが現れたら、動物性タンパク質を摂りすぎていないか食生活を見直そう。
2. タンパク質という栄養素の基本

タンパク質の摂りすぎによる健康障害がないことはわかったが、タンパク質が不足してしまうと身体にどのような影響があるのだろうか。ここではタンパク質の働きについて詳しく解説しよう。
身体への働き
20種類のアミノ酸で構成されているタンパク質は、その配列が変わることで体内での働きも変わる。20種類の中でも9種類のタンパク質は体内で作ることができないため、食事から摂取することが非常に重要だ。(※2)
タンパク質は体内で筋肉や臓器などを構成する成分になるだけでなく、ホルモンや酵素、抗体など身体を調節する機能も担う。(※3)
身体を動かしたり、免疫機能を保つことで身体を守ったり、タンパク質はさまざまな働きで生命維持の重要な役割を果たしているのだ。
不足した場合の影響
タンパク質の不足は成長障害や免疫力の低下につながる。通常の食生活でタンパク質が不足することは少ないといわれているが、無理なダイエットによる食事制限や加齢に伴う食事量の減少などによってはタンパク質が不足してしまう。タンパク質が不足するとタンパク質で構成されている髪の毛や爪、肌の状態が悪化するのはもちろんのこと、ホルモン状態にも深く関連していることから集中力が低下するほかストレスにも敏感になるとされる。(※4)
このようなリスクを回避するために、厚生労働省では日本人の食事摂取基準(2020年版)にてタンパク質の摂取基準を定めている。
3. タンパク質の摂取目安量

では、一日にどれくらいのタンパク質を摂取すればよいのだろうか。推奨されているタンパク質の摂取量を見ていこう。
一日の摂取量
一日に必要なタンパク質量は年齢や性別によって異なる。日本人の食事摂取基準では、18~64歳の男性で一日65gの摂取、65歳以上の男性では60gの摂取が推奨されている。一方女性は18歳以上の成人では50gが推奨量とされており、年齢によって差はないものの、妊娠期においてはその週数によって5~25gを上乗せして摂取することが推奨されている。
また、運動を日常的に行う人は通常の推奨量の1.2倍程度のタンパク質を摂取することが求められている。摂取エネルギーや運動量により、タンパク質の摂取推奨量は多少異なるが、身体に悪い影響がないことを考えると意識して取り入れたい栄養素だ。
4. タンパク質を多く含む食材

積極的に摂取したいタンパク質だが、効率的に摂取するにはどのような食品を取り入れればよいだろうか。ここでは動物性食品と植物性食品に代表されるタンパク質食材を紹介する。
動物性食品と植物性食品
動物性タンパク質は肉、魚介、卵、乳製品などの動物性食品、植物性タンパク質は豆や穀類などの植物性食品に多く含まれている。良質なタンパク質とは、体内で生成できない必須アミノ酸をバランスよく含む食材のこと。一般的に動物性食品に含まれるタンパク質の方がアミノ酸スコアは高く、良質なタンパク質とされている。
動物性食品として100g当たりに含まれるタンパク質量が多い食材としては、肉類だと若鶏肉(ささみ、皮つき胸肉)や豚肉(ロース、ヒレ、もも)、魚類だと丸干しのうるめいわしやしらす干し、乳類はパルメザンチーズやプロセスチーズが挙げられる。
植物性食品として100g当たりに多くタンパク質量を含む食材には豆類で油揚げ、穀類で車麩(焼き麩)がある。
ちなみに、タンパク質の摂りすぎによる健康被害は報告されていないが、プロテインなどで動物性タンパク質を過剰に摂りすぎると、便秘やおならの悪臭化、ひどい場合には尿路結石などの症状を引き起こす可能性があると報告されている。現時点ではタンパク質の摂取量に上限値は設けられていないが、動物性タンパク質も植物性タンパク質も過剰に摂りすぎることなくバランスの取れた食生活を心がけよう。
結論
タンパク質を摂りすぎた場合と不足した場合に、身体にどのような影響があるのか解説した。タンパク質の摂りすぎによる健康被害は報告されていないが、理想的なボディメイクにはタンパク質以外の栄養素も欠かせない。タンパク質だけ過剰に摂りすぎたりせず、栄養バランスの整った食事を楽しんでほしい。
(参考文献)
(※1)国立がん研究センターがん対策研究所
動物性・植物性たんぱく質の摂取と死亡リスクとの関連
(※2)
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020 年版)「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書|
(※3)農林水産省
たんぱく質(しつ)はどのように体にいいのですか。:農林水産省
(※4)メディカル・ケア・サービス株式会社?
タンパク質の働きとは?含まれる食品や不足・過剰症状も紹介 | 健達ねっと|