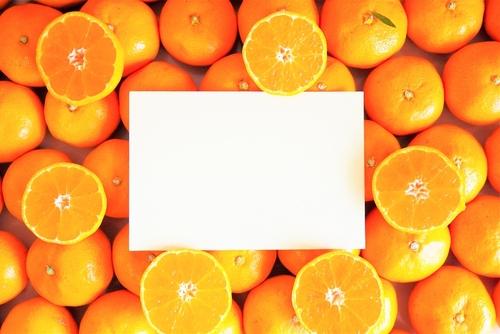目次
1. みかんの漢字表記

みかんの旬は冬のイメージが強いが秋から春先にかけて長く市場に出まわる。そんな老若男女、誰からも愛されるみかんだが意外と漢字について知らない方も多い。そこでみかんの漢字の由来や11月3日と12月3日がみかんの日といわれる由来をご紹介しよう。
蜜柑
蜜のような甘さと書いて蜜柑(みかん)と読むが、かつてみかんは「みっかん」と呼ばれており、1603年に発行された日葡辞書という文献にもmiccanと表記されている。そこからみかんの旬である11月と12月の「みっか(3日)ん」という語呂合わせから「みかんの日」とされるようになった。そもそもなぜみかんは「蜜柑」という漢字になったか、その歴史についても知ってほしいのでもう少しお付き合いいただきたい。
2. みかんの漢字と歴史

かつては室町時代、みかんが中国から伝わってきたとき、それまで食されていた柑橘類とは違い甘みを感じ、蜜のように甘かった。このことから蜜柑(みかん)という漢字が生み出されたと考えられている。みかんの漢字の由来が分かったところで、日本で人気の温州みかんの歴史について触れていこう。
温州みかん
みかんを想像したとき真っ先に温州みかんが思い浮かぶ方も多いのではないだろうか。温州みかんの漢字は、一見すると「おんしゅう」と読んでしまいそうだが、正式には「うんしゅう」と読む。温州みかんは鹿児島県で誕生したとされる品種だが中国の温州地方が由来といわれている。一説によると中国の古典「柑録」において温州産のみかんが美味しい果物として扱われていた。それにあやかって、美味しいみかんを温州みかんと呼ぶようになったと考えられている。
3. みかんに関係する漢字の読み方

こちらではみかんに関係する漢字について解説しようと思う。スーパーでみかんを買う時に目にする機会のある漢字もあるので読み方を知っておくと役に立つ日がくるかもしれない。
極早生と早生
こちらはスーパーで見かけたことがあるのでは?極早生は「ごくわせ」と読み、極早生みかんとは温州みかんより早い9月頃に収穫される品種のことだ。早生は「わせ」と読み、早生みかんは極早生みかんより少しだけ後に収穫されるみかんで艶やかなオレンジ色をしている。
生薬の漢字
本の医薬品に関する公定書である「第十六改正日本薬局方」には生薬としてのみかんが3つ収載されている。ひとつめに陳皮(ちんぴ)といわれる果実の果皮、ふたつめに枳実(きじつ)といわれる未熟な果実、最後に橙皮(とうひ)といわれる成熟した果皮だ。これらをそれぞれ乾燥させたものである。これらの生薬にはさまざまな効能があるとされ、漢方として処方されている。
結論
みかんの漢字について深く掘り下げてみたがいかがだっただろうか。日本の冬の季語にもなっている「みかん」だが知られていないことも多い。日本には極早生みかんのように9月から味わえるものから春先までさまざまな品種のみかんがある。みかんの漢字にまつわる歴史を知り、ここで得た豆知識をいつかどこかでお披露目してほしい。
監修管理栄養士:小林里穂
経歴:管理栄養士養成施設を卒業後、栄養士資格・管理栄養士資格・栄養教諭資格を取得。学校給食センターでの勤務時に小・中学生に食育を実施した経験を活かし、栄養分野の記事執筆・監修を中心に活動中。