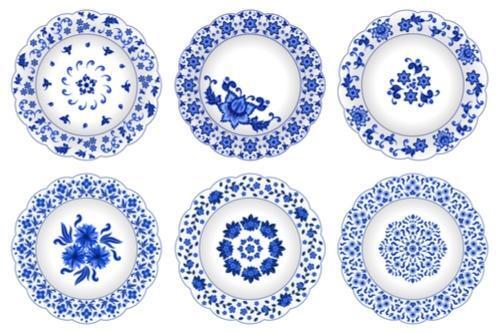1. 日本六古窯の一つ、瀬戸焼の特徴とは

陶器と磁器の両方がある
瀬戸焼の大きな特徴の一つは、「陶器」も「磁器」も両方作られていることだ。陶器は「土もの」と呼ばれ、「陶土」という粘土質の土が原材料である。一方、磁器は「石もの」と呼ばれ、石英や長石などの陶石を粉砕し粘土と混ぜたものが使われる。そのため、陶器と磁器では焼成温度も大きく異なるのだ。
異なる手触りの器が楽しめる
できあがった器を比べてみると、色とりどりの釉薬で色付けされる陶器に対し、磁器は白を基調としたものが多い。高台(茶碗の胴や腰をのせている円い輪の部分)についても、陶器は茶色くざらついているため、表面の手触りから風合いや手作りならではの温かみを感じられる一方、磁器の高台はガラスのような滑らかさや硬質を持ち、すべて白色である。
さまざまな性質を持つ瀬戸焼は、食器や置物のみならずファインセラミックスや建築陶材などにも使われている。わたしたちの生活に溶け込み、彩りやぬくもりを与えてくれる焼き物なのだ。
さまざまな性質を持つ瀬戸焼は、食器や置物のみならずファインセラミックスや建築陶材などにも使われている。わたしたちの生活に溶け込み、彩りやぬくもりを与えてくれる焼き物なのだ。
2. 瀬戸焼に最適!瀬戸地域の陶土と粘土

瀬戸市周辺で採られる陶土や粘土は瀬戸焼にうってつけだ。たとえば、粘土はとても柔らかく耐光性や耐火性にも優れている。また鉄分をほとんど含まないため磁器表面の色は美しい白色になり、この白さを活かした繊細な線や絵付けなど多彩なデザインが生み出されている。このように瀬戸市周辺では良質な粘土が多く産出されたため、多種多様な焼き物の生産が可能になったのだ。
3. 歴史的に有名な品や現代作家作品を眺めてみよう!

「灰釉(かいゆう)」という植物由来の灰から作られる釉薬がある。灰釉は、灰の中に含まれる不純物や焼成の仕方によって色味が少しずつ異なるのが特徴だ。この灰釉を使用した瀬戸焼の歴史的名品の一つが「灰釉陶器」である。人工的に施釉された陶器としては国内最初期のものだ。
近代の瀬戸焼なら、繊細な染付(そめつけ)や上絵など絵付け技法に注目したい。最近では、現代作家の素朴で親しみやすい絵付けの作品も多数販売されている。現代作家の作品を手に取ることで、瀬戸焼の存在をより身近に感じられるだろう。これまで瀬戸焼についてあまり知らなかった方にも、肩ひじ張らずに眺めてみることをおすすめする。お気に入りの瀬戸焼がきっと見つかるだろう。
近代の瀬戸焼なら、繊細な染付(そめつけ)や上絵など絵付け技法に注目したい。最近では、現代作家の素朴で親しみやすい絵付けの作品も多数販売されている。現代作家の作品を手に取ることで、瀬戸焼の存在をより身近に感じられるだろう。これまで瀬戸焼についてあまり知らなかった方にも、肩ひじ張らずに眺めてみることをおすすめする。お気に入りの瀬戸焼がきっと見つかるだろう。
4. せともの祭に参加してみよう!

瀬戸焼に限らず、陶磁器の作品を一度にいろいろ見てみたいという方には、「陶器市」などのイベントに参加するのがおすすめだ。
瀬戸焼に関連したイベントには「せともの祭」(毎年9月第2土曜・日曜に開催)もある。せともの祭では朝9時から夜8時(2日目は夜7時)まで「せともの大廉売市」が催され、瀬戸川沿いに約200軒のせともの店が立ち並ぶ。普段使いできる食器や作家作品などをお手頃な値段で購入できるほか、子どもから大人まで楽しめる絵付け体験コーナーもある。初日の夜には花火も上がるので、お祭り気分で大いに楽しめるだろう。
瀬戸焼に関連したイベントには「せともの祭」(毎年9月第2土曜・日曜に開催)もある。せともの祭では朝9時から夜8時(2日目は夜7時)まで「せともの大廉売市」が催され、瀬戸川沿いに約200軒のせともの店が立ち並ぶ。普段使いできる食器や作家作品などをお手頃な値段で購入できるほか、子どもから大人まで楽しめる絵付け体験コーナーもある。初日の夜には花火も上がるので、お祭り気分で大いに楽しめるだろう。
結論
陶器と磁器の両方が作られる瀬戸焼について解説した。瀬戸焼についてさらに知りたいという方は、瀬戸市内にある瀬戸焼および陶磁器に関する美術館や工芸館に行ってみよう。お土産を買うなら、「せとものプラザ」や「瀬戸陶磁器センター」に寄るのもおすすめだ。美術工芸品から普段使いの食器まで、瀬戸の焼き物が多く展示販売(即売)されているので、瀬戸市周辺に観光に行く機会があればぜひ一度足を運んでみよう。