目次
1. A4サイズとB5サイズの大きさを比較

A4とB5それぞれの大きさを解説する。また、インチやピクセルに変換した場合の大きさも知っておこう。
A4サイズは縦横何センチ(cm)?
A4の各辺の長さは21.0×29.7センチだ。A判はドイツで提案された規格で、現在は国際規格サイズとなっている。面積が1m2(平方メートル)の長方形がA0である。A規格はA0を半分に、それをまた半分にという具合に切っていったサイズのことで、半分に4回切ったところでA4になる。
B5サイズは縦横何センチ(cm)?
B5の各辺の長さは18.2×25.7センチである。B5はA4をひと回り小さくしたサイズと覚えると分かりやすい。B判は日本の美濃紙をもとに定められた独自の規格で、面積が1.5m2の長方形をB0としている。B規格ではB0を半分に5回切ったところでB5になる。
インチ(inch)やピクセル(px)に変換して比較すると?
・A4(単位インチ):8.27in×11.69in
・B5(単位インチ):7.17in×10.12in
・A4(単位ピクセル):2894px×4093px
・B5(単位ピクセル):2508px×3541px
A4:21.0×29.7センチとB5:18.2×25.7センチを、インチやピクセルに変換すると上記になる。ピクセル数は解像度350dpiでの数値である。
・B5(単位インチ):7.17in×10.12in
・A4(単位ピクセル):2894px×4093px
・B5(単位ピクセル):2508px×3541px
A4:21.0×29.7センチとB5:18.2×25.7センチを、インチやピクセルに変換すると上記になる。ピクセル数は解像度350dpiでの数値である。
2. A4サイズとB5サイズそれぞれの縦横比率は?

A4とB5それぞれの縦横比率について解説する。
A4サイズもB5サイズも縦横比率は「1:√2」の白銀比
A4もB5も縦横比率は「1:√2」の白銀比で成り立っている。白銀比とは1:√2の比率のことだ。人が美しいと感じる比率であり、1:√2でできた長方形を半分にしても1:√2、それをまた半分にしても1:√2というように、どこまで半分にしても同じ大きさ、相似形の長方形になる。A4もB5も同じ白銀比だからこそ、A4からB5へ、またB5からA4へなどと縮小、拡大コピーが可能なのである。
3. A4サイズからB5サイズへ、B5サイズからA4サイズへ印刷する際の倍率は?

印刷時に大きさを縮小拡大する場合は、面積からではなく各辺の長さから倍率を求める必要がある。A4とB5を縮小拡大し印刷する際の倍率を解説する。
A4サイズからB5サイズに印刷する場合の縮小率
A4からB5へサイズを変更して印刷する場合の縮小率は87%となる。縮小率と拡大率は計算式で求めることができる。後述する計算方法を知っておこう。
B5サイズからA4サイズに印刷する場合の拡大率
B5からA4にサイズを変更して印刷する場合の拡大率は115%となる。
縮小率や拡大率の計算方法を知っておくと便利
・18.2(B5短辺)÷21.0(A4短辺)×100≒86.7%
・25.7(B5長辺)÷29.7(A4長辺)×100≒86.5%
A4は21.0×29.7センチであり、B5は18.2×25.7センチであるため縮小する場合の計算式は上記となる。
・21.0(A4短辺)÷18.2(B5短辺)×100≒115.3%
・29.7(A4長辺)÷25.7(B5長辺)×100≒115.5%
同様の計算式で拡大する場合は上記となる。A4からB5は縮小で87%、B5からA4は拡大で115%とするといいことになる。印刷の際、微妙な大きさの調整をしたいときは、上記の計算方法を役立ててほしい。
・25.7(B5長辺)÷29.7(A4長辺)×100≒86.5%
A4は21.0×29.7センチであり、B5は18.2×25.7センチであるため縮小する場合の計算式は上記となる。
・21.0(A4短辺)÷18.2(B5短辺)×100≒115.3%
・29.7(A4長辺)÷25.7(B5長辺)×100≒115.5%
同様の計算式で拡大する場合は上記となる。A4からB5は縮小で87%、B5からA4は拡大で115%とするといいことになる。印刷の際、微妙な大きさの調整をしたいときは、上記の計算方法を役立ててほしい。
4. A4サイズとB5サイズを使い分けるポイントは?

A4やB5を使い分けるポイントを紹介する。どのような場面での使用に適しているか目安を知っておこう。
履歴書に適しているのは?
履歴書の大きさはA4とB5がありどちらを使用しても差し支えないが、企業で用いる書類がA4で統一されているなどの理由からA4を使用することを推奨しているようである。ただし、企業によってはB5が主流のところもあるようなので、どっちの用紙にすべきか迷う場合は、直接企業に問い合わせるといいだろう。
ノートやルーズリーフは?
A4かB5で迷ったときは、A4を使用するのが無難だろう。A4のプリントを配られた場合、A4ノートやルーズリーフだとピッタリ挟めるが、B5だとはみ出てしまう。また、使用する際に、ある程度の余白があった方が使いやすい。ちなみに、市販のB5ノートはセミB5と呼ばれるサイズで、通常のB5より若干小さくなる。
ビジネス関係の書類は?
ビジネス関係の書類は、流通量も多く、海外でも多く使用されているA規格のA4がおすすめである。ただし、B5で作られている書類も多いため、使用する状況に合わせて変えていくのが賢明だろう。
写真付きのパンフレットなどは?
スケール感のある写真に見せたいならA4、可愛らしさやコンパクトさを出したいときはB5を使用するのがおすすめだ。見せ方によってサイズを選ぼう。
教科書やカタログなどにB5サイズが多い理由
B5は教科書やカタログで多く使われている。これには理由があり、サイズが大きいと集中したいときに邪魔になったり、1ページの文字数が多すぎると分かりにくい内容になったりする可能性があるからだ。そのため、A4よりも少し小さいB5が好まれている。
5. A4サイズやB5サイズを入れるのに適した封筒の大きさは?

A4やB5を入れるのに適した封筒はどの大きさだろうか。そのまま入れる場合と三つ折りにして入れる場合の封筒をそれぞれ紹介する。
A4サイズがそのまま入る封筒
角形2号のサイズは24.0×33.2センチなので、A4を折らずに封入することができる。少し余裕があるため、クリアファイルに入れた状態や枚数が多いときでも封入が容易である。A4にピッタリサイズの封筒を使いたいときは、サイズが22.9×32.4センチの角形20号がおすすめだ。
A4サイズを三つ折りにして入れるなら?
A4を三つ折りにして封入するなら長形2号や長形3号が最適である。これらの封筒よりもひと回り小さい長形6号もA4を三つ折りで入れることができる。こちらは返信用封筒として使用されることが多い。
B5サイズがそのまま入る封筒
角形3号のサイズは21.6×27.7センチなので、B5を折らずに封入することができる。厚さがないものであれば、ひと回り小さい角形4号でもよいだろう。
B5サイズを三つ折りにして入れるなら?
B5を三つ折りにして封入するなら長形4号が最適だ。ちなみに二つ折りの場合は、長形2号がちょうどよい大きさである。
6. そもそも「A判」と「B判」がある理由は?
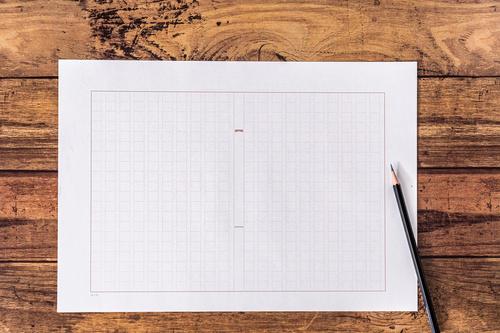
用紙にはA判とB判があるため、少しややこしく感じる方も多いはずだ。なぜA判とB判があるのか、その違いや歴史とあわせて、A判とB判のサイズを一覧で紹介する。
A判とB判の違い
書類のA判化に伴い、使用頻度の高いA4に比べ、最近では見かけることが少なくなったB5判だが、日本で使用されているB判は国際規格のB判とはサイズが異なることをご存じだろうか。日本産業規格JISにて標準化されているA判は国際規格ISOと同じだが、B判はA判の面積を1.5倍にしたものであり、日本独自の規格である。ただし、A判、B判ともに長辺対短辺の比率は1:√2であり、長辺を半分に切るごとに1ずつ数字が増えていくという構造は同じだ。具体的に表すとA0>A1>A2>A3>A4と続き、最後がA10となる。Bも同様だ。
A判とB判の歴史
用紙サイズがJISにて標準化される以前、日本には数種類の用紙サイズがあり、中でも半紙系の「菊判」と、美濃紙系の「四六判」が主として用いられていた。主に菊判は雑誌に、四六判は書籍に使用されることが多かった。その後、用紙サイズを標準化するにあたり、菊判と近いサイズを含む国際規格のA判は菊判系統として採用された。一方、四六判系統に関しては、国際規格のB判より、国際規格A判の面積を1.5倍にしたサイズの方が四六判と近いサイズであったため、別途日本独自のB判を取り決めることとした。つまり、日本のB判は美濃紙系の四六判に対応させるための規格といえるようである。
A判のサイズ一覧
・A0:84.1×118.9センチ
・A1:59.4×84.1センチ(A0の半分)
・A2:42×59.4センチ(A1の半分)
・A3:29.7×42センチ(A2の半分)
・A4:21×29.7センチ(A3の半分)
・A5:14.8×21センチ(A4の半分)
・A6:10.5×14.8センチ(A5の半分)
・A7:7.4×10.5センチ(A6の半分)
・A8:5.2×7.4センチ(A7の半分)
・A9:3.7×5.2センチ(A8の半分)
・A10:2.6×3.7センチ(A9の半分)
上記のように「A」に続く数字が大きくなるほどサイズは小さくなる。また、たとえばA4はA5を2つつなげたサイズ、A3を半分にしたサイズだ。A4のサイズを覚えておけばA3とA5もおのずと分かる。
・A1:59.4×84.1センチ(A0の半分)
・A2:42×59.4センチ(A1の半分)
・A3:29.7×42センチ(A2の半分)
・A4:21×29.7センチ(A3の半分)
・A5:14.8×21センチ(A4の半分)
・A6:10.5×14.8センチ(A5の半分)
・A7:7.4×10.5センチ(A6の半分)
・A8:5.2×7.4センチ(A7の半分)
・A9:3.7×5.2センチ(A8の半分)
・A10:2.6×3.7センチ(A9の半分)
上記のように「A」に続く数字が大きくなるほどサイズは小さくなる。また、たとえばA4はA5を2つつなげたサイズ、A3を半分にしたサイズだ。A4のサイズを覚えておけばA3とA5もおのずと分かる。
B判のサイズ一覧
・B0:103×145.6センチ
・B1:72.8×103センチ(B0の半分)
・B2:51.5×72.8センチ(B1の半分)
・B3:36.4×51.5センチ(B2の半分)
・B4:25.7×36.4センチ(B3の半分)
・B5:18.2×25.7センチ(B4の半分)
・B6:12.8×18.2センチ(B5の半分)
・B7:9.1×12.8センチ(B6の半分)
・B8:6.4×9.1センチ(B7の半分)
・B9:4.5×6.4センチ(B8の半分)
・B10:3.2×4.5センチ(B9の半分)
A判と同様に「B」に続く数字が大きいほどサイズは小さくなる。B6を2つつなげるとB5、B4を半分するとB5になるサイズ感も同じだ。
・B1:72.8×103センチ(B0の半分)
・B2:51.5×72.8センチ(B1の半分)
・B3:36.4×51.5センチ(B2の半分)
・B4:25.7×36.4センチ(B3の半分)
・B5:18.2×25.7センチ(B4の半分)
・B6:12.8×18.2センチ(B5の半分)
・B7:9.1×12.8センチ(B6の半分)
・B8:6.4×9.1センチ(B7の半分)
・B9:4.5×6.4センチ(B8の半分)
・B10:3.2×4.5センチ(B9の半分)
A判と同様に「B」に続く数字が大きいほどサイズは小さくなる。B6を2つつなげるとB5、B4を半分するとB5になるサイズ感も同じだ。
A判もB判もすべて比率は同じ「白銀比」
A4とB5の比率は白銀比とお伝えしたが、実はA判とB判も比率はすべて同じ白銀比だ。どこまで半分にしても同じ大きさ、相似形の長方形になる。
7. A4サイズとB5サイズの大きさや比率の違いを知ってうまく使い分けよう

A4が主流となった現在でも、まだまだB5を使用している場面も多くある。A4とB5の大きさを知り、A4とB5を状況によって適切に使い分けることで、仕事や書類提出などの場面もスムーズに進み、無駄なトラブルを招くこともないだろう。
結論
A4やB5のサイズや大きさ、縦横比率などについて解説した。A4は21.0×29.7センチ、B5は18.2×25.7センチで、A4よりひと回り小さいサイズがB5だと覚えておこう。一般的にA4が主流になっているため、どちらかサイズで迷ったときはA4を選んだ方が無難だろう。小さくて困ることはあっても大きくて困ることは少ないはずだ。






