目次
1. 肉眼で見えるダニの種類
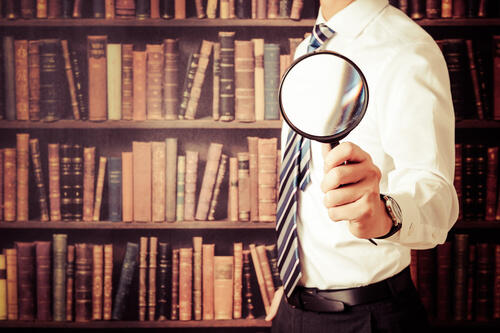
ダニは2万種以上存在するといわれているが、一般家庭の室内に存在するのはそのうちわずか数種類である。ダニは非常に小さく視認は困難であるが中には肉眼で見えるダニも存在する。
肉眼で見えるダニとは?
室内でもっとも多いのは、家庭内のダニの90%を占めるともいわれている「チリダニ」だ。死骸やフンなどがアレルギーの原因となる種でもある。だがチリダニは体長0.2〜0.4mmと極めて小さく、大量発生した際に集団で動いて見えることはあるかもしれないが、基本的には肉眼で見つけるのが難しい。肉眼で見えるダニとしては「コナダニ」「ツメダニ」「イエダニ」「マダニ」などが挙げられる。
多くのダニは1mm以下!「1mm」のサイズ感は?
お手元に10円玉があればぜひ見ていただきたい。10円玉に刻まれた「1」の太さがちょうど1mmだ。ダニの多くはこれよりも小さいため、本稿で「見える」ダニとして紹介していく種も人によっては肉眼では見えづらいことがあると思っていただきたい。
2. 肉眼で見えるダニの特徴

肉眼で見えることがあるダニの代表的な4種類について、そのサイズ感や特徴などを紹介しよう。
コナダニ(ケナガコナダニ)
コナダニは0.3〜0.5mmほどのサイズ感だ。高温多湿の場所を好み、食品や衣料品をエサとする。体は白っぽい色で、真夏に大量発生した際は小麦粉をこぼしてしまったかのように白く見えることがある。ただし背景が白またはそれに近いと視認は困難である。
ツメダニ(フトツメダニ)
ツメダニは0.3〜0.8mmほどのサイズ感で、薄い黄色からオレンジがかったような色をしている。コナダニなどほかのダニを捕食する性質を持ち、人間の血を吸うわけではないが咬むことがある。咬まれた部位はのちに炎症を起こしたり痒みが生じたりする。
イエダニ
イエダニは0.7〜1mmほどと大きめなので、ほかのダニよりも肉眼で見える可能性が高い。白っぽい色をしているが吸血すると赤っぽく変化するためより見えやすくなる。基本的にはネズミなどに寄生して生きているが、人間を咬むこともある。ツメダニ同様、咬まれた部位は痒みが生じることがある。
マダニ
マダニはイエダニよりもさらに大きめの種で3〜4mmほどのサイズ感だ。焦げ茶から黒っぽい色をしている。吸血すると体が膨張するため、さらに見えやすくなる。サイズが大きめなので室内で見かけるとギョッとするかもしれないが、基本的には森や草むらなど自然の中に生息している。ペットを散歩した際などに付着すると、そのまま室内に持ち込まれてしまうことがある。散歩をしたあとは体を洗ってあげるといったことを習慣にするとよいだろう。
3. ダニと見間違えやすい害虫
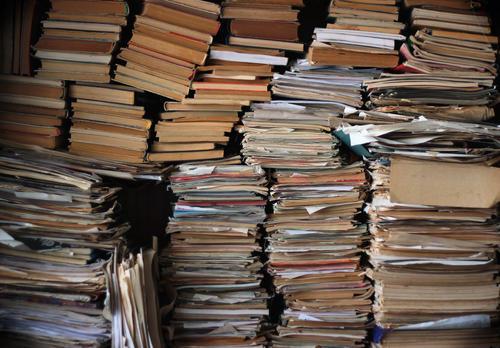
当然ながら、室内で見える小さな虫がすべてダニというわけではない。ダニに見えるがダニではない害虫の種類と特徴も覚えておこう。
ノミ
茶色や赤みがかった色をしており、体長は1〜3mm程度なのでダニよりもやや大きい。肉眼でも見える害虫だ。ダニと違ってピョンピョン跳ねるためノミと判別しやすい。なおノミも吸血する。
南京虫
「トコジラミ」という別名を持つのが南京虫だ。体長5〜8mmと大きいので肉眼でも見える。絨毯や畳の隙間、家具やダンボールの隙間など狭いところに生息し、人間の血を吸う。吸血されると激しい痒みが生じるほか、人によっては発熱といった症状を招くこともある。
チャタテムシ
チャタテムシは体長1mm前後で、畳や障子あるいは「本シラミ」の別名からも分かるように古本などを好む。本の中に白い小さな虫が見えるという場合、チャタテムシの可能性が高い。多湿な場所を好み夏から秋にかけて多く発生する。なおツメダニはチャタテムシを捕食するため、大量発生し二次的被害を被る前に駆除することが大切だ。
4. ダニを肉眼で見る方法

話をダニに戻そう。「肉眼で見えるダニの種類」とお伝えしてきたが、前述のように人によっては見えづらい、まったく見えないこともある。確実に見たいという方は以下のような方法があるので覚えておこう。
顕微鏡やアプリなどを使って見る
一般的に肉眼で見ることが難しいダニも、アプリや顕微鏡といった道具を使えば見える。とはいえ顕微鏡があるご家庭は少ないだろう。より手軽な方法として、スマホの顕微鏡アプリを使う手がある。
市販の「ダニ目視キット」を使って見る
より本格的にダニを見るには、市販のダニ目視キットを使うといった方法がある。ダニ観察用のルーペが付いているものもあり、生きたままリアルな動きを確認することも可能だ。ダニが見えることで生息場所や発生しやすい場所を特定できれば、掃除にも生かせるのではないだろうか。
5. ダニの駆除方法

ダニはどのご家庭にも存在するといわれている。全滅させることは難しいが、人間にとっては害虫のためやはり駆除して個体数をできる限り減らしておくことが大切だ。
一部のダニは「アレルゲン」となりうる
室内でダニが見えると不快だが、それ以上にやっかいなのがアレルゲンとなりうる点だ。見える、見えないに関わらず、安心して暮らすためにもダニの駆除方法を知っておこう。
ダニの効果的な駆除方法は「熱」
一般的にダニは50℃の熱で20〜30分、60℃の熱であれば一瞬で死滅するといわれている。効果的にダニを駆除するには熱を与えることである。
布団乾燥機やホットカーペットなどの「ダニ退治機能」を使う
布団乾燥機やホットカーペット、あるいは電気毛布などには「ダニ退治」といった機能が搭載されていることがある。お使いのそれらの家電にそれらがあれば、ぜひ活用しよう。
コインランドリーの乾燥機を使う
コインランドリーの乾燥機もダニ退治に大きく貢献してくれる。一般家庭用と異なり高温で70〜80℃以上になることもあるため、一瞬で死滅させられる可能性があるのだ。掛け布団やカーペットなど大物のダニを一掃したいというのであれば、コインランドリーを活用しよう。
ダニに効果的な駆除剤を使う方法もある
レック「バルサン」や、アース製薬「ダニアースレッド」など、燻煙タイプの駆除剤を使う方法もおすすめだ。布団類以外に家具や畳の隙間といった掃除しにくいところにも殺虫成分が行き届きやすい。もちろん布団乾燥機やコインランドリーなどとの合わせワザもOKだ。
ダニを死滅させたあとは死骸やフンを取り除く
ダニの死骸やフンがアレルゲンとなることがある。そのため熱や駆除剤などでダニを死滅させたあとは、掃除機で吸い取るなどして死骸やフンをできる限り減らしておこう。
6. ダニの発生を防ぐ方法

ダニを駆除したら、次は再発を防ぐための策を講じよう。1匹残らず家から排除することは困難であり、どんなに入念にお手入れをしていても発生してしまうものではあるが、少しでも抑えることが肝心だ。
こまめに掃除をする
ダニのエサとなりうる食品や衣料品、ホコリや髪の毛といった汚れをできる限り取り除くため、こまめに掃除をしよう。毎日掃除機と雑巾がけをするのは大変だが、たとえば日々「廊下を通る際にフロアワイパーをかける」「トイレに入ったらハンディタイプの掃除機をかける」など少しずつ積み重ねていけばよい。
防ダニ効果のあるシーツや布団を使う
防ダニシートといったアイテム、あるいは防ダニ加工のシーツや布団を使うといった方法もある。ただしこれらを使用していても不衛生な環境であったり湿気が溜まっていたりすればダニが繁殖するおそれがある。こうしたアイテムはほかの方法と併用するのがおすすめだ。
湿気を逃がすため定期的に換気をする
ダニは熱のほか乾燥も苦手である。換気をして湿気を飛ばす、除湿機などで湿度をコントロールする、天日干しが可能な布製品などは干すといったように、さまざまな手段で湿気を溜め込まないように心がけよう。
結論
ダニは非常に小さく肉眼で見ることは難しいが、アプリや目視キットなどを活用すれば見えることがある。それはそうと、ダニはアレルゲンにもなりうる害虫である。安心して生活するためにも、お伝えした駆除方法や予防方法の中からできるものを実践してみていただきたい。
この記事もcheck!






