目次
1. 「湯桶」はなんて読む?ゆおけ?ゆとう?

湯桶読みという言葉を確認したとき、まず気になるのが「湯桶」の読み方だ。湯桶読みについて知る前に、2つの読み方について解説しよう。
湯桶(ゆおけ)とは
湯桶(ゆおけ)とは、いわゆる風呂桶をイメージしてほしい。一般的に風呂桶といえばプラスチック製が主流だが、湯桶という字面には木製が合っているだろう。旅館や温泉などでよく見かける丸い木製の桶のことだ。湯桶をゆおけ、と読むときは風呂桶なので覚えておこう。なお、明確に区別するため「湯おけ」と書くケースも意外と多い。
湯桶(ゆとう)とは
一方、湯桶(ゆとう)とは、蕎麦屋には欠かせない蕎麦湯を入れるあの道具を指す。塗り物や陶器などがあり、どちらも湯桶だが、本来は塗り物を指していたといわれている。同じ漢字であるにもかかわらず、読み方や意味がまったく異なる。使うケースや話の前後で判別できるはずだが、念のため、間違えないように違いを覚えておこう。なお、湯桶読み(ゆとうよみ)にはこちらの読み方を使用する。
2. 「湯桶読み」とは?例を交えて解説
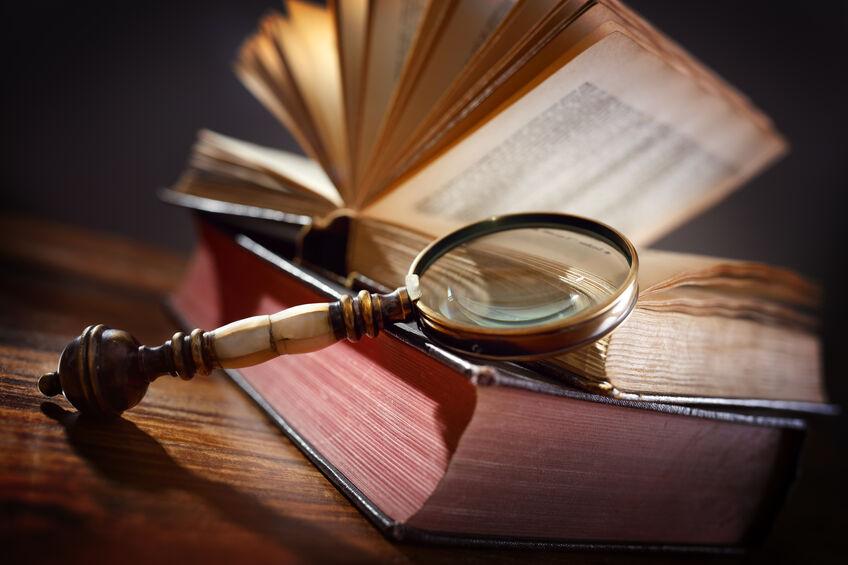
それでは、本題の湯桶読みについて解説しよう。例の一覧と併せてまとめた。
湯桶読みとは
湯桶読みとは、訓読みと音読みが混在する読み方だ。「湯(ゆ)」が訓読みで、「桶(トウ)」が音読みになる。転じて「訓読みと音読み」で成り立つ熟語を湯桶読みという。音読みは音読みと、訓読みは訓読みと組み合わせるのが一般的だが、湯桶読みはその例外だ。
湯桶読みの例
・相性(あいショウ)
・場所(ばショ)
・家賃(やチン)
・株券(かぶケン)
・消印(けしイン)
・夕刊(ゆうカン)
・見本(みホン)
・豚肉(ぶたニク)
・手順(てジュン)
・小判(こバン)
・雨具(あまグ)
・高台(たかダイ)
・敷金(しきキン)
・野宿(のジュク)
・場所(ばショ)
・家賃(やチン)
・株券(かぶケン)
・消印(けしイン)
・夕刊(ゆうカン)
・見本(みホン)
・豚肉(ぶたニク)
・手順(てジュン)
・小判(こバン)
・雨具(あまグ)
・高台(たかダイ)
・敷金(しきキン)
・野宿(のジュク)
3. 「重箱読み」とは?湯桶読みとの違いや例を交えて解説
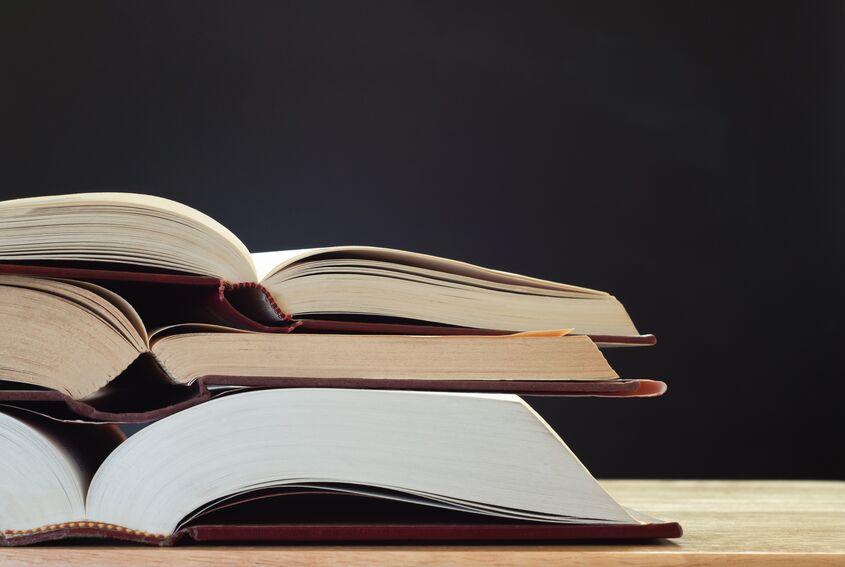
湯桶読みについて学んだあとは、重箱読みも併せてチェックしておきたい。重箱読みの基礎知識と例の一覧を紹介する。
重箱読みとは
重箱読み(じゅうばこよみ)とは、湯桶読みと逆に「音読みと訓読み」で成り立つ熟語を指す。「重(ジュウ)」は音読みで、「箱(ばこ)」が訓読みであることからきている。湯桶読みと間違わないように注意しよう。ちなみに重箱とは、サイズが同じ四角形の箱を積み重ねた食べ物用の容器のことだ。
重箱読みの例
・番組(バンぐみ)
・台所(ダイどころ)
・王様(オウさま)
・素直(スなお)
・職場(ショクば)
・本屋(ホンや)
・絵筆(エふで)
・額縁(ガクぶち)
・金歯(キンば)
・団子(ダンご)
・残高(ザンだが)
・縁組(エンぐみ)
・軍手(グンて)
・碁石(ゴいし)
・毎年(マイとし)
・台所(ダイどころ)
・王様(オウさま)
・素直(スなお)
・職場(ショクば)
・本屋(ホンや)
・絵筆(エふで)
・額縁(ガクぶち)
・金歯(キンば)
・団子(ダンご)
・残高(ザンだが)
・縁組(エンぐみ)
・軍手(グンて)
・碁石(ゴいし)
・毎年(マイとし)
4. 湯桶読みと重箱読みの見分け方のコツとは
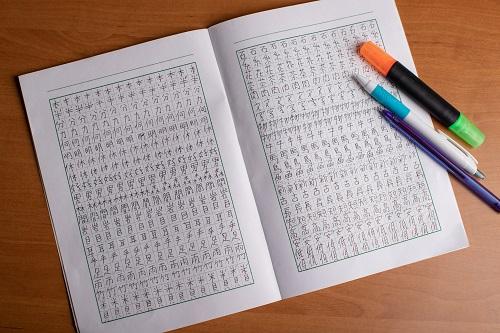
湯桶読みと重箱読みを見分けるためには、まず音読みと訓読みについて学ぶ必要がある。見分け方や二字熟語のパターンなど、基本的な知識をまとめた。
そもそも「音読み」「訓読み」とは?
音読みとは中国語の発音を取り入れた読み方のことを指す。漢字は中国から伝わっており、その読み方も同様だ。たとえば「山」という漢字は、中国語で「シャン」と発音する。その発音に似た「サン」という読み方が音読みになった。これが音読みの由来だ。
一方で、訓読みとは何か。日本ではもともと山を「やま」と呼んでいたため、漢字にもその読み方をあてた。1つの漢字に2つの読み方があるのはこのためだ。なお、辞書などでは中国由来の音読みはカタカナ、日本語の言葉をあてた訓読みはひらがなで区別するケースが多い。
一方で、訓読みとは何か。日本ではもともと山を「やま」と呼んでいたため、漢字にもその読み方をあてた。1つの漢字に2つの読み方があるのはこのためだ。なお、辞書などでは中国由来の音読みはカタカナ、日本語の言葉をあてた訓読みはひらがなで区別するケースが多い。
音読みと訓読みの見分け方
紹介したとおり、湯桶読みとは「訓読みと音読み」、重箱読みとは「音読みと訓読み」で組み合わせる。音読みと訓読みの区別がつけば、湯桶読みと重箱読みが見分けられるようになるだろう。
「それだけでは意味がわかない」読み方は音読みであることが多い。ただし、「肉(ニク)」「本(ホン)」「客(キャク)」など、意味はわかるが音読みのケースもある。また、読み方が一つしかない場合は音読みなので、まずチェックしてみよう。他にも「濁点で始まる」「読み方が「ン」で終わる」「ラ行で始まる」「読み方が3文字以下」など、いずれかに当てはまれば音読みの可能性が高い。
「それだけでも意味が伝わる」のが訓読みの特徴とされる。一方で、「家(や)」「身(み)」「場(ば)」など、例外もあるので注意してほしい。また、「上(あ)がる」「生(しょう)じる」というように、「がる」「じる」といった送り仮名が必要なら訓読みだ。また、公(おおやけ)など、読み方が4文字以上のときも訓読みと考えよう。
「それだけでは意味がわかない」読み方は音読みであることが多い。ただし、「肉(ニク)」「本(ホン)」「客(キャク)」など、意味はわかるが音読みのケースもある。また、読み方が一つしかない場合は音読みなので、まずチェックしてみよう。他にも「濁点で始まる」「読み方が「ン」で終わる」「ラ行で始まる」「読み方が3文字以下」など、いずれかに当てはまれば音読みの可能性が高い。
「それだけでも意味が伝わる」のが訓読みの特徴とされる。一方で、「家(や)」「身(み)」「場(ば)」など、例外もあるので注意してほしい。また、「上(あ)がる」「生(しょう)じる」というように、「がる」「じる」といった送り仮名が必要なら訓読みだ。また、公(おおやけ)など、読み方が4文字以上のときも訓読みと考えよう。
二字熟語の読み方は4パターン
・音読みと音読み:事故(ジコ)
・訓読みと訓読み:出口(でぐち)
・訓読みと音読み(湯桶読み):身分(みブン)
・音読みと訓読み(重箱読み):献立(コンだて)
・訓読みと訓読み:出口(でぐち)
・訓読みと音読み(湯桶読み):身分(みブン)
・音読みと訓読み(重箱読み):献立(コンだて)
5. 湯桶読みや重箱読みは中学受験の問題などに出る?

湯桶読みや重箱読みについて、中学受験の問題で詳しく問われるケースはあまりない。しかし、万が一湯桶読みや重箱読みについて出題されたとき、読み方や意味がわからなければ困るだろう。基本的な知識を身に着けておいて損はないはずだ。日本語の基礎である音読みや訓読みへの勉強になるので、湯桶読みや重箱読みと併せてチェックしておこう。
6. 日頃使う二字熟語が湯桶読みか重箱読みか考えてみるのも一興
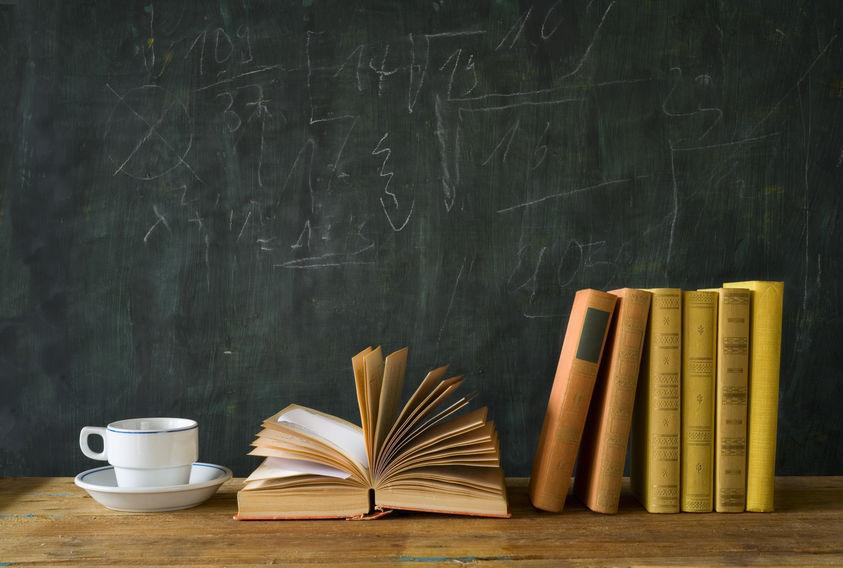
湯桶読みや重箱読みの熟語は多く、知らないうちに使っているケースは多い。二字熟語は4つのパターンに分かれるので、まずは2つの漢字が音読みか訓読みかを確認してみよう。湯桶読みや重箱読みかを考えることは、日本語や漢字の勉強にもつながる。
辞書などでは訓読みはひらがな、音読みはカタカナで記載されるので、自分で答え合わせをしてみるのもよいだろう。いつも使っている二字熟語から少しずつ勉強して、湯桶読みや重箱読みについての理解を深めてほしい。
辞書などでは訓読みはひらがな、音読みはカタカナで記載されるので、自分で答え合わせをしてみるのもよいだろう。いつも使っている二字熟語から少しずつ勉強して、湯桶読みや重箱読みについての理解を深めてほしい。
結論
湯桶読みとは、訓読みと音読みで成り立つ熟語だ。重箱読みはその逆で、音読みと訓読みで成り立つ。この2つを見分けるためには、音読みと訓読みをしっかりと区別することが重要だ。湯桶読みや重箱読みのそれぞれの例を一覧で紹介したので、ぜひ参考にしてほしい。二字熟語の読み方4パターンと併せてチェックして、日本語をより深く学ぼう。






