1. 残暑払いの意味とは?

残暑払いと似た言葉に「暑気払い」というものがある。暑気払いとは、文字通り夏の暑さを払うことを指す。「暑気払い=夏の飲み会」というイメージをお持ちの方もいるかもしれないが、実は暑気払いにはさまざまな方法がある。
たとえば体にたまった暑さを冷たい食べ物や飲み物で追い払ったり、海や川へ遊びに行ったりするのも暑気払いだ。ただし現在は、暑さによるストレスを飲み会で発散する、という意味合いでの使用が多く見られる。
たとえば体にたまった暑さを冷たい食べ物や飲み物で追い払ったり、海や川へ遊びに行ったりするのも暑気払いだ。ただし現在は、暑さによるストレスを飲み会で発散する、という意味合いでの使用が多く見られる。
「残暑払い」とは?
最近は暑気払いではなく「残暑払い」という言葉が使われる場合がある。暑気払いと同じ意味合いで、残暑に行われるものを残暑払いという造語で表現しているようだ。これは、残暑になると暑中見舞いが残暑見舞いに替わることにならったものだと考えられる。
2. 残暑払いの時期はいつからいつまでなの?
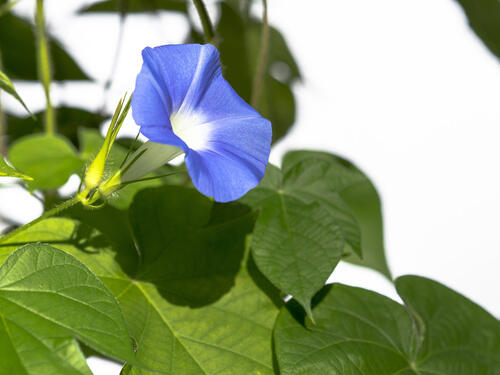
残暑払いとは残暑の暑さを払うもののため、必然的に残暑の時期に使われる言葉だと考えられる。ここでは残暑払いが行われる時期や、そもそも残暑とはいつのことを指すか解説しよう。
「残暑」とはいつのこと?
残暑とは、暦の上での秋である「立秋」を過ぎても残る暑さを指す。立秋とは1年を24の期間に分類した「二十四節気」のひとつで、年によって異なるものの、大体8月7日ごろから8月22日ごろに該当する。この立秋に入ってからの暑さを残暑といい、この時期に送るのは暑中見舞いから残暑見舞いに切り替わる。
暑さが残る時期という意味合いからも、残暑にはっきりとした終わりの日付はない。一般的には8月いっぱい、まだ暑い場合は9月が残暑の時期といえる。つまり残暑払いという言葉も、8月から9月にかけての暑い時期に使われるものと思っていいだろう。
暑さが残る時期という意味合いからも、残暑にはっきりとした終わりの日付はない。一般的には8月いっぱい、まだ暑い場合は9月が残暑の時期といえる。つまり残暑払いという言葉も、8月から9月にかけての暑い時期に使われるものと思っていいだろう。
3. 残暑払いの案内文の例文
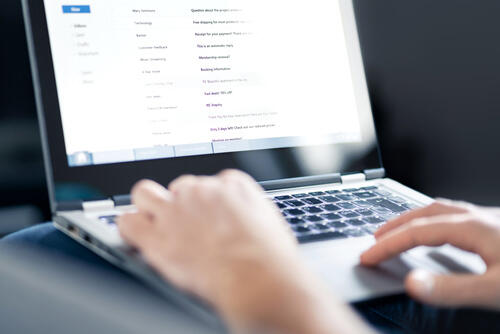
暑気払いや残暑払いといえば、現在は飲み会で暑さを吹き飛ばそうと催されることが多く見られる。残暑の時期に飲み会をしたい場合、また会社や部署で暑気払いを開催するのが遅れてしまった場合、「残暑払い」という名目で飲み会を企画してみてはいかがだろうか。
残暑払いの案内文の書き方
飲み会の幹事がする仕事のひとつが、メールや案内状を送って参加者を招待することだ。案内文を書くときは、以下のポイントを押さえて作成しよう。参加者の都合を考え、案内を早めに出すことも大切だ。
・趣旨がわかる件名や題名をつける
・簡単な挨拶文や時候の挨拶を入れる
・飲み会の日時、場所、会費を明確にする
・いつまでに出欠の返事が必要か書く
・自分の連絡先を書く
・趣旨がわかる件名や題名をつける
・簡単な挨拶文や時候の挨拶を入れる
・飲み会の日時、場所、会費を明確にする
・いつまでに出欠の返事が必要か書く
・自分の連絡先を書く
残暑に使える時候の挨拶
残暑払いの案内文に使える時候の挨拶には、「残暑の候」や「残暑厳しき折」、「立秋とはいえ、まだ暑い日が続きます」といったものがある。メールや案内状に時候の挨拶を盛り込み、上手な導入部を作成しよう。以下にごくシンプルなものではあるが、残暑払いの案内文の文例を紹介するのでぜひ参考にしてほしい。自分らしい言葉を加え、アレンジしてみよう。
残暑払いの案内文の文例
「立秋を過ぎたとはいえ、なお暑い日が続いております。さて、この暑さを乗り切るべく、今年は残暑払いの会を催したく存じます。業務にお忙しいかと存じますが、皆様には奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。」といった書き出しで、「記」と書いた下に飲み会の日時、場所、会費などを入れよう。
最後は「お手数ですが、出欠につきましては◯月◯日までに、◯◯までご連絡くださいますようお願いいたします。」などと締め、下にメールアドレスや電話番号を記しておくとよい。
最後は「お手数ですが、出欠につきましては◯月◯日までに、◯◯までご連絡くださいますようお願いいたします。」などと締め、下にメールアドレスや電話番号を記しておくとよい。
結論
残暑払いには、冷たいものを飲み食いしたり飲み会を開催したりといった行動で残暑の暑さを払うという意味がある。近年の夏は猛暑と呼ばれる暑さが続くが、冷たいビールを飲む、夏野菜など季節の食材を食べるといった方法で、暑さを追い払おう。






