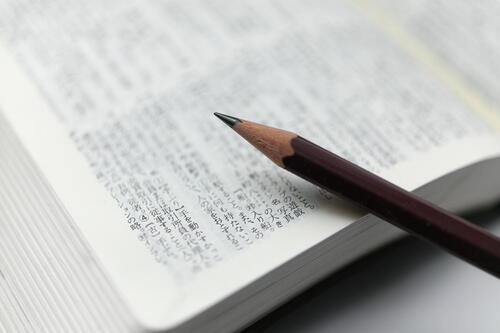1. 鉛筆の起源に関する歴史
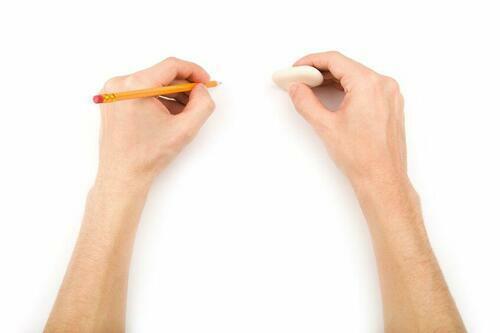
まずは鉛筆の芯の歴史から見ていこう。
鉛筆の歴史は良質な黒鉛が発見されたことで始まる
鉛筆の歴史は1560年代にイギリスのボローデール鉱山で質の良い黒鉛が発見されたことから始まる。日本の歴史でいうと室町時代だ。
黒鉛の黒くなめらかな性質が注目され、現在の鉛筆に近いものが作られた。この頃は黒鉛を細長く削って、木で挟んだり紐で巻いたりして筆記用具として使っていた。
黒鉛の黒くなめらかな性質が注目され、現在の鉛筆に近いものが作られた。この頃は黒鉛を細長く削って、木で挟んだり紐で巻いたりして筆記用具として使っていた。
黒鉛を掘りつくしたため新たな鉛筆の芯が作られた
ボローデール鉱山の黒鉛を掘りつくしたため、1760年ころに黒鉛の粉と硫黄を混ぜて棒状に固めた芯が考案された。考案者はドイツ人のカスパー・ファーバーだ。現在の鉛筆の芯に近い形になったが、残念ながら書き心地は良くなかった。
その後1795年になると硫黄の代わりに粘土を混ぜて焼き固める製法が生み出された。この製法の考案者はニコラス・ジャック・コンテというフランス人で、黒鉛と粘土の比率を変えることで鉛筆の芯の硬度が変化することも発見した。この製法は現在でも鉛筆の芯を作る基本として用いられている。
その後1795年になると硫黄の代わりに粘土を混ぜて焼き固める製法が生み出された。この製法の考案者はニコラス・ジャック・コンテというフランス人で、黒鉛と粘土の比率を変えることで鉛筆の芯の硬度が変化することも発見した。この製法は現在でも鉛筆の芯を作る基本として用いられている。
2. 鉛筆の軸や消しゴムに関する歴史

続いて鉛筆の軸の歴史を見てみよう。
鉛筆の軸の歴史
鉛筆の軸の歴史は黒鉛だけを鉛筆の芯として使用していた時代から始まる。黒鉛だけを使用していた時の鉛筆の軸は、芯を木で挟んだり紐で巻いたりしただけの簡易的なものだった。
その後、鉛筆の軸用の細長い板に四角い溝を作って、四角く削った黒鉛を入れて鉛筆を作るようになった。木の板に芯を入れたら、もう一枚の木の板でふたをしてから丸く削る。現在の鉛筆の形の基礎となる製法だ。
19世紀後半にアメリカの鉛筆業者が鉛筆の芯を丸くして、丸い溝を作った板に挟む製法を開発した。これは現代の鉛筆の軸の製法と同じだ。この製法の開発により、コストが安くて使いやすい鉛筆ができたため、鉛筆は世界的に普及した。
その後、鉛筆の軸用の細長い板に四角い溝を作って、四角く削った黒鉛を入れて鉛筆を作るようになった。木の板に芯を入れたら、もう一枚の木の板でふたをしてから丸く削る。現在の鉛筆の形の基礎となる製法だ。
19世紀後半にアメリカの鉛筆業者が鉛筆の芯を丸くして、丸い溝を作った板に挟む製法を開発した。これは現代の鉛筆の軸の製法と同じだ。この製法の開発により、コストが安くて使いやすい鉛筆ができたため、鉛筆は世界的に普及した。
消しゴムがついた鉛筆はいつ頃できた?
軸の後ろ側に消しゴムがついた鉛筆の歴史は、アメリカ人のハイマン・リップマンの発明から始まった。彼はデッサンをする際にそばに置いたはずの消しゴムがすぐになくなることにストレスを感じて、1858年に鉛筆と消しゴムをセットにすることを思いついた。この発明がもととなり、すでにある商品を組み合わせて新しい商品を開発する手法は、ハイマン法と呼ばれている。
3. 日本における鉛筆の歴史
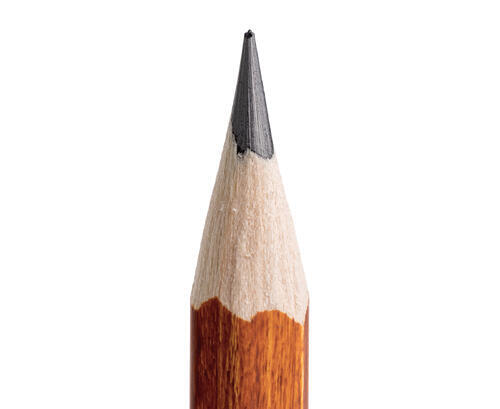
日本に残っている歴史上もっとも古い鉛筆は、久能山東照宮博物館に展示されている徳川家康のものだとされている。軸は赤樫、芯はメキシコ産の鉛筆だが、どのように徳川家康に届いたのかは分かっていない。
徳川家康のほかに鉛筆を使っていたとされる歴史上の人物は伊達政宗だ。1974年(昭和49年)に墓所の瑞鳳殿の発掘を行った際に7cmほどの鉛筆が発見された。
ちなみに色鉛筆の歴史では、姫路神社の古文書に赤鉛筆で書かれたものがもっとも古いとされているが、その赤鉛筆の本体は残っていない。
徳川家康のほかに鉛筆を使っていたとされる歴史上の人物は伊達政宗だ。1974年(昭和49年)に墓所の瑞鳳殿の発掘を行った際に7cmほどの鉛筆が発見された。
ちなみに色鉛筆の歴史では、姫路神社の古文書に赤鉛筆で書かれたものがもっとも古いとされているが、その赤鉛筆の本体は残っていない。
4. 鉛筆のその後の歴史
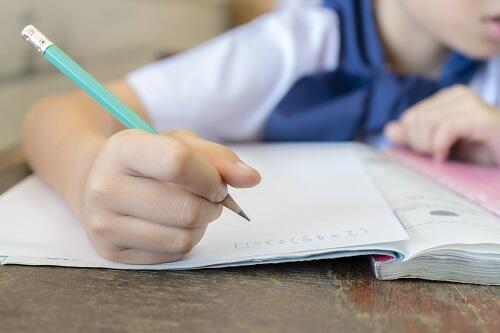
日本ではいつ頃から一般的に鉛筆が使われるようになったのだろうか?そしていつ頃から日本国内で鉛筆が作られるようになったのだろうか?日本国内の鉛筆の歴史を見てみよう。
日本で本格的に鉛筆が使われ始めたのは明治維新以降
日本の歴史の中で本格的に鉛筆が使われ始めたのは明治維新後のことだ。明治時代になってすべての青少年が平等に教育を受けられる仕組みを取り入れ始めたことで、それまで以上に鉛筆が必要となった。
この頃の鉛筆はドイツからの輸入品で高額だったため、一部の人しか使っていなかった。日本の主な筆記用具といえば筆だったため、日本国内でも鉛筆を作れるようにドイツやオーストラリアに伝習生を派遣して、技術を習得させた。
この頃の鉛筆はドイツからの輸入品で高額だったため、一部の人しか使っていなかった。日本の主な筆記用具といえば筆だったため、日本国内でも鉛筆を作れるようにドイツやオーストラリアに伝習生を派遣して、技術を習得させた。
日本での鉛筆作りの歴史
鉛筆の製造技術を習得した伝習生は1873年(明治6年)に帰国した。そして小池卯八郎が、伝習生が持ち帰った技術をもとに、日本で初めて鉛筆を製造した。小池卯八郎は「教育ノ器具」として、国産の鉛筆を1877年(明治10年)に東京の上野で開催された第1回内国勧業博覧会に出品した。
1887年(明治20年)には眞崎仁六が現在の三菱鉛筆株式会社の基となる眞崎鉛筆製造所を造って、鉛筆製造を工業として始めた。この頃の工場は水車を動力とするものだった。三菱鉛筆株式会社には130年以上の歴史があるのだ。
1887年(明治20年)には眞崎仁六が現在の三菱鉛筆株式会社の基となる眞崎鉛筆製造所を造って、鉛筆製造を工業として始めた。この頃の工場は水車を動力とするものだった。三菱鉛筆株式会社には130年以上の歴史があるのだ。
鉛筆の値段はどう推移した?
明治10年代の1本あたりの鉛筆の値段は6~9厘程度だった。しかし国内で大量生産が可能になったおかげで明治34年には1本1厘になり、庶民でも手が届くようになった。
結論
子どものころから身近にある鉛筆の歴史について紹介した。イギリスでは1560年代からすでに現在の鉛筆に近いものを使用していたと知って、驚いただろうか?普段なんとなく使っている鉛筆だが、歴史を知ると大変興味深くてより親しみが湧く。身近な方に鉛筆の歴史を話してみてはいかがだろうか?