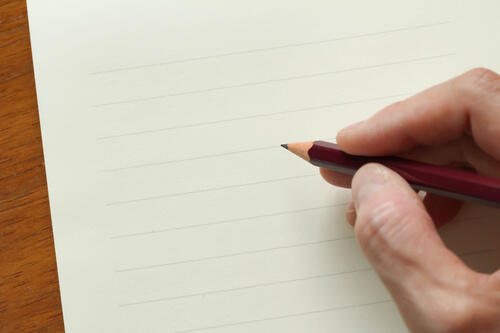1. 鉛筆だこができる原因とは?

鉛筆だこは「タコ」の一種である。タコとは、同じ場所に力や摩擦がかかり続けたときに体の防御反応が起こり、皮膚の角質層が厚く硬くなる症状だ。鉛筆やボールペンなどで文字を書いているときに、一ヶ所に一定の力がかかりすぎると鉛筆だこができることがある。
鉛筆だこはなぜできる?
文字を書く作業が多いからといって必ずしも鉛筆だこができるわけではないだろう。鉛筆だこができる原因は力の入りすぎと言われている。鉛筆を持つときに力を入れすぎていたり、筆圧が高かったりすると鉛筆だこができやすい。また、鉛筆やボールペンを正しく持っていないと力が分散されず、鉛筆だこの原因になるため注意しよう。
2. 鉛筆だこをケアする方法

鉛筆だこができると、その部分だけ膨らんで邪魔になったり、指の形が変わってしまったりして気になるだろう。鉛筆だこができてしまったら、どう対処すればいいのだろうか?
角質ケアをする
鉛筆だこは硬くなった角質でできているので、角質ケアが効果的だ。硬くなった部分をぬるま湯で柔らかくし、軽石などで優しくこする。ある程度角質を落とせたらハンドクリームなどの保湿アイテムを使って乾燥を防ごう。一度硬くなってしまった角質をすぐになくすことは難しい。無理に削ったりせず、肌のターンオーバーを促すようにケアを重ねることが大切だ。
ケアの効果には個人差がある
鉛筆だこができる原因やベストな治療法は個人によって違いがある。角質ケアをしても改善しない場合は、セルフケアを中断し皮膚科の受診をおすすめする。
3. 鉛筆だこができやすい人の注意点

猫背の方は鉛筆だこができやすい傾向にある。猫背の状態で文字を書くと、頭が机に近付き体重が前にかかってしまう。こうなると、文字を書いている手に頭を支えるための不要な力が入り、鉛筆だこができる原因となるのだ。鉛筆だこを作らないためにも正しい姿勢で文字を書くように注意しよう。また、姿勢が悪い状態で文字を書いていると、鉛筆だこだけではなく肩こりや慢性疲労の症状にも繋がる。
4. 鉛筆だこを予防する正しい持ち方

鉛筆を正しく持つことが、一番の鉛筆だこの予防法だ。最後に、鉛筆だこを予防する正しい鉛筆の持ち方を紹介する。
鉛筆の正しい持ち方
1.親指と人差し指で丸を作る
2.作った丸に中指・薬指・小指を包み込むように添える
3.鉛筆を親指と人差し指の間に入れ、中指の爪の根元あたりで支える
2.作った丸に中指・薬指・小指を包み込むように添える
3.鉛筆を親指と人差し指の間に入れ、中指の爪の根元あたりで支える
鉛筆を持つときのコツ
・鉛筆を持ったとき、人差し指よりも親指が上になるようにする
・手のひらにたまごを持っているようなまるい空間をイメージする
・親指の力は抜き、なるべく力まず持つ
・手のひらにたまごを持っているようなまるい空間をイメージする
・親指の力は抜き、なるべく力まず持つ
鉛筆を正しく持つためには姿勢も重要
鉛筆を正しく持ったなら、書く姿勢にも注意しよう。お腹と机の間、両脇の下にこぶしが1つ入るくらいのスペースを作る。鉛筆が身体に近すぎると書きにくいので、お腹が鉛筆の先から30cmほど離した場所にくるように調整する。机と腕は45度くらいの角度を意識し、背筋を伸ばした状態をキープしよう。
鉛筆を正しく持つメリット
鉛筆だこを予防できる以外にも、鉛筆を正しく持つことでさまざまなメリットが得られる。
・たくさん文字を書いても疲れにくい
・思い通りに文字が書きやすい
・「とめ」「はね」がしやすい
・正しい姿勢により猫背や肩こりが解消される
・たくさん文字を書いても疲れにくい
・思い通りに文字が書きやすい
・「とめ」「はね」がしやすい
・正しい姿勢により猫背や肩こりが解消される
結論
今回は鉛筆だこができる原因や予防方法などを紹介した。角質が硬くなってできる鉛筆だこは、文字を書くときに邪魔になるだろう。鉛筆だこができてしまった場合はすぐに角質ケアをし、悪化させないように気を付けよう。また、鉛筆だこを予防するには正しい持ち方、正しい姿勢で鉛筆を使うことが重要だ。鉛筆だこができた経験のある方は、今回の記事を参考に鉛筆の正しい持ち方をマスターしてもらいたい。