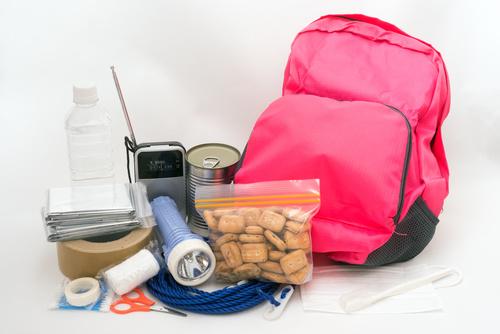1. 防災の水~1日当たりの必要量はどれくらい?

防災用に備蓄しておく水は、どれくらい必要なのだろうか。今までの自然災害の経験を踏まえた備蓄推奨量が内閣府からも提示されている。
飲料水は1人につき1日3リットル
防災用の飲料水は、成人1人につき1日3リットルは確保するように推奨されている。家族4人の場合には12リットルだ。さらに、水道が復旧するのに時間がかかる場合も考えられる。自力でしのぐためには最低でも3日分、可能であれば1週間分の防災用飲料水を備蓄しておきたい。
保存水とミネラルウォーターの違いとは
素朴な疑問として、コンビニなどで売られているミネラルウォーターを備蓄用飲料水として保存することはできないのだろうか。保存水との違いは何なのだろう。
国産のミネラルウォーターのほとんどは、加熱殺菌が行われているため備蓄用飲料水と品質に変わりはない。違いは容器だ。
ペットボトル容器はごくわずかであるが気体を通すという特性がある。備蓄用飲料水は通常のペットボトルよりも厚い材質が使われており、気体の透過性が低くなっていることで賞味期限が長く設定されている。
国産のミネラルウォーターのほとんどは、加熱殺菌が行われているため備蓄用飲料水と品質に変わりはない。違いは容器だ。
ペットボトル容器はごくわずかであるが気体を通すという特性がある。備蓄用飲料水は通常のペットボトルよりも厚い材質が使われており、気体の透過性が低くなっていることで賞味期限が長く設定されている。
2. 防災の水の収納と備蓄方法

防災用の水は、どのように備蓄しておけば、いざというときに安心なのだろう。備蓄方法を紹介しよう。
分散させる
防災用の水は、物置やクローゼットなど1カ所に集めておいた方が管理しやすい。しかし、地震などで家屋が倒壊したり傾いたりすると、場合によっては備蓄している場所から水を取り出せないこともある。
そこで、推奨したいのが分散させるという手段だ。家の中の何カ所かに分散させることによって、確保できる確率が高くなる。
そこで、推奨したいのが分散させるという手段だ。家の中の何カ所かに分散させることによって、確保できる確率が高くなる。
直射日光は避けて備蓄する
防災用飲料水を保管する場所は、できるだけ直射日光を避けた冷暗所が望ましい。加熱殺菌処理がされていても、直射日光が当たることで水の品質が変化してしまう可能性がある。
生活用水の確保も
水は飲料水だけではない。トイレや洗い物といった生活用水も必要になってくる。これらは必ずしも新鮮な水である必要はない。雨水をためたものや浴槽の水を利用することができる。浴槽の水は入浴後にすぐに流してしまうのではなく、入浴前に古いお湯を捨てて新しいお湯にするように習慣づけるといい。
3. 防災の水は賞味期限に注意

防災用の備蓄飲料水は、賞味期限が長いという特徴がある。それゆえに、賞味期限を忘れてしまう可能性がある。
防災用の備蓄飲料水の賞味期限は
一般的には5年という賞味期限が設けられている。保存場所に入れっぱなしにしておくと、賞味期限切れとなって、いざというときに役に立たないということになってしまう。定期的にチェックすることが大切だ。
防災用の備蓄飲料水をムダにしないために
賞味期限切れの水は、生活用水として使用することになる。賞味期限切れになる前に、上手に消費するためには、備蓄用であっても「使う」ことだ。10本の水があったら、2本、3本と使って、新しく補充する。これをルーティーンにすることで、常に賞味期限内の水を確保することができる。
4. 防災用の水おすすめ3選

防災用の水にもいろいろな種類がある。できるだけ保存期間の長いものや自分に合った飲み口の水を選ぶことがポイントだ。おすすめの防災用の保存水を紹介しよう。
アサヒ「「おいしい水」天然水 長期保存水(防災備蓄用)」
アサヒ「おいしい水」天然水は、富士山麓や六甲山系の天然水をくみ上げ、自然のままのおいしさそのままにボトルに詰め込んだミネラルウォーターだ。そのミネラルウォーターを長期保存可能にした。そのため、中身は飲み慣れたミネラルウォーターになっている。
ひと目で防災備蓄用とわかるデザインで、製造から6年の保存が可能になっている。
ひと目で防災備蓄用とわかるデザインで、製造から6年の保存が可能になっている。
富士ミネラルウォーター「非常用5年保存水」
日本人になじみのある「軟水」を使った保存用飲料水だ。富士の麓、800mで採取されたミネラルウォーターで、冷やさなくてもおいしく飲めるのが特徴だ。衛生処理されたミネラルウォーターの保存期間は5年間で、保管用の段ボールには、取っ手穴を付けず防塵・害虫対策もしっかりされている。
アクアインターナショナル「富士山バナジウムウォーター保存水」
富士の伏流水を使用したミネラルウォーターで、豊富な天然ミネラル成分を多く含有しているのが特徴だ。保存水は水の分子が細かく、身体に浸透しやすい。水の劣化を自ら防ぐため5年という長期保存を可能にした。
結論
地震や台風などの自然災害に対する防災準備は、やりすぎるということはない。とくに水の備蓄は、生命に直結するものなので必ず準備しておきたい。水を用意したからと安心はしていられない。水の備蓄量や備蓄方法、さらに賞味期限の確認などを怠ると、いざというときに使い物にならない可能性もある。家族と話し合いながら災害に備えよう。