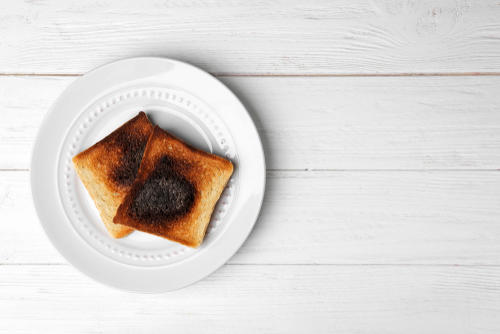1. パンの焦げは本当に体に悪いのか?

体に悪いといわれたり、ガンになるなどといわれたりする「焦げ」だが、本当に体に悪いのだろうか?焦げだけを好んで食べる人は少数派だろうが、香ばしい少し焦げたパンを好む人は少なくないだろう。そこでまずは、焦げが体に悪いのかどうか、科学的な根拠があるのかを紹介する。
結論からいうと、焦げがガンのリスクになることは確認されている。食べるのはなるべく避けたほうがよいとはいえ、体に悪いからと一欠片たりとも食べないようにするほど神経質にはならなくてもよい。なるべく焦げを取り除き、好んで食べるようなことは避ければよいだろう。体に悪いことが懸念される成分としては、以下の2つだ。詳しく見ていこう。
結論からいうと、焦げがガンのリスクになることは確認されている。食べるのはなるべく避けたほうがよいとはいえ、体に悪いからと一欠片たりとも食べないようにするほど神経質にはならなくてもよい。なるべく焦げを取り除き、好んで食べるようなことは避ければよいだろう。体に悪いことが懸念される成分としては、以下の2つだ。詳しく見ていこう。
ヘテロサイクリックアミン
1975年に発見されたヘテロサイクリックアミンは、動物実験によって発ガン性を示すことが確認されている成分だ。実際、国立がんセンターでもDNAに傷をつける発がん性物質として扱われている。もともとは魚の焦げから発見された成分だが、たんぱく質を多く含む肉の焦げにも発生するようだ。肉や魚は、長時間熱するなど、焦げをつくるような調理方法は避けたほうがよいとされている。
アクリルアミド
アクリルアミドは、土壌凝固や漏水防止の用途で1950年代から製造されている化学物質だ。2002年には、揚げたり焼いたりした馬鈴薯に発生していることが発表された。発ガン性を始め、神経障害などの健康への影響があるとされている。水分含有量の少ないものにはとくに加熱調理でできやすくなるとされているので、やはりパンの調理には気を配るべきだろう。
2. パンの焦げの取り方や再利用方法

パンの焦げが健康リスクになることが分かっていても、どうしても焦がしてしまうこともあるだろう。そこで、焦げの取り方や再利用方法などを考えていこう。
おろし金を使って取る
焦げの取り方としては、指でざっくり取る方法でもよいが、パンの場合はおろし金を使ってとるのもいい。中まで焦げていない場合、表面の焦げさえ取ればそのまま食べることができる。
冷蔵庫で脱臭炭として使う
意外な利用方法だが、パンの焦げは炭に近いイメージで、脱臭効果が期待できる。脱臭炭として使う場合は、しっかりと焦がした方が効果を期待できるだろう。お皿やタッパーなどに入れ、ラップなどはかけずに冷蔵庫の中に入れておくとよい。
このように、焦がしたからと言ってすぐゴミ箱へ捨てるのではなく、おろし金で対応してみたり、冷蔵庫などの脱臭に取り組んでみるのもよいだろう。
このように、焦がしたからと言ってすぐゴミ箱へ捨てるのではなく、おろし金で対応してみたり、冷蔵庫などの脱臭に取り組んでみるのもよいだろう。
3. アルミホイルなどで、そもそもパンを焦がさないようにしよう

トースターなどで食パンをトーストする場合、パンを焦がさないようにするには加熱時間やパンの厚さを一定にすればよいので比較的簡単だ。しかし、食パン以外のパンやトーストをアレンジする場合などは、グリルやオーブンを使うので、焦げてしまう場合もあるだろう。そこで、なるべく焦げを少なくしつつ、きちんと調理もできるような方法を見ていこう。
グリルやオーブンをきちんと温める
コンロの魚焼きグリルやオーブンの使い方しだいで、焦げを少なくすることはできる。それは、あらかじめきちんと庫内を温めておくことだ。予熱をきちんとしておくことで、不要な水分が飛び、食材全体に熱が伝わりやすくなる。パンの表面が焦げていくのを防ぐことにつながるのだ。単純にトーストを作るだけならば、面倒くさがらずに裏返しをすることも重要である。
冷凍のパンを焼くときにはアルミホイルを使う
パンを冷凍して保存している人も多いと思うが、冷凍したパンを焦がさないように焼くには一工夫必要だ。具体的にはアルミホイルの使用をおすすめする。パンの下にアルミホイルを敷いてグリルすることで、焦げを防いでくれる。アルミホイルがない場合は、クッキングプレートなどを使うとよいだろう。また、あらかじめ冷凍状態のときに、半分にしておくとより焦げにくい。
結論
パンの焦げの健康リスクや焦げてしまったときの再利用方法、そもそも焦がさない方法をご紹介した。焦げを好んで食べる人はあまりいないと思うが、健康に影響があるのであれば、できるだけ避けたいところだ。今回紹介したことを活かし、なるべく焦げを食べないようにすることを心がけよう。