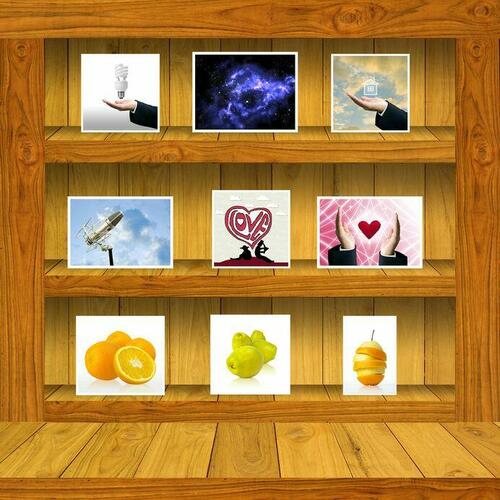1. すのこで本棚制作。強度は大丈夫?

ホームセンターや大手スーパーの家具コーナー、100均など、すのこは手軽に購入できる。価格も安く、サイズも豊富に揃っていて、DIYを楽しむ人たちの間で「便利素材」として重宝されている。「すのこ DIY」で検索すれば、すのこで作られた棚や、ウォールハンガー、調味料入れなどの作品を見つけることができる。
しかし、重い本を収納する本棚の素材としては、強度を気にせず利用できるのだろうか。すのこは「ゲタ」と呼ばれる角材に、すきまを開けて細長い平板を数枚打ち付けたもので、通気性がよい反面、強度が心配になる。
実際、側面材としてすのこを使い、棚板には厚めの平板を使用すれば、少々重いものを乗せてもたわみはしないが、すのこを棚板として使用すると、本を7~8冊乗せただけで中央がたわんでしまい、ぎっしり本を並べての使用は難しい。
側面材だけにすのこを使用するにしても、地震の揺れや物をぶつけた衝撃などで、フレーム自体がゆがんだり、折れる心配もある。すのこの横幅を短くカットした1~2段のミニ本棚に、軽いコミックスや文庫本を並べるのなら問題はないが、すのこを棚板に用いて本格的な本棚を制作するのは困難なようだ。
しかし、重い本を収納する本棚の素材としては、強度を気にせず利用できるのだろうか。すのこは「ゲタ」と呼ばれる角材に、すきまを開けて細長い平板を数枚打ち付けたもので、通気性がよい反面、強度が心配になる。
実際、側面材としてすのこを使い、棚板には厚めの平板を使用すれば、少々重いものを乗せてもたわみはしないが、すのこを棚板として使用すると、本を7~8冊乗せただけで中央がたわんでしまい、ぎっしり本を並べての使用は難しい。
側面材だけにすのこを使用するにしても、地震の揺れや物をぶつけた衝撃などで、フレーム自体がゆがんだり、折れる心配もある。すのこの横幅を短くカットした1~2段のミニ本棚に、軽いコミックスや文庫本を並べるのなら問題はないが、すのこを棚板に用いて本格的な本棚を制作するのは困難なようだ。
2. すのこで作るなら、絵本などをディスプレイできる飾り本棚がおすすめ

「やっぱりすのこで本棚を作るのは無理か~」と諦めるのはまだ早い。発想を転換すれば、すのこでとてもセンスのよい本の収納棚を作ることができる。それは本の表紙を正面に立てて見せる、ディスプレイタイプのブックスタンドだ。
すのこを裏返して壁に立てかけ、ゲタ部分に本を乗せるように置くだけで、本屋の店頭のディスプレイ風になる。たくさんの冊数を収納する本棚としては強度が心配なすのこだが、裏面のゲタを使うことで、実にユニークなインテリアを作ることができる。
幼い子ども用の絵本置き場として使えば、字が読めなくても楽しめるし、カラフルな表紙がインテリアにもなる。同様に、写真集や雑誌、ジャケットが美しいCDなどをこの棚に飾れば、リビングのアクセントとしても使えそうだ。
ただし、すのこの裏は表面に比べてザラザラしているので、すのこをそのまま壁に立てかけただけでは、ちょっとした振動で倒れてしまう。ディスプレイ棚としては優秀なすのこに工夫を加えてこそ、インテリアとして成立する。さっそく楽しみながら、すのこでDIYに取りかかってみよう。
すのこを裏返して壁に立てかけ、ゲタ部分に本を乗せるように置くだけで、本屋の店頭のディスプレイ風になる。たくさんの冊数を収納する本棚としては強度が心配なすのこだが、裏面のゲタを使うことで、実にユニークなインテリアを作ることができる。
幼い子ども用の絵本置き場として使えば、字が読めなくても楽しめるし、カラフルな表紙がインテリアにもなる。同様に、写真集や雑誌、ジャケットが美しいCDなどをこの棚に飾れば、リビングのアクセントとしても使えそうだ。
ただし、すのこの裏は表面に比べてザラザラしているので、すのこをそのまま壁に立てかけただけでは、ちょっとした振動で倒れてしまう。ディスプレイ棚としては優秀なすのこに工夫を加えてこそ、インテリアとして成立する。さっそく楽しみながら、すのこでDIYに取りかかってみよう。
3. 100均すのこで飾り本棚をDIYする方法

すのこを使ったディスプレイ式ブックスタンドの作り方の一例を紹介する。
準備するもの
すのこ2枚、サンドペーパー、ボンド・グルーガン、釘、ハンマー、ペンキ・刷毛など(着色する場合)、のこぎり
手順1
1枚目のすのこ(ブックスタンドの本体用)の平板は、表面がなめらかであっても裏面はザラザラしている場合がある。裏面や角材には、本が傷まないようにサンドペーパーをかけてなめらかにする。
手順2
もう1枚のすのこを分解する。釘などで板が打ち付けられているすのこなら、ゲタのついている裏面からハンマーで平板を叩いたり、ボンドなどで接着されているときは、接着面にマイナスドライバーなどを差し込んで、テコのように動かすとはずしやすくなる。
手順3
解体したすのこの平板を、本来なら床などに設置するゲタの面に、釘やボンドで貼り付ける。ゲタを底にした浅いポケットを作るイメージだ。これを取り付けると、単に本を立てかけるよりも、本が差しやすく落ちにくくなる。
平板の代わりに、段ボールなどの厚紙を使ってもよいし、100円ショップなどにあるタオルかけ用のアイアン棒(ねじや両面テープで固定するもの)をゲタの少し上に取り付けるのもよいだろう。
平板の代わりに、段ボールなどの厚紙を使ってもよいし、100円ショップなどにあるタオルかけ用のアイアン棒(ねじや両面テープで固定するもの)をゲタの少し上に取り付けるのもよいだろう。
手順4
解体したすのこの平板1枚を、すのこの短辺の長さに合わせてカットする。すのこを壁に立てかけたとき、床に接地する部分の裏側に平置きし、釘やボンドで貼り付ける。本体のすのこがななめになっている分、少しすきまが開くので、気になるなら平板を斜めに削るとよいが、ボンドやグルーガンを厚めに盛って接着すれば削らなくても大丈夫。
これがブックスタンドの底板になる。底板を取り付ければ、すのこが少しずつ前にせり出してバタンと倒れてしまう心配もなくなるだろう。
平板をカットするのこぎりが家になかったり、カットするのが面倒な時は、100均にある「家具の転倒防止」のための樹脂製パーツ(三角形のブロックのようなもの)を、すのこ板の床の接地面に正面から押し込んでやるだけでも、前にせり出して倒れるのを防止できる。
これがブックスタンドの底板になる。底板を取り付ければ、すのこが少しずつ前にせり出してバタンと倒れてしまう心配もなくなるだろう。
平板をカットするのこぎりが家になかったり、カットするのが面倒な時は、100均にある「家具の転倒防止」のための樹脂製パーツ(三角形のブロックのようなもの)を、すのこ板の床の接地面に正面から押し込んでやるだけでも、前にせり出して倒れるのを防止できる。
手順5
全体を好みの色にペイントしたり、柄を描くなどして仕上げる。
結論
スタンダードタイプの本棚制作には強度的に向かないすのこだが、独特の形状を利用することで、センスのよいディスプレイタイプのブックスタンドが2~3時間のDIYで作ることができる。子供との「大工さんごっこ」にもぴったりだ。短時間で安価にでき、初心者でも楽しめる手作りインテリア。1度挑戦してみてはいかがだろうか。