1. 関東と関西で違う?暑中見舞いを出すのに適した時期は?
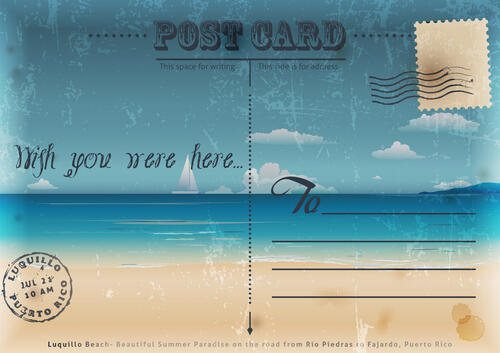
暑中見舞いは、夏の暑さが厳しい時期にお客様やなかなか会えない方に近況を報告したり安否を伺ったりするためのもので、あいさつや報告をするいい機会になる。例えばお中元のお礼や結婚・出産の報告は暑中見舞いとして送るのがおすすめだ。お店や会社であれば、イベントやキャンペーンの案内を送るのにも適しているし、おすすめの商品を紹介するのにも向いている。
暑中見舞いを送るタイミング
いざ暑中見舞いを送ろうと思ったとき、どのタイミングで出せばよいかわからない方も多いはずだ。暑中見舞いを出すタイミングには諸説あり、小暑(7月7日頃)から立秋(8月7日頃)までといわれることが多いが、だいたいは梅雨が明けたあとから立秋をむかえる前までに送るのが一般的とされているようだ。
梅雨明けというと、例えば関東だけ取り上げても時期はまちまちである。また、全国でみても1ヶ月ほど時期にズレが生じることもあり、関東と関西とで梅雨明け時期が異なることもよくある。関東と関西のどちらかが梅雨明けしていなくとも厳密に梅雨が明けるのを待つ必要はなく、暑さが増して夏らしくなれば暑中見舞いを出しても問題ないようだ。
梅雨明けというと、例えば関東だけ取り上げても時期はまちまちである。また、全国でみても1ヶ月ほど時期にズレが生じることもあり、関東と関西とで梅雨明け時期が異なることもよくある。関東と関西のどちらかが梅雨明けしていなくとも厳密に梅雨が明けるのを待つ必要はなく、暑さが増して夏らしくなれば暑中見舞いを出しても問題ないようだ。
2. 暑中見舞いはがきの基本の書き方

暑中見舞いは、はがきで出すのが一般的である。暑中見舞いについて厳密な書式があるわけではないが、書く際は以下の4つのブロックで構成するのがよいだろう。
暑中見舞いの挨拶
こちらは「暑中お見舞い申し上げます」といった類の文言であり、はがきの目立つ部分に大きく書くとよいだろう。
時候の挨拶からはじまる主文
こちらでは季節感についてしたためつつ相手の健康状況を気遣うような言葉を書き、そのあとに自身の近況報告をするとよいだろう。
結びの挨拶
暑中見舞いの最後は、相手を思いやる言葉で締めくるのが一般的である。
日付
日付(詳細な日付は書かず、「盛夏」などと書く)を記して完成だ。なお、はがきは縦書き・横書きどちらでもOKである。
3. ビジネス向けの暑中見舞いの文例

お客様や取引先に送るビジネス向けの暑中見舞いには、決まった言い回しがよく使われている。一般的な暑中見舞いではなくビジネス仕様の文言をしたため、失礼のないようにしたいものだ。
時候の挨拶からはじまる主文の文例として、ビジネス向けの暑中見舞いには以下のようなものが挙げられる。
時候の挨拶からはじまる主文の文例として、ビジネス向けの暑中見舞いには以下のようなものが挙げられる。
ビジネス向け時候の挨拶
「平素は格別のお引き立てをたまわり御礼申し上げます。今後ともなお一層のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。」
「毎々格別のお引き立てをたまわり厚く御礼を申し上げます。酷暑の折柄ご自愛ならびにご発展のほどお祈り申し上げます。」
「平素はひとかたならぬご厚情にあずかりますこと心より御礼申し上げます。連日の酷暑のなか皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。今後ともなお一層ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。」
ビジネス向けの暑中見舞いでは、以下のように夏季休業をあわせて案内するケースもある。
「さてこのたび夏期休暇のため誠に勝手ではございますが左記の通り休業させていただきます。ご迷惑をおかけすることとは存じますが御了承下さいますようお願い申し上げます。」
「毎々格別のお引き立てをたまわり厚く御礼を申し上げます。酷暑の折柄ご自愛ならびにご発展のほどお祈り申し上げます。」
「平素はひとかたならぬご厚情にあずかりますこと心より御礼申し上げます。連日の酷暑のなか皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。今後ともなお一層ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。」
ビジネス向けの暑中見舞いでは、以下のように夏季休業をあわせて案内するケースもある。
「さてこのたび夏期休暇のため誠に勝手ではございますが左記の通り休業させていただきます。ご迷惑をおかけすることとは存じますが御了承下さいますようお願い申し上げます。」
結論
暑中見舞いは、梅雨が明けたあと立秋をむかえる前までに出すのが一般的である。時期を逃さないのはもちろんだが、書き方の基本もきちんと押さえておきたいところだ。ビジネス向けの暑中見舞いの場合は、決まった言い回しを使いこなして失礼のないようにしたい。







