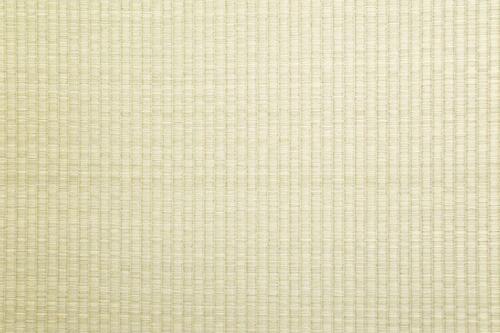1. 畳のカビの原因は湿気

カビの発生原因
カビは、以下の3つの原因がそろったときに発生しやすい。このような環境が続くとカビが目に見える形で繁殖するので注意しよう。
- 湿度75%以上
- 温度20~30℃
- カビの栄養分となるホコリなどの汚れ
畳の特性
畳には湿度を吸収しやすい特性があるので、高温多湿になりやすい6月から9月にかけての時期は畳にカビが発生しやすい。多くの場合、天然イ草が使われている畳の表にカビが発生する。これまで畳に付着していたホコリや汚れがカビの栄養分となり、梅雨に入って一気に湿度が上がるとカビが繁殖する原因になってしまうのだ。
とくに畳が使用して1年から2年ぐらいの新品の状態だと、素材に使われている天然イ草が空気の吸収と放出を自然的に行う性質がある。この過程で湿度が吸収されるため、ある程度の除湿機能が畳には備わっているわけだ。しかし、イ草が吸収できる水分の許容範囲を超えてしまうとカビが発生することになる。風通しが悪い部屋であれば余計にカビが繁殖しやすくなるだろう。新しいイ草ほど吸湿機能が強く働くので、新品の畳や表替えをしたばかりの畳はとくに湿度に注意しなければならない。
とくに畳が使用して1年から2年ぐらいの新品の状態だと、素材に使われている天然イ草が空気の吸収と放出を自然的に行う性質がある。この過程で湿度が吸収されるため、ある程度の除湿機能が畳には備わっているわけだ。しかし、イ草が吸収できる水分の許容範囲を超えてしまうとカビが発生することになる。風通しが悪い部屋であれば余計にカビが繁殖しやすくなるだろう。新しいイ草ほど吸湿機能が強く働くので、新品の畳や表替えをしたばかりの畳はとくに湿度に注意しなければならない。
畳にカビが発生しやすいケース
畳にカビが発生しやすい条件もあるので、以下の場合はとくに気を付けよう。カビの発生を抑えるにはこまめな風通しが重要なので、湿気が室内にこもらないようにしたい。
- 風通しや日当たりが悪く、空気や湿気がこもりやすい部屋に畳がある場合
- 昼間留守で閉め切っている部屋に畳がある場合
- 床下に湿気がこもりやすい物件の場合
- 新しい畳の上にラグなどの敷物をしている場合
2. 畳のカビを除去する方法

畳のカビを除去するときに気を付けるポイント、胞子を飛ばさないように取り除くことだ。胞子は軽くて空中に飛びやすいので、吸い込んでしまうと健康によくない。念のためマスクの着用をおすすめする。カビを除去するのに用意するのは70%から80%の濃度のエタノール(消毒用アルコール)だ。洗剤が液だれして手につかないようにゴム手袋もつけておこう。
用意するもの
- 消毒用アルコール
- 畳の目を掃除できるブラシ
- スプレー式ボトル
- ブラシをつけ置きできる大きさの容器
カビを除去する手順
- カビ除去に取りかかる前に窓をあけて風通しをよくする。
- 消毒用アルコールをスプレー式容器に入れてカビ全体に吹きつけ、15分ほど放置する。
- 容器に消毒用アルコールを入れてブラシを浸しておく。
- 15分経ったら消毒用アルコールに浸したブラシで畳の目にそってカビをかきだす。
- かきだしたカビをブラシですくい、容器に入れた消毒用アルコールで洗う。消毒用アルコールが汚れてきたら交換する。
- 畳のカビが取れるまで繰り返す。
- カビが一通り取れたら、消毒用アルコールを吹き付け、乾いた雑巾で畳の目にそって拭きとる。
- 除去が終わったら畳をよく乾燥させる。
3. 畳のカビの予防法

カビを予防するには、以下の方法が効果的である。
- 年に二回は大掃除をする
- 天気のいい日に外で畳を乾かしてカビを予防する
- 畳の片側をあげて床と畳の間に物を差し込むなどして風通しを行う
- 掃除機は持ち上げて吸う
- 梅雨や夏は換気を重点的に行う
- 汚れた素足では歩かない
もともと畳は旅館などの畳を除き、素足で歩くことはマナー違反となっている。足の裏の汗や皮脂、埃といった汚れが畳に付着してカビを繁殖させる原因となるためだ。畳は水拭きができないため、足裏の汚れがひどい場合は素足で畳の上を歩かないようにしてカビを予防しよう。
結論
畳にカビが生える原因や除去・予防法について紹介したがいかがだっただろうか。畳のカビ対策は、カビの発生要因のひとつである湿度をコントロールすること、発生源となる埃や汚れが表面につかないようにすることが大切である。日ごろから換気や掃除を行い、カビが発生する環境にならないように気をつけて畳のカビを防ごう。