目次
1. トイレつまりの直し方の前に!原因と前兆

トイレつまりは、直し方を誤ると悪化しかねない。まずは原因を知る必要がある。
トイレの構造
トイレの排水管はS字状に湾曲している。湾曲させて水を溜めることで下水の臭いが上がってくるのを抑えるためだが、つまりやすくもなっている。
トイレつまりの原因
- 水流が弱い
- 多量のトイレットペーパーやお掃除シートを流した
- ティッシュ、生理用品、おむつ、ペットシート、おしり拭きなどを流した
- 芳香剤のキャップ、子どものおもちゃなどを流した
- スマホ、ハンカチ、財布などを流した
といったことが考えられる。ただ、直し方はあるので「水が溢れた」「逆流した」などのケースを除き、焦らず原因に沿った直し方をしよう。
トイレつまりの前兆
- 一度水位が高くなってから下がる
- ゴボゴボなど異音が聞こえる
- 少量の水しか流れない
洗浄レバーを回した際、こんな症状が現れたらトイレつまりの前兆を疑おう。
2. トイレつまりの基本的な直し方

ご存知「すっぽん(正式名称:ラバーカップ)」は、トイレつまりの直し方の基本だ。すっぽんによるトイレつまりの直し方を説明する。
すっぽんの選び方
すっぽんには和式用と洋式用がある。よく見かけるお椀型が和式用だ。洋式トイレは排水口が狭いため、洋式用のすっぽんは、それに合うようにお椀の先に小さなカップが付いている。
すっぽんの使い方
続いて直し方だ。すっぽんの先を排水口にあて、柄の部分を持ってカップを軽く押しながら中を真空状態したら、上下に押したり引いたりしよう。強く引きすぎると逆流のおそれがある。静かに、少しずつがコツだ。
繰り返すうちに水が引き始めたら、洗浄レバーを少し回し、水位が上がってこなければ(いつもの正常な水位で止まれば)つまりは解消したと考えられる。洗浄レバーを全開にして流し、最終確認をしよう。
逆に水が引かなければ、小さくグっと押して少し引く、といった動作を繰り返そう。
繰り返すうちに水が引き始めたら、洗浄レバーを少し回し、水位が上がってこなければ(いつもの正常な水位で止まれば)つまりは解消したと考えられる。洗浄レバーを全開にして流し、最終確認をしよう。
逆に水が引かなければ、小さくグっと押して少し引く、といった動作を繰り返そう。
3. すっぽん以外のトイレつまりの直し方
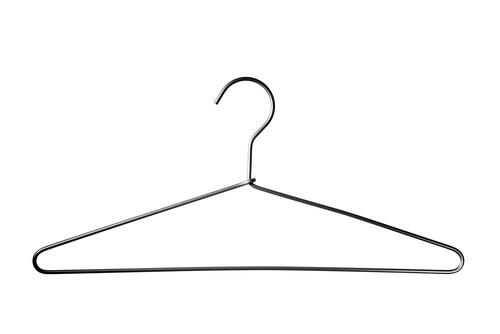
すっぽん以外のトイレつまりの直し方も覚えておこう。
ハンガーを使った直し方
まずはハンガーを使った直し方だ。ハンガーは針金製で柔らかめのものを使おう。ペンチなどで切って伸ばし、先端を輪っか状にしてトイレの排水口に挿入する。異物に当たったらハンガーを少しずつ動かして削っていこう。水が流れ始めれば解消も近い。
ワイヤーブラシを使った直し方
次に、排水管掃除用のワイヤーブラシを使った直し方だ。先端がブラシ状になったワイヤーをトイレの排水口から配管の奥へ押し込んでいくのだが、このときグルグルとねじりながら押し込むとつまりに引っかかりやすい。押し込んだらつまりを崩す、引っ掛けるといったイメージでワイヤーを動かしてみよう。水が引いてくれば成功だ。
真空管パイプクリーナーを使った直し方
すっぽんにポンプが付いたもので、すっぽんよりも吸い込む力がある。使い方はすっぽんと同じで、排水口にゆっくりとカップ部分を押し付け、レバーをゆっくり引いたり押したりを繰り返す。
業者への依頼も検討
いずれの方法も、試してみて解消しなかったら無理をして続けず、いったん作業を中止して業者への依頼を検討しよう。
4. トイレのつまりの直し方の注意点

トイレつまりの直し方はほかにもあるが、注意点をお伝えしておく。
お湯を使った直し方
お湯を使った直し方は有名だろう。トイレットペーパーによるつまりには有効だが、便器は陶器だ。熱湯を流すと、ヒビ割れなど新たなトラブルが想定されるため注意したい。
お酢と重曹を使った直し方
つまりの元がトイレットペーパーや尿石だったときの直し方だ。だが、お酢と重曹を混ぜると炭酸ガスが発生する。それぞれの分量は判断が難しいうえ、トイレの配管内は炭酸ガスや水の逃げ道がなく、溢れるおそれもあるので注意したい。
5. 直し方と一緒に押さえたいトイレつまり予防法

上記の直し方を実践してつまりが直ったら、次は予防をしよう。最後に、直し方とあわせて覚えておきたいトイレつまり予防の5箇条をお伝えする。
1.トイレの説明書を読み、流せる/流せないものを確認する
2.トイレ内にスマホなど小物を持ち込まない
3.芳香剤のキャップなどは便器の上で開閉しない
4.子どもをトイレで遊ばせない
5.トイレットペーパーは溶けやすいものを選び、一度に大量に流さない
このような日々の心がけでトイレつまりは予防できる。直し方を覚えるよりも簡単だ。
1.トイレの説明書を読み、流せる/流せないものを確認する
2.トイレ内にスマホなど小物を持ち込まない
3.芳香剤のキャップなどは便器の上で開閉しない
4.子どもをトイレで遊ばせない
5.トイレットペーパーは溶けやすいものを選び、一度に大量に流さない
このような日々の心がけでトイレつまりは予防できる。直し方を覚えるよりも簡単だ。
結論
トイレつまりの直し方や注意点などを解説してきた。これらの方法で水が引かないときは、無理に続けるのではなく業者に相談しよう。トイレットペーパー以外は流さないなど、日頃から予防する意識も大切になってくる。







