1. 窓に結露が!発生原因と放置するデメリット

窓に結露ができる原因と結露を放置するデメリットを見ていこう。
原因
- 部屋の中と屋外との温度差が大きい
- 部屋の湿度が高い
冬に窓の近くが寒くなるのは、窓が外気に冷やされて冷たくなるからだ。窓付近の空気が冷えると気体から液体に変わる。これが結露だ。
もうひとつは、部屋が高湿度になっていること。気温に対する飽和水蒸気量を超えた場合、余った水蒸気は水滴となって現れる。これは窓に限らず、床や家具などの結露の原因にもなる。
もうひとつは、部屋が高湿度になっていること。気温に対する飽和水蒸気量を超えた場合、余った水蒸気は水滴となって現れる。これは窓に限らず、床や家具などの結露の原因にもなる。
放置するデメリット
- 窓のサッシや木材部分(巾木など)が傷む
- 黒カビが発生する
- カビの胞子を人間が吸い込んでしまう
窓の結露を放置すると、やがて下へ流れ落ちて溜まる。濡れたままのサッシや巾木などが傷んだり、雑菌やホコリが混じって黒カビが発生したりすることもある。さらに放置すれば、家具や壁、床、カーテンなどにも黒カビが広がる、カーテンが剥がれるといったことも起こる。
そのうえ黒カビの胞子は非常に軽く、空気中を浮遊するので人間が吸い込んでしまうおそれもある。体質によってはアレルギーや喘息を引き起こす可能性も出てくる。
窓の結露自体は人体に害を及ぼすものではないが、放置するデメリットこそあれ、メリットは何一つない。
そのうえ黒カビの胞子は非常に軽く、空気中を浮遊するので人間が吸い込んでしまうおそれもある。体質によってはアレルギーや喘息を引き起こす可能性も出てくる。
窓の結露自体は人体に害を及ぼすものではないが、放置するデメリットこそあれ、メリットは何一つない。
2. 窓の結露を解消する方法

窓の結露はその都度、雑巾で拭き取ったりスクイージーで除去したりすれば解消する。だが、原因を断たねばまたすぐに結露ができるだろう。湿度や温度を管理して、窓に結露が生じにくい環境にすることが大切だ。
窓の結露の解消法
- 換気して部屋の温度や湿度を下げる
- 加湿器をこまめに止めて湿度を管理する
- サーキュレーターなどで空気を循環させる
- 除湿剤を置く、除湿機を使用するなどして湿度を下げる
こうした方法で窓の結露は解消できる。手軽なのは換気扇を回したり、窓を開けたりする方法だ。ただ、冬の寒い時期に窓を開けるのは辛い。そこで、そもそも結露ができにくい窓にする方法も覚えておこう。
食器用洗剤を塗る
先に窓をキレイに掃除しておこう。食器用洗剤を水で20〜30倍に希釈し、雑巾に含ませるなどして窓を拭いていくと、コーティング代わりになる。長持ちはしない、結露がひどいときは効果が薄いといったデメリットはあるが、何もしないよりはいいはずだ。
3. 窓の結露防止やカビ対策は便利グッズで
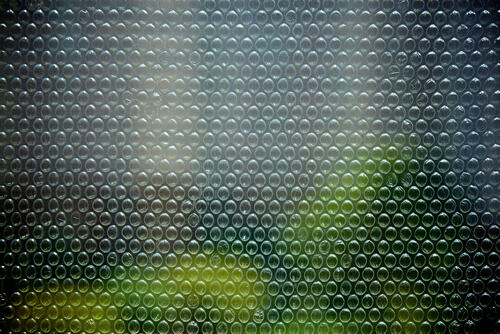
断熱シート
窓の結露を防ぐには、根本的な原因である温度・湿度管理が大切だが、あわせて使うとより効果的な便利グッズもある。たとえば断熱シート。水で貼るタイプや剥離紙を剥がしてそのまま貼るタイプがある。外気の温度が窓に伝わりにくくなるため、結露予防につながる。
スプレー、テープ
業務用の結露防止スプレーなども販売されている。徐々に効果は落ちるが、10日程度は持続するので手間は減らせるだろう。結露が窓の下に溜まるのを防ぐなら、吸水テープを貼る方法もある。サッシのカビや巾木の腐食などが防げるだろう。
二重窓
グッズではないが、二重窓(内窓)にしてしまう手もある。ただ、結露は大幅に軽減できるものの、すべての窓を二重窓にした場合はそれなりの費用が必要だ。賃貸物件なら事前許可や原状回復費用もかかるため、あまり現実的ではないかもしれない。
カビが生えたら
黒カビが生えたらできるだけ早く対処したい。ジェルタイプのカビ取り剤なら垂れずに塗りやすいのでおすすめだ。黒カビを除去したあとは、アルコールの除菌スプレーをこまめに吹きつけて除菌しよう。
結論
窓の結露をそのままにすると黒カビが生じ、建材だけでなく人体にも影響を及ぼすことがある。面倒かもしれないが、窓の結露はできるだけこまめに解消しよう。温度・湿度管理が難しいなら、グッズを使って結露を最小限に抑えたい。







