目次
1. 縄跳びの消費カロリーはどれくらい?

縄跳びの消費カロリーは跳び方などさまざまな条件で変わってくるが、ジョギングやウォーキングなどと比べて短時間で高カロリーを消費できる優秀な運動であることがわかる。
ジョギングの1.3〜2倍程度の消費カロリー
個人差はあるが、たとえば同じ10分縄跳びと軽いジョギングをした場合、縄跳びはジョギングの1.3~2倍程度カロリーを消費できるといわれている。短時間で効率的にカロリーを消費できるという点は、縄跳びが注目され取り入れる方が増えている大きな理由といえるだろう。
2. 縄跳びの消費カロリーの具体的な計算方法

縄跳びの消費カロリーが目に見えれば、モチベーションを保つために大いに役立つ。消費カロリーは「METs」という運動強度を表す単位を使った、以下の計算式で求められる。
「METs」を用いた縄跳びの消費カロリーの計算方法
METs×運動時間(h)×体重(kg)×1.05=消費カロリー
METsは安静時を「1」とし、運動しているときと安静にしているときを比較した結果、何倍のカロリーが消費されたかを数字で表す際に用いる単位だ。(独)国立健康・栄養研究所が作成した「身体活動のメッツ(METs)表」(※1)には、いろいろな運動のMETsが掲載されている。計算式のMETsの部分に該当する運動の数値を入れれば、カロリー消費量の計算が可能だ。
METsは安静時を「1」とし、運動しているときと安静にしているときを比較した結果、何倍のカロリーが消費されたかを数字で表す際に用いる単位だ。(独)国立健康・栄養研究所が作成した「身体活動のメッツ(METs)表」(※1)には、いろいろな運動のMETsが掲載されている。計算式のMETsの部分に該当する運動の数値を入れれば、カロリー消費量の計算が可能だ。
縄跳びはペースによってMETsが変化する
- ゆっくりペース 毎分100回未満/8.8METs
- ほどほどペース 毎分100~120回/11.8METs
- 速いペース 毎分120~160回/12.3METs
たとえば60kgの方がゆっくりペースで30分縄跳びをした場合、消費カロリーは
【8.8METs(縄跳び:ゆっくりペース)×0.5(h)×60(kg)×1.05=277.2kcal】
となる。このように、METsを用いると縄跳びの消費カロリーが簡単にわかる。消費カロリーが目に見えるようになれば、上述のようにモチベーションの向上・維持にもつながるし、食事の組み立てもしやすくなるなどメリットが多い。
【8.8METs(縄跳び:ゆっくりペース)×0.5(h)×60(kg)×1.05=277.2kcal】
となる。このように、METsを用いると縄跳びの消費カロリーが簡単にわかる。消費カロリーが目に見えるようになれば、上述のようにモチベーションの向上・維持にもつながるし、食事の組み立てもしやすくなるなどメリットが多い。
3. 縄跳びでカロリー消費を狙うなら20分以上跳ぼう

縄跳びでカロリーを消費したい方は、20分以上跳ぶことを目標にしよう。その理由は次のとおりだ。
脂肪や糖がエネルギー源に切り替わる
有酸素運動において脂肪や糖がエネルギー源に切り替わるのは、運動開始から20分後以降であるといわれている。このため、縄跳びで効果的にカロリーを消費するにはできる限り長い時間跳ぶことが理想だが、初心者の方や久しぶりの方がいきなり長く跳び続けるのはハードだろう。その場合は無理をしないことが大切だ。まずは10分跳ぶことを目標にするとよい。ほどほどのペースで跳べば10分でおよそ1,000回跳ぶことができる。
4. 縄跳びで効果的にカロリーを消費するためのポイント

続いて、縄跳びで効果的にカロリーを消費するためのポイントをお伝えする。上述のように、縄跳びの消費カロリーは跳び方でも違る点は忘れないようにしよう。
ポイント1.縄を回すスピードを普段よりも速くする
縄を回すスピードが速くなれば、おのずと跳ぶスピードも速くなる。跳ぶスピードが速くなれば運動強度が高まりカロリー消費量もアップする。初めはゆっくりペースで始め、慣れてきたらペースを上げるなどして運動強度を高めよう。
ポイント2.片足ずつ交互に跳ぶ
片足ずつ跳ぶと普通の縄跳びに「もも上げ」のような負荷が加わり、運動効果が高まる。また筋肉の中でも大きい「大腿四頭筋(太もも前の筋肉)」を鍛えることで基礎代謝の向上効果も期待できる。基礎代謝が上がれば、日常動作や運動でカロリーを消費しやすくなり、太りにくい体質を手に入れられる。跳ぶことに慣れてきて、縄跳びでより一層カロリーを消費したい方は片足跳びをするとよいだろう。
ポイント3.継続して運動をおこなう
先述のように脂肪や糖が有酸素運動に使用されるエネルギー源に切り替わるのは、運動開始から20分後以降とされている。20分を超えて、より長い時間縄跳びをすればその分だけ消費カロリーも増加する。1日最低30分は跳びたいところだ。30分続けるのが難しい方は、1日15分×2セットなど分割してもよい。継続しやすいように工夫をしよう。最近ではスマホと連動する縄も登場している。跳んだ回数や消費カロリーを表示できるので、気になる方はぜひそういった縄を探してみてはいかがだろうか。
ポイント4.筋トレを一緒におこなう
縄跳びだけでもカロリーを消費できるが、あわせて筋トレをおこなうのがおすすめだ。筋トレをすると筋肉や骨を強くするホルモンが分泌される。ホルモンの分泌によって血糖値が上昇した状態で縄跳びをおこなうと、より効果的にカロリーを消費できる。縄跳びとあわせて筋トレもぜひ取り入れてみよう。
5. ところで縄跳びの効果やメリットとは?

縄跳びは跳ぶというシンプルな動きながら、全身にある「47種類」もの筋肉を使うという優れた有酸素運動だ。跳ぶ動作と着地により、とくに大腿四頭筋や腰の上部が効率的に鍛えられる。改めて、縄跳びによって期待できる効果を確認していこう。
基礎代謝の向上による脂肪燃焼効果
お伝えしたように、縄跳びをすることで大腿四頭筋といった大きな筋肉を鍛えることができる。それにより基礎代謝が向上し、脂肪燃焼効果のアップが期待できる。短時間でカロリーを消費しやすい点も魅力である。
心肺機能や持久力の向上
一般的に有酸素運動というと筋トレなどと比べて軽そうなイメージがあるかもしれないが、縄跳びはその有酸素運動の中でもハードな部類だ。そのうえある程度の時間連続で跳び続けたり、継続したりしやすい運動でもあることから、心肺機能や持久力の向上が期待できる。
体幹の強化、下半身の引き締め効果
跳ぶ動作を安定させてバランスを取るため、腹筋や体幹(インナーマッスル)などが使われる。またふくらはぎや太ももの筋肉を鍛えることによる、下半身の引き締め効果も期待できる。
6. 縄跳びのバリエーションと跳び方
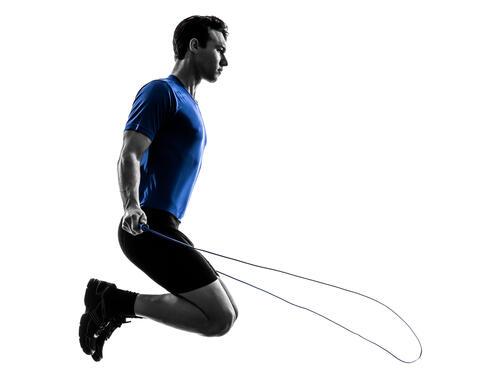
縄跳びはいろいろな跳び方ができるのも魅力のひとつだ。1パターンでは飽きてしまうかもしれないので、ぜひいろいろなバリエーションを覚えておくとよいだろう。
前跳び
もっとも基本となる跳び方である。リズムよく跳び続けることが大切だ。初心者の方や、小学生以来跳んでいないといった久しぶりの方は、まず前跳びが安定してできるようになるまで練習しよう。
後ろ跳び
縄を後ろに回しながら跳ぶのが後ろ跳びだ。前跳びと違い、跳ぶ瞬間に縄が見えないことからやや難易度が高い。前跳びに慣れて(飽きて)きたら、ちょっとした変化をつける意味で取り入れるとよいだろう。
二重跳び
1回のジャンプで縄を2まわしするのが二重跳びである。前二重跳びと後ろ二重跳びがある。通常の前跳びや後ろ跳びよりも高くジャンプする必要があるうえ、縄を速くまわす技術も必要なため難易度はやや高めである。引っかかってしまうという方は、跳んだときに膝を曲げるといった工夫をしてみよう。
交差跳び・あや跳び
左右の腕を交差させた状態で跳ぶのが交差跳び、その交差跳びと前跳びを交互に繰り返すのがあや飛びだ。いずれも難易度は高い。交差させて跳ぶときは腕をしっかり伸ばさないと引っかかりやすいので気をつけよう。まずは交差跳びができるようになってからあや飛びにチャレンジするのがおすすめだ。
はやぶさ跳び
あや飛びの二重跳びバージョンがはやぶさ跳びである。1回のジャンプで交差跳びと前跳びをするという、かなり難易度の高いワザだ。小学校で扱う縄跳びの授業の中でも、もっとも高難易度とされている。長時間継続するのが難しいため、ダイエット目的などの方は前跳びがよいかもしれない。
7. 筋トレやダイエットに縄跳びを取り入れる際の注意点

縄跳びは手軽に取り入れられる運動だが、跳ぶ動作と着地をひたすら繰り返すため「足首」「膝」「腰」などに負担がかかりやすい。慣れない方は決して無理をしないことが大切だ。また縄跳びを始める前は必ずストレッチをおこなうようにしよう。腰や太もも、ふくらはぎやアキレス腱、足首などを入念にほぐしておくことでケガを防止してほしい。可能であれば、クッション性の高いシューズに履き替えるといったこともおすすめだ。
8. 消費カロリーが多い縄跳びを上手に取り入れよう

縄跳びはジョギングやウォーキングなどと比べて消費カロリーが多い。しかも継続しやすい運動なので、ぜひ積極的に取り入れよう。筋トレと縄跳びを交互におこなうのもよいだろう。また、縄跳びは単に運動としてだけでなく、ジョギングやジムでのトレーニング前のウォーミングアップとしてもおすすめできる。シンプルながら消費カロリーの多い優秀な有酸素運動、縄跳びをぜひこの機会に見直してみてはいかがだろうか?
結論
縄跳びは短時間でカロリーを消費できる効率のよいトレーニングだ。忙しくジムなどに通えない方でも、縄と少しのスペースがあればできる。消費カロリーや跳んだ回数、減少した体重など数字や結果が目に見えれば、継続するためのモチベーションにもつながる。本稿で紹介した消費カロリーの計算方法などもぜひ取り入れつつ、効率的に鍛えてほしい。
(参考文献)
- 1:(独)国立健康・栄養研究所「身体活動のメッツ(METs)表」
https://www.nibiohn.go.jp/eiken/programs/2011mets.pdf






