目次
- 1. 自重力トレーニングとは?
- 2. 自重力トレーニングのメリット
- 3. 自重力トレーニングの効果を高めるコツ
- 4. 自重力トレーニングメニュー | 胸筋編
- 5. 自重力トレーニングメニュー | 背筋編
- 6. 自重力トレーニングメニュー | 腹筋編
- 7. 自重力トレーニングメニュー | 腕編
- 8. 自重力トレーニングメニュー | 脚編
- 9. 自重力トレーニングは毎日してもいい?
- 肩幅より少し広めに手を広げ、床につける
- 少し開いた脚を後ろに伸ばしてつま先だけで身体を支え、首から脚までがまっすぐになるような体勢をとる
- 肘を曲げて身体を下ろす
- 床に身体がつくくらいまで下ろしたら、ゆっくり戻す
- まずはうつ伏せで寝転がる
- 普通の腕立て伏せよりも、肩幅一つ分外側に手を置く
- 身体をゆっくり持ち上げて、首から脚が真っ直ぐになるようなセットポジションを作る
- 広背筋を収縮するように意識しながら身体をゆっくりと下ろす
- 床に身体がつくくらいまで下げたらその体勢を少しキープする
- 手のひら全体を使って押し上げるように元の体勢に戻す
- イスやベンチなどに足を乗せ、腕立て伏せの体勢になる
- 手幅を肩幅より少し広げ、床につける
- 床ギリギリまで身体を下ろす
- 地面を押し上げるように身体を元に体勢に戻す
- 肩幅より広い位置にぶら下がり、バーの中央あたりに視線を合わせる
- バーと顎が同じ高さになるまで身体を持ち上げる
- 上まで上がったら少しキープする
- 肘が伸ばしきらない程度にゆっくりと身体を下ろす
- 仰向けの状態で自然に手を地面に置き寝転がる
- 膝を90度に曲げ、脚を肩幅に広げる
- 肩甲骨を支点にして、膝・腰・肩が一直線になるように骨盤を上げる
- うつ伏せで寝転がる
- 両手を頭の後ろか耳の横に添え、肘を横に伸ばす
- 上半身ばかりを上げ過ぎないように、胸と両脚をゆっくり上げる
- 背筋が刺激されているのを感じたら、そのままの体勢でキープする
- 身体をゆっくり下げる
- 仰向けに寝転がり、膝を90度に曲げる
- 腕を耳の横に添え、腰が上がらないよう注意しながら上体を起こす
- そのまま3秒キープする
- 上体を起こすときの2倍の時間をかけてゆっくりと元の状態に戻す
- 仰向けで寝転がり、ふくらはぎが床と平行になるように膝を上げる
- 両手を頭の後ろに置き、上体を軽く起こす
- 片脚はまっすぐに伸ばし、もう片脚は胸に引き寄せる
- 3.のときに、伸ばした脚の方の上体を、もう片方の引き寄せた脚に寄せる
- 今度は逆の脚で同じ動作を行い、繰り返す
- 肘とつま先で体重を支えるようにうつ伏せになる
- 背中のラインがまっすぐになるように意識して初めは20秒キープする
- 腕立て伏せの体勢になり、肩の真下に手をつくように手幅を狭める
- 肘が脇から離れないように意識しながら、身体をゆっくりと下ろす
- 手に胸がつくくらい身体が下がったら、床を押すように元の体勢に戻す
- イスやベンチなどを背にして立ち、肩幅に広げた両手をおく
- そのままの体勢で少し俯きながら腰を下げる
- お尻が床につくくらいまで下がったら肘を伸ばして元の体勢に戻す
- カールさせる腕の手首を逆の手で押さえる
- 押さえる手は常に下方向に力を加え、カールさせる腕は対抗するように胸の前まであげる
- 腕を逆にして同様に行う
- 肩幅に脚を開き、つま先は外側に向ける
- 手をまっすぐ前に伸ばす
- 息を吸いながら、股関節から曲げるようにゆっくりと腰を下ろす
- 太ももが床と平行になるまで腰を下ろしたら、息を吐きながらゆっくりと元の体勢に戻す
- 肩幅より広めに脚を広げ、つま先は外側に向ける
- 胸の前で平行になるように両手を組む
- 背筋に力を入れた状態でしっかりと直立し、息を吐きながら腰をゆっくり下ろす
- 太ももが床と平行になるまで腰を下ろしたら、息を吐きながらゆっくりと元の体勢に戻す
- 壁際に直立した状態で、脚を肩幅より少し狭めに広げる
- 両手を肩幅に広げ、壁につける
- かかとを最大の高さまで上げ、ゆっくりと下ろす
1. 自重力トレーニングとは?

自重力トレーニングとはトレーニング機器を使わずに、自分の体重を負荷として行う筋トレだ。具体的には腕立て伏せや上体起こしなどのことを指す。自重力トレーニングは身体一つあればジムでも自宅でもできるので、初心者でも始めやすいと人気があるのだ。取り組みやすさだけでなく、メニューや種類の豊富さも自重力トレーニングの魅力である。
2. 自重力トレーニングのメリット

自重力トレーニングのメリットを紹介していこう。
自宅で簡単に取り組める
自重力トレーニングは思い立ったらすぐにできるので、自宅で簡単に始めることができる。また、トレーニングを始めたばかりの頃に陥りやすい3日坊主も、自宅で気軽に行えるので続きやすいというメリットもあるのだ。
器具を使わない
自重力トレーニングは自分の体重を負荷にして行うので、基本的には器具を揃えなくても始めることができる。
怪我する危険性が低い
自重力トレーニングは負荷が自分の体重だけなので、身体のコントロールがしやすく、怪我のリスクが少ないのだ。
トレーニングメニューが豊富
トレーニングメニューが豊富なのが自重力トレーニングのメリットの一つだ。筋トレや初心者でもできるメニューが多く、飽きずにトレーニングができる。
3. 自重力トレーニングの効果を高めるコツ

自重力トレーニングの効果を高めるコツを紹介していこう。
限界まで追い込む
トレーニング初心者は10~15回を3セット程行うのが理想だが、筋肉がついてきて継続できるようになったら、回数やセット数を増やしたり、スローで行ったりしてみよう。鍛えたい部分への刺激がマンネリ化しないように常に限界まで行うことが重要だ。
休憩時間を短くする
休憩時間の長さも、自重力トレーニングの効果を高めるうえで重要なポイントだ。休憩時間が長すぎると、筋肉の成長に必要なホルモンが分泌されなくなり、筋肥大の効果が薄れる恐れがあるので、休憩時間を短くして時間を無駄にしないように行おう。
ゆっくりとしたスピードで行う
自重力トレーニングを行う際、重力に頼って身体を素早く下ろしてしまいがちだろう。しかし、身体を下ろす際にもエキセントリック収縮という負荷がかかっている。素早く身体を下ろしてしまってはもったいないので、ゆっくりとしたスピードで行おう。
4. 自重力トレーニングメニュー | 胸筋編

胸筋を鍛える自重力トレーニングを紹介していこう。
ノーマルプッシュアップ
20回3セットを目安に行うといいだろう。
ワイドプッシュアップ
ワイドプッシュアップはノーマルプッシュアップより負荷がかかるので、ノーマルプッシュアップでは物足りない方におすすめの自重力トレーニングだ。
デクラインプッシュアップ
主に、大胸筋上部を鍛えることができる自重力トレーニングだ。
5. 自重力トレーニングメニュー | 背筋編

背筋を鍛える自重力トレーニングを紹介していこう。
チンニング
バーを使った自重力トレーニングだ。
ヒップリフト
初めは30秒キープすることから始めてみよう。
バックエクステンション
背筋を鍛えるトレーニングの中では基礎的なメニューなので、初心者でも取り組みやすい自重力トレーニングだ。
6. 自重力トレーニングメニュー | 腹筋編
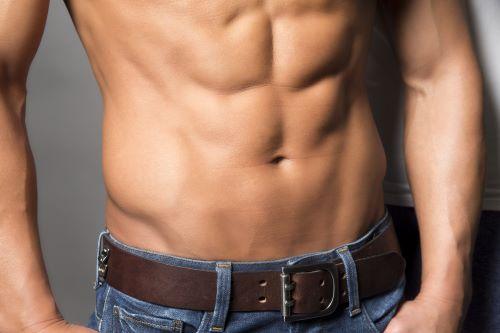
腹筋を鍛える自重力トレーニングを紹介していこう。
クランチ
1セット10回を、3セット程行えるような負荷で行うことが望ましい。
バイシクルクランチ
一般的な腹筋トレーニングとは異なり、ねじりの動作が入ることで、お腹の横に効く自重力トレーニングだ。
プランク
腹筋はもちろん、全身の筋肉を刺激することができる自重力トレーニングだ。
7. 自重力トレーニングメニュー | 腕編

腕を鍛える自重力トレーニングを紹介していこう。
ナロープッシュアップ
通常の腕立て伏せで満足できなくなった人は、このナロープッシュアップという自重力トレーニングがおすすめだ。
リバースプッシュアップ
背中を丸めるように行うとより効果的だ。
パームカール
3~4秒くらいで腕があがるくらいの負荷が望ましい。自重力トレーニングの中でも、唯一腕をメインに鍛えることができるトレーニングだ。
8. 自重力トレーニングメニュー | 脚編

脚を鍛える自重力トレーニングを紹介しよう。
ノーマルスクワット
スクワット15回は腹筋500回に相当するといわれるほど、効果が見込める自重力トレーニングだ。
ワイドスクワット
ノーマルスクワットよりも脚を広げた状態で行う自重力トレーニングだ。
スタンディングカーフレイズ
動作が小さい自重力トレーニングなので、正しいフォームで行うことが大切だ。
9. 自重力トレーニングは毎日してもいい?

自重力トレーニングはウエイトトレーニングの一つなので、超回復理論に準じて行う必要がある。トレーニングを行うと筋肉の損傷や筋繊維の裂傷が少なからず生じるだろう。そこで一定の休息期間を設けることで、トレーニング前よりも太く、強くなって回復する。その回復を超回復という。超回復にはトレーニングから48~72時間の休息が必要なので、自重力トレーニングは2日以上間隔を空けて行うことをおすすめする。自重力トレーニングを毎日行いたい場合は、部位を細かく変えながら行うといいだろう。
結論
自重力トレーニングは、器具をそろえずに自宅で気軽に行うことができるトレーニングだ。しかしその反面、継続するには根気が必要である。自重力トレーニングに取り組む際には、正しいフォームで行ったり、超回復理論を利用したりなど、効率よく鍛えられる知識を身につけておくことが大切だ。豊富なメニューをうまく組み合わせて、鍛える部位を変えながら継続的に行おう。






