目次
1. 肥満度の基本をおさらい
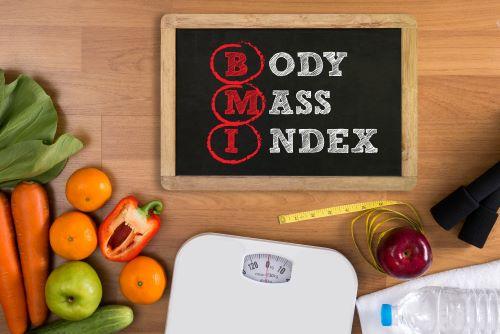
肥満度の計算について知る前に、まずは肥満に関する基礎的な知識をおさらいしておこう。
そもそも肥満とは何か?
そもそも肥満とは、体重が多いことに加え、体脂肪が過剰に蓄積した状態を指している。肥満は「内臓脂肪型肥満」、そして「皮下脂肪型肥満」の2つに分類され、内臓脂肪型の方が生活習慣病の発症リスクが高い。ほかにも病気を引き起こす可能性があるため、健康に生きるには肥満の予防と対策が重要といえる。
肥満度であるBMIとは?
肥満の定義は「脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数(BMI)25以上のもの」とされている(※1)。BMIはBody Mass Indexの略で、肥満度を示す体格指数として国際的に使われている。標準の値は22とされ、先ほどの定義の通りBMI25を超えると肥満に分類されてしまう。詳しい肥満度の計算方法は、次の項目で説明していこう。
2. 肥満度の計算方法と判定基準

次に、肥満度の具体的な計算方法と肥満度の分類を判定するための基準をまとめる。
肥満度の基本的な計算方法
肥満度は[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で求めることが可能だ。たとえば180cm85kgの男性の場合は、85÷(1.8×1.8)で肥満度の計算をするため、BMIは26.23...となる。前述の通りBMI25以上は肥満に分類されるので、この男性は肥満だといえるのだ。いまの自分を知るため、まず肥満度の計算をしてみよう。
ちなみに自分がどの体重を目指せばよいかの指標となる標準体重は、身長(m)の2乗×22で求められる。肥満の場合は、標準体重を目指すべき体重の目安にするとよいだろう。自分の身長と体重を入力するとBMIや理想体重、摂取カロリー目安まで計算してくれるサイトもあるので、そういったものを活用することもおすすめしたい。
日本肥満学会による肥満度分類
肥満はBMIの値によって4種類に分類されていることをご存じだろうか。日本肥満学会による分類(※1)では、25~30までが肥満1度、30~35までが肥満2度、35?40までが肥満3度、そして40以上が肥満4度とされている。
たとえば身長180㎝の場合、81?97.2kgが肥満1度、97.2~113.4㎏が肥満2度、113.4?129.6㎏が肥満3度、そして129.6㎏以上が肥満4度だ。
3. 肥満度が高いとなぜ危険なの?

ここまで肥満度の計算について見てきたが、そもそもなぜ肥満度を計算する必要があるのかというと、肥満にはさまざまな危険があるからだ。肥満度が高いとどのような危険があるのか、詳しく見ていく。
その1.生活習慣病のリスクが上がる
肥満との関係で最も注目を集めているのが、脂質異常症や高血圧、糖尿病といった生活習慣病だ。肥満をそのままにしていると生活習慣病が悪化し、血管がもろくなって動脈硬化を引き起こし、最終的には腎不全や心筋梗塞、脳卒中など大きな病気につながる可能性がある。
筋肉の動きを助ける物質であるインスリンの分泌が少ない人種である日本人は、少し太っただけで生活習慣病になるリスクが高い。つまり、日本人はとくに肥満にならないよう気を付ける必要があるのだ。
その2.そのほかの病気のリスクも上がる
肥満が引き起こすのは生活習慣病だけではない。肥満だと骨や関節への負担が大きくなり、膝や腰が痛む関節障害や高尿酸血症による痛風を起こしやすくなる。また突然死の原因の1つである睡眠時無呼吸症候群にも大きく影響し、免疫力の低下を招き感染症にかかりやすくなってしまう。
それに加え、前立腺がんや肝臓がんなどさまざまながんに対してリスクが上がるという指摘もあるなど、肥満は多種多様な病気を招いてしまうのだ。まずは肥満度の計算で自分の現状を知ることが大切である。
4. 必ずしも「肥満度が高い=危険」ではない

肥満度の計算で肥満とでたものの、実は危険ではないという場合もある。どういったケースが該当するのだろうか。
その1.筋肉質でBMIが高い可能性がある
筋肉は脂肪より重いため、筋肉量が多い男性の場合、BMIの値が高くなってしまう場合もある。格闘技やラグビー、アメリカンフットボールなど筋肉を多く使う競技のスポーツ選手の中にはBMIが30を超えている選手も多いのだ。肥満度の計算で肥満の値がでた場合に見た目が筋肉質であれば、筋肉の重さが原因という可能性も高い。
筋肉質な男性の場合には、体脂肪量や筋肉量を計測ができる体組成計を使用して自分の筋肉量を見ることにより、自分の身体の状態を把握できる。
その2.皮下脂肪が多くてBMIが高い可能性がある
同じ脂肪でも、身体のどこについているかで健康に対するリスクは大きく変わる。つまり、肥満度の計算で肥満の値であっても脂肪のつき方によってはさほど気にしなくてよい場合もあるというわけだ。
皮膚のすぐ下に蓄積する皮下脂肪は、さきほど挙げたような疾患を引き起こしにくい。つまり、皮下脂肪が多いことが原因でBMIが高い場合には、必ずしも危険とはいえないのだ。
5. 内臓脂肪型肥満の人はダイエットしよう

前項では、皮下脂肪が多くてBMIが高い場合の危険性は低いと述べた。しかし内臓脂肪が多いために肥満度の計算が肥満の値になった場合には、注意が必要だ。
内臓周りに蓄積する脂肪である内臓脂肪は、女性よりも男性につきやすいうえ、糖尿病や高血圧などを引き起こしやすい。つまり、肥満度の計算で肥満の値になった原因が内臓脂肪だと、病気にかかるリスクが大きく上がってしまうのである。
皮下脂肪と内臓脂肪は、脂肪がつく場所で見分けることが可能だ。内臓脂肪が多い場合にはお腹がぽっこりするため、リンゴ型肥満と呼ばれる。一方で皮下脂肪は太ももや腰周り、お尻など下半身につきやすいため洋ナシ型肥満と呼ばれるのだ。また市販の体組成計の中には体重の中に占める皮下脂肪の割合が見られるものもあるので、活用するとよい。
肥満度の計算をしたうえで、脂肪がついている場所や皮下脂肪の割合なども踏まえて内臓脂肪型肥満だとわかったら、ダイエットすることを考えてみよう。
結論
肥満度の計算方法や肥満の危険性について見てきた。内臓脂肪が多いタイプの肥満である場合にはとくに、標準体重を目指す必要があるといえる。肥満から脱出するためにも、生活習慣を見直して、ダイエットに励んでみてはいかがだろうか。
(参考文献)
※1出典:e-ヘルスネット(厚生労働省)|「肥満と健康」






