目次
- 鶏ささみ(※3):23.9g
- 牛もも(※4):19.2g
- 豚ロース(※5):19.3g
- いわし丸干し(※6):45.0g
- キハダマグロ(※7):24.3g
- 鶏卵(※8):12.2g
- 納豆(※9):16.5g
- プロセスチーズ(※10):22.7g
1. タンパク質の基本をおさらい

まずは、タンパク質の基本についておさらいしておこう(※1、2)。
タンパク質とは、エネルギーを生産する栄養素のひとつだ。20種類のアミノ酸が結合し、筋肉や臓器、髪の毛などを構成している。それだけでなく、ホルモンや酵素といった機能にも欠かせない成分で、生きていくうえで重要な栄養素といえるだろう。
タンパク質は、肉類や卵類、豆類などに多く含まれていて、中には体内で必要量が生成されず、食事から摂取すべきアミノ酸もある。
2. タンパク質ダイエットとプロテインダイエットの違い
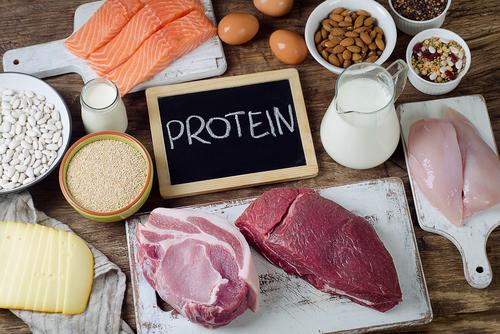
タンパク質ダイエットとプロテインダイエット。タンパク質を英語にするとprotein(プロテイン)なので、一見すると同じなのではという印象を受ける。しかし、タンパク質ダイエットとプロテインダイエットは、似て非なるダイエットなのだ。ここでは、タンパク質ダイエットとプロテインダイエットの違いについて理解しておこう。
タンパク質ダイエットとは?
タンパク質ダイエットとは、タンパク質の摂取量を増やし、炭水化物や脂質の摂取量を減らすダイエット法である。
私たちは、ごはんや麺類、パンなどを摂取する機会が多い。これらには炭水化物が多く含まれている。炭水化物のメインは糖質だ。糖質を摂取することで血糖値が上昇し、さらにインスリンも分泌される。インスリンは、血中にある糖を筋肉や脂肪などに取り込むため、結果的に太りやすくなってしまうのだ。
そこでタンパク質を積極的に摂り、炭水化物などの摂取量を減らし、ダイエットを目指していく。
プロテインダイエットとは?
プロテインダイエットには、プロテインが摂取できるサプリメント(粉末やドリンクなど)を用いる。食事や間食の一部をプロテインに換え、ダイエット効果を狙う方法だ。
たとえば、おやつの代わりにプロテインを摂取する、食事のおかずをプロテインに置き換えるといった具合で行う。
プロテインをサプリメントで補給する目的は、食事バランスを整えることにある。バランスの取れた食事にすることで、痩せやすい身体を手に入れるのだ。
また、運動をプラスして筋肉量を維持することで、さらにダイエットが実現しやすくなるだろう。
3. 成人男性のタンパク質の推奨量

成人男性の1日当たりのタンパク質摂取量は、どれくらいの量が推奨されているのだろうか。詳しく見てみよう。
1日あたり65gを目標に摂る
成人男性(18歳~64歳)の1日当たりのタンパク質目標摂取量は、65gである。生活習慣病予防のためにも、目標量は摂取したいものだ。
とはいえ65gのタンパク質が、いったい何をどれだけ食べたらよい量なのかわからない方もいるだろう。食品100g当たりのタンパク質含有量を、いくつか例を挙げて紹介しよう。
上記の量はあくまで目安であり、肉の品種や脂肪のつき方、製品によって変わってくる。
単純計算で65gのタンパク質を摂取するなら、1日で鶏ささみ100g、キハダマグロ100g、納豆100g食べる必要があるのだ。
また、活動量によってもタンパク質の適量が異なる。運動をしたり、仕事で身体を動かしたりと、普段から活動量が多い場合には、少し多めに見積もる必要がある。
4. タンパク質ダイエットの注意点

タンパク質ダイエットを行ううえで、注意しておきたい点が2つある。以下に紹介する点に留意したい。
その1.1度にまとめて食べない
タンパク質をたくさん摂取したいからといって、1日分の摂取量を1度にまとめて食べるのはよくない。なぜなら、1度に体内で吸収できるタンパク質の量は限られているからである。過剰分は排出されてしまったり、脂肪として蓄積されたりするので、タンパク質ダイエットをしていたとしても太ることがあるのだ。そのため、食事ごと、こまめにタンパク質を摂取することが望ましい。
その2.過剰にタンパク質を摂らない
タンパク質の過剰摂取も控えておこう。前述した通り、吸収しきれなかったタンパク質は、脂肪に変換してしまう恐れがある。タンパク質ダイエットをしているのに、余分な脂肪がついてしまったら元も子もない。そして、腎臓への負担にもなりかねない。
また、動物性のタンパク質は、便秘や下痢を引き起こす原因ともなりうる。腸内における悪玉菌の栄養分となるからだ。
タンパク質だけでなく、ほかの栄養素や食物繊維などをおろそかにせず、バランスに留意して摂取しよう。
その3.加工品は控える
ソーセージやハムといった加工品は、タンパク質ダイエットにあまり適していない。
確かに肉類ではあるが、未加工品と比べて塩分や添加物の量が多く、脂質や糖質も高いのだ。塩分や添加物を多く摂取してしまうと、健康面にも悪影響を与えかねない。
そのため、タンパク質に重点を置いているタンパク質ダイエットでは、できるだけ未加工品をチョイスするとよいだろう。
結論
タンパク質ダイエットは、タンパク質の摂取量を増やし、炭水化物や脂質などを減らしてダイエットを目指す方法である。だからといって、過剰にタンパク質を摂取してはダイエットにはならない。1日のタンパク質摂取目標量を目安に、ほかの栄養素とのバランスも整えてダイエットをしていこう。






