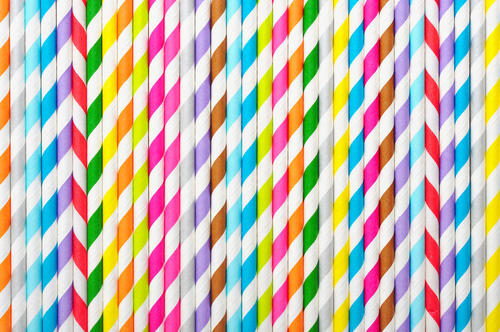1. 紙ストローの現状

昨今、話題になっている紙ストロー。ひと昔前は、水が染み込んで使いづらいと言われていたが、技術革新が進み、プラスチックストローと遜色のない製品が続々と登場している。
海外では
日本ではまだ始まったばかりに思える紙ストローであるが、海外ではすでにかなり浸透しているところもある。アメリカのシアトルでは、昨年の夏頃からストローを含む、プラスチック製の使い捨てカトラリーの使用が禁止された。街にあるのは、再利用できるプラスチックストローか紙ストローだけ。フランスでも、プラスチック製容器の禁止、インドでは2020年までに禁止などが掲げられている。
紙ストローの価格
最大の問題とも言えるのが、コスト面である。紙ストローはプラスチックストローに比べると高い。中小企業が紙ストローを取り入れるには、金銭面でまだ問題が残る。ただ、持続可能な社会を考えると、紙ストローへの転換やストローを使わない方法に変更するのが望ましいことは明白である。余談ではあるが、紙ストローはプラスチックストローに比べて、見た目におしゃれなものが多いので、そういった面でも有用性は高いかもしれない。
2. 紙ストローとプラスチック

なぜ紙ストローなのか?
紙ストローがここまで注目されたのは、それ自体の魅力というよりも、プラスチックストローの代替え品という側面が大きい。ストローに限らず、プラスチック製品の環境に対する影響は、年々増大している。この現状を打開する一手として、紙ストローが持ち出されたのだ。
プラスチックとは
プラスチックの原料は、石油である。熱や圧力をかけることで自由に形を作ることができるため、ストローのみならず、多くのシーンで活用されてきた。プラスチックは合成化合物なので、紙などと違って地球に戻ることはない。いくら細分化したところで、土には還らないのだ。ここが大きな弊害となっている。その上、ゴミとして燃やすと有害物質が発生する。捨てることも燃やすこともできない、困ったゴミなのである。
マイクロプラスチックとは
プラスチックゴミは、廃棄されると衝撃や紫外線など、多くの外的影響を受けながら、だんだんと小さくなっていく。このようなものをマイクロプラスチックと呼ぶ。また、洗顔料のスクラブなどに使われている小さなプラスチックの粒のことも、同じように呼ぶ。この小さなプラスチックもまた、環境汚染の大きな原因となっている。例えば、水中で自然に還ることなく漂うマイクロプラスチックを食べた魚を、人間が捕獲する。その魚を食べることは、人間がマイクロプラスチックを食べることになるのだ。すでにマイクロプラスチックは、食物連鎖の一部になっているとも言える。
3. 紙ストローと環境

ストローに限らず、レジ袋や使い捨て容器など、プラスチックは生活に欠かせない存在になっている。ただ、今までのように使い続ければ、廃棄される量も増え続ける一方である。プラスチックは地球に還ることはないので、ゴミとして捨てられるほかない。それが人体だけでなく、生態系全体にどのような影響を与えるかを考えたとき、多くの人がこのままではいけない、と思うことだろう。だからこそ、脱プラスチックのムーブメントがここまで浸透したのだ。紙ストローへの転換は、そのひとつのきっかけに過ぎない。
企業姿勢の表れ
脱プラスチックのきっかけとなる紙ストローへの転換は、環境保全を考える上で、かなり重要なセンテンスになっている。それと同時に企業にとっては、エコな姿勢をアピールするひとつのツールにもなり得る。世界に名の知れた大企業が行うことで、それに追随する企業が増え、ひとつのムーブメントとなることも予想される。ただ、一時の運動にならないよう、注意深く見守る必要がありそうだ。
結論
我々が当たり前のように使ってきたプラスチックストローも、環境汚染のひとつになり得る。そのストローを紙に変えることで、守れる環境がある。この事実を知っていると知らないとでは、今後の生活にも違いがでてくるのではないか。環境保全は誰かが行うことではなく、すべての人が考える必要があることも併せて、もう一度考えていきたい。