1. 豚丼の栄養について知ろう
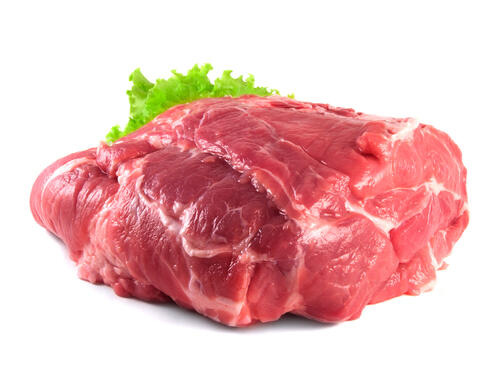
豚丼の栄養については、使用する豚肉の部位や、豚肉以外に加える具材によって多少異なってくるが、炭水化物、脂質、タンパク質の三大栄養素は、豚丼だけで十分に補うことができる。
特筆すべきは、豚丼には、他のどんぶりものと比べると、ビタミン
B1が豊富に含まれているということだ。これは豚丼の主役である豚肉のビタミンB1の含有量が、食品中トップクラスを誇るほど豊富なためだ。ちなみにその含有量は、牛肉や鶏肉のおよそ7~10倍近くもある。
ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換する際に必要なビタミンで、不足すると糖質がうまくエネルギーに変換されず、疲労の元となってしまう。また、ビタミンB1は水溶性ビタミンであり、暑い季節には汗とともに失われやすいので、スポーツをする人や夏場は特に意識して摂るようにするといいだろう。
豚丼の具材としておなじみの、玉ねぎや長ねぎに含まれるアリシンは、ビタミンB1の吸収率をアップさせ、糖質をより効率的にエネルギーに変換するために、とても役立っている成分だ。
特筆すべきは、豚丼には、他のどんぶりものと比べると、ビタミン
B1が豊富に含まれているということだ。これは豚丼の主役である豚肉のビタミンB1の含有量が、食品中トップクラスを誇るほど豊富なためだ。ちなみにその含有量は、牛肉や鶏肉のおよそ7~10倍近くもある。
ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換する際に必要なビタミンで、不足すると糖質がうまくエネルギーに変換されず、疲労の元となってしまう。また、ビタミンB1は水溶性ビタミンであり、暑い季節には汗とともに失われやすいので、スポーツをする人や夏場は特に意識して摂るようにするといいだろう。
豚丼の具材としておなじみの、玉ねぎや長ねぎに含まれるアリシンは、ビタミンB1の吸収率をアップさせ、糖質をより効率的にエネルギーに変換するために、とても役立っている成分だ。
2. 豚丼の献立に加えたい食材とは?

豚丼の主役の豚肉には、良質のタンパク質、ビタミンB1のほかにも、各種ビタミン、ミネラルが比較的バランスよく含まれてはいるが、食物繊維が不足している。一般的な豚丼に使用される豚肉以外の具材は、玉ねぎや長ねぎくらいなので、どうしても食物繊維が不足しやすくなるようだ。そのため、豚丼の献立には、食物繊維が豊富に含まれる食材を加えると、栄養バランスをととのえることができる。
食物繊維には、不溶性と水溶性の2タイプがあるが、どちらもバランスよく摂取することが望ましい。不溶性食物繊維は、野菜全般、特に葉物野菜、根菜類、イモ類、きのこ類、豆類などに豊富だ。水溶性食物繊維は、海藻類、納豆、らっきょう、大麦、豆味噌などに豊富だ。
これらの食材を使って、豚丼との栄養バランスに加え、味のバランスもよい豚丼の献立例をこれからいくつか紹介しよう。
食物繊維には、不溶性と水溶性の2タイプがあるが、どちらもバランスよく摂取することが望ましい。不溶性食物繊維は、野菜全般、特に葉物野菜、根菜類、イモ類、きのこ類、豆類などに豊富だ。水溶性食物繊維は、海藻類、納豆、らっきょう、大麦、豆味噌などに豊富だ。
これらの食材を使って、豚丼との栄養バランスに加え、味のバランスもよい豚丼の献立例をこれからいくつか紹介しよう。
3. 豚丼の理想的な献立例

献立例1 豚丼+ごぼうときのこの味噌汁+海藻サラダ
ごぼうやきのこ類は、不溶性と水溶性の食物繊維のどちらも豊富に含まれている。きのこ類は旨み成分も豊富に含むため、好みのきのこをいくつか選ぶといいだろう。海藻サラダは、海藻類とキャベツあるいは大根の千切りを加えて、好みのドレッシングをかけて、よく混ぜれば出来上がりだ。
献立例2 豚丼+らっきょう漬け+具だくさんの味噌汁
らっきょうには、水溶性の食物繊維が豊富で、アリシンも豊富に含まれているため、豚肉に含まれるビタミンB1の吸収率を高める働きも望める。甘酸っぱい味つけなのでさっぱりしていて、豚丼との味のバランスもよい。味噌汁は、冷蔵庫にある野菜を数種使い具だくさんにすれば、より多くの食物繊維を摂取することができる。
献立例3 豚丼+漬け物+小松菜と豆腐とわかめの味噌汁
漬け物は、たくあん、ぬか漬けなど好みのものでかまわない。小松菜は、不溶性食物繊維のほかに、鉄分やカルシウムも豊富だ。わかめは、水溶性食物繊維や各種ミネラルが豊富だ。
結論
栄養バランスを考慮した豚丼の献立例について、理解することができただろうか。今回こちらで紹介した献立例は、ほんの一例にすぎない。味のバランスなども念頭に入れながら、家にある食材をうまく組み合わせて、家族もよろこぶ豚丼メニューをたててみよう。
この記事もCheck!







