1. ナトリウムの解説と効果
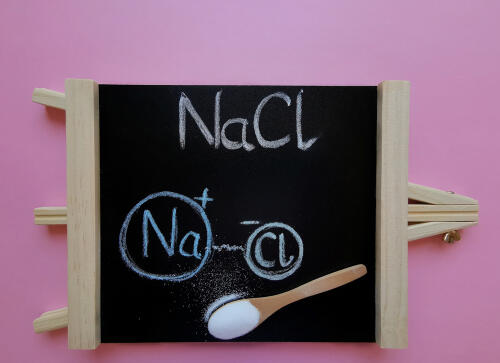
そもそもナトリウムは、私たちの身体にとって必要不可欠な必須ミネラルで、体内で作り出すことができないため、必ず食品などから摂取する必要がある。食品から摂取する場合は、塩化ナトリウムという形で摂取して、体内でナトリウムとして必要な分だけ吸収され、残りは腎臓で濾過されて体内に排出される。
ナトリウムの役割
ナトリウムは、身体の各細胞に存在している体液(血液、リンパ液、消化液など)の浸透圧を調整して、バランスを保つことで、各細胞を正常に機能させるという重要な役目を果たしている。各細胞が正常に機能しているからこそ、私たちは、食べ物からの栄養を十分に吸収し、筋肉や神経を正常に動かすことができ、血圧や脈拍を安定させることができているのだ。すなわち、ナトリウムは、身体の健康を維持するための重要なミネラルということになる。ただし、必要以上に摂取しすぎると、体液のバランスを保つために、血圧が上がったり、身体がむくんだりするなど、人体にさまざまな不都合が生じる。
成人に1日に必要なナトリウム量
ちなみに成人の場合、必要な1日のナトリウム量は食塩換算量で、1.5gと考えられている。これだけあれば、問題なく身体の健康を維持することができるということだが、1.5gというと、大粒の梅干し1個程度あるいは魚肉ソーセージ1本程度食べれば、必要量をすでに満たしてしまうことになる。そのために、ナトリウムは過剰摂取が問題視されやすいのだ。
2. ナトリウムを含む食材や果物・飲み物

ナトリウムを含む食材としては、真っ先に食塩を思い浮かべることだろう。通常、塩分量の多い食品はすべて、ナトリウムも多く含まれることになる。
ナトリウムを含む調味料
とくに味噌や醤油、めんつゆ、市販の出汁の素などの調味料には、多くのナトリウムが含まれている。当然であるが、それらの調味料を使用して作った料理にも、相当量のナトリウムが含まれているということになる。味付けを濃くすればするほど、料理に含まれるナトリウムの量も増えることになる。
ナトリウムを含む食品
食品では、ソーセージ、ハム、ベーコンなどの加工肉、かまぼこ、ちくわなどの練り製品、漬け物、干物、佃煮、たらこや塩鮭、梅干しなどに多く含まれている。
ナトリウムを含む飲み物
飲み物では、昆布茶に多く含まれ、トマトジュース、ココアなどにも比較的多く含まれているようだ。
ナトリウムを含む野菜や果物
ナトリウムは多くの野菜や果物にも含まれているが、その量はごく微量である。野菜や果物には、ナトリウムを排出させる働きのあるカリウムが多く含まれているため、積極的な摂取が推奨されている。
3. ナトリウム不足と感じたら?

ナトリウムは、ありとあらゆる食材に含まれている。ナトリウムをまったく含まない食材を探すことのほうが困難といえるだろう。その量は微量といえど、水や多くの野菜や果物にもナトリウムは含まれている。そのため、通常の食生活を送っていれば、ナトリウムが不足することは、まずないと考えられている。
ナトリウムが不足しやすい時
しかし、たとえば、大量に汗をかいた場合や大量の水を飲んだ場合、過度な減塩を続けた場合などに、ナトリウムが不足することも十分に起こり得る。ナトリウムが不足すると、血圧低下、循環不全、脱水、立ちくらみ、むくみ、肌荒れなど全身に不快な症状が生じやすいといわれている。もしそのような症状が生じた場合、ナトリウム不足が考えられるだろう。もちろん、適切に水分と塩分を摂ることで改善されることもあるが、症状によっては、素人判断が危険なこともあるので、医療機関を受診して医師の指示に従うことが賢明といえるだろう。
結論
ナトリウムの重要性について理解していただけただろうか。摂りすぎても少なすぎても身体にとってさまざまな不都合が生じる。そのため、食事のバランスには意識をくばり、適切なナトリウムの摂取を心掛けてほしい。
この記事もCheck!







