1. リンとは?
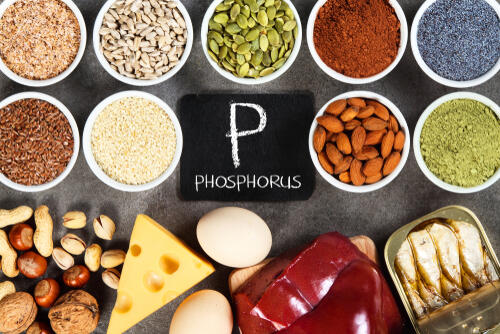
リンはほかのミネラル成分と結びつき、リン酸カルシウムやリン酸マグネシウムとなって体内に存在している。体内に含まれるリンの量は最大で800g。そのうちの約8割が骨や歯の構成成分だ。残りは筋肉や細胞膜に含まれ、1%とわずかな量だけが細胞外液に含まれている。 リンの主な働きは次のとおりだ。
- 骨や歯を構成する
- リン脂質として細胞膜を構成する
- DNAやRNAを構成する
- ATPを構成する
- 浸透圧の調節
- 心臓や腎臓機能の維持
- 神経伝達
リンは生体内の重要な成分の構成要素となり、さまざまな代謝反応に関わる。また、「ハイドロキシアパタイト」としてカルシウムとともに骨や歯を構成するので、とくに成長期の子どもにとっては欠かせない栄養素といえるだろう。
リンの吸収
リンの吸収は回腸や十二指腸、大腸などで行われ、吸収率は60〜70%とされている。リンはカルシウムやマグネシウムなどによって吸収が阻害され、ビタミンDによって促進される。どの栄養素と一緒に摂取するのかが大切なポイントとなる。 なお、体内のリン酸濃度は、腎臓での再吸収や骨からの溶出によって一定に保たれている。恒常性が維持されていることからも、摂取すればするほど吸収されるというわけではない。
リンの摂取量
リンの摂取目安量は、成人男性で1000mg、女性は800mgである。成人男性の平均摂取量は1,064mg、女性が939mgでどちらも満たされている。
2. リンを含む食べ物や飲み物

リンはさまざまな食品に含まれている。小魚や豆類、米ぬか、卵黄、乳製品など動物性、植物性を問わない。 リンは加工食品にも多く含まれている。食品添加物としてリン酸塩が使われているため、加工食品の摂取が増えた現代ではリンは不足よりも過剰摂取のほうが問題となりやすい。
リンの過剰症
リンを長期的に過剰摂取することで、腎機能の低下や副甲状腺機能の亢進、カルシウムの吸収阻害などが起こることがある。カルシウムとリンの比率は1:1〜2とされているが、現代の日本ではリンの過剰摂取により1:3になることが多いと考えられている。
リンをとりすぎるとカルシウムとのバランスが悪くなり、骨や歯が弱くなってしまうことがある。骨量や骨密度の低下を防ぐためには、リンをとりすぎず、カルシウムをしっかりと摂取することが大切である。加工食品の摂取量を減らし、リンの摂取を抑えるようにしよう。
リンをとりすぎるとカルシウムとのバランスが悪くなり、骨や歯が弱くなってしまうことがある。骨量や骨密度の低下を防ぐためには、リンをとりすぎず、カルシウムをしっかりと摂取することが大切である。加工食品の摂取量を減らし、リンの摂取を抑えるようにしよう。
3. リン不足と感じたら?

リンは過剰摂取が問題となりやすい栄養素だが、なかには不足症状が見られる場合もある。低リン血症の原因としては、アルコール依存症、飢餓、利尿薬の使用などがある。低リン血症は症状を伴わないことが多いが、重度に慢性化した状態になると次のような症状が現れる。
- 食欲不振
- 骨軟化
- 筋力低下
- 進行性脳症
- けいれん
- 昏睡、死亡
リンの不足を防ぐために
リンはさまざまな食品に含まれているため、普通の食生活をしていれば極端に不足することは少ない。なんらかの基礎疾患を持っている場合は、治療と並行して経口でリン酸ナトリウムやリン酸カルシウムを摂取することで低リン血症の治療となる。
結論
リンはカルシウムとともに骨や歯を構成する主要なミネラルである。リンは不足よりも過剰摂取のほうが問題視されている。加工食品のとりすぎには十分注意しよう。また、基礎疾患の有無や吸収能によっては、低リン血症を起こす恐れがある。初期は症状が現れにくいので、体調の変化には十分に注意しておこう。
この記事もCheck!







