1. 骨なし魚が人気の理由!どんな過程で骨なしになるのか?

骨なし魚のブームのきっかけは1980年代後半で、病院食に採用されるようになってからのことだ。
骨なし魚が普及した理由
病院では厳密な栄養管理が必要で、魚はたんぱく質源として重宝されるが、高齢者は骨が原因で誤嚥(ごえん)などのリスクが高まる。安全性の面で需要が広がったというのが骨なし魚の人気の理由のひとつだ。また、魚の種類も豊富。たらなどの白身魚や鮭、赤魚、サバなどさまざまな種類を楽しめる。冷凍しておけば日持ちがしやすいというのもメリットである。骨なし魚は、安全性・衛生面・効率的という点で条件が整い、大量給食施設に受け入れられていった。近年では活用の幅が広がり、ホテルや飲食店、学校給食、弁当などさまざまな場面で用いられている。
骨なし魚の製造工程
骨なし魚は、皮についた鱗や骨を手作業でひとつずつ取り除いて作られている。国内での作業よりも、タイやベトナム、中国などの外国で加工されることが多い。海外工場はHACCPまたはISO取得済みの施設であり、品質管理をしっかりと行っている。骨を取る工程によって魚の品質が懸念されるが、温度管理や水の取り扱いなどには十分な配慮がされているようだ。
2. 骨なし魚の気になる製造過程
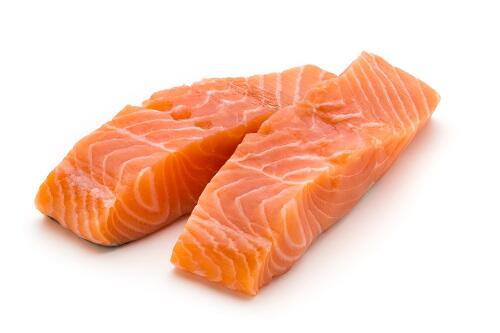
骨なし魚は骨がないので食べやすく、骨が喉に刺さるリスクもないので安心だ。しかし、意外と知られていない製造時の気になる点について紹介したい。
崩れた身には認可済の食品添加物で結着されている
魚の骨を抜くと身が崩れてしまう箇所がある。このような部分には結着剤といって、身を結合するための酵素製剤が使われている。酵素は「トランスグルタミナーゼ」というもので、厚生労働省認可の食品添加物だ。また、商品によっては、酵素製剤のなかに乳たんぱく質や魚ゼラチンを使っているものもある。骨なし魚には添加物が使われている場合もあるので、100%天然の魚とは異なる。
骨の有無はX線でチェックされている
骨なしの魚は完璧に骨が抜けているのだろうか。骨がすべて抜けているのかをどのように確認するのかは気になるところだ。目で見たり手で触ったりして確認できる小骨は「ピンボーン」と呼ばれる。このピンボーンはピンセットのようなもので1本ずつ丁寧に抜かれているが、人間の目や手では限界がある。そこで、作業の最終確認はX線が活用され行われている。X線とは人間の骨のレントゲン検査のようなもの。小さい骨まですべて抜けているかを確認できる。その後切り身にされ、袋詰めされてから再び金属探知機で異物が混入していないかが検査されているのだ。
3. 骨なし魚はどんな料理に使える?レシピを紹介

骨なしの魚は業務用スーパーなどで購入することもできるようになっている。どのように活用できるのか、ここではおすすめのレシピを紹介したい。
南蛮漬け
南蛮漬けは魚に片栗粉をつけて揚げ、野菜と一緒に甘酢に漬けた冷菜である。骨があると食べにくい料理なので、骨なし魚が重宝する。南蛮漬けは青魚が合うので、サンマやサバ、アジなどがよいのではないだろうか。
白身魚のフリッター
骨なしの魚を一口サイズにカットし、卵白を泡立てて小麦粉と混ぜた衣にくぐらせ、油で揚げたもの。小さめにカットすると子どもも美味しく食べられる。ポテトと合わせてフィッシュ&チップスもおすすめだ。
魚ハンバーグ
身を崩して豆腐やパン粉などのつなぎと合わせ、小判型に成形して焼いたもの。魚は肉よりも脂質が少なくヘルシーだ。体重が気になる時でもハンバーグが食べたいときや、魚が苦手な子どもに食べさせたいときにはよいメニューである。
結論
骨なし魚の特徴やメリットについて紹介した。骨なし魚は、骨の誤飲を防止できる安全性から病院や高齢者施設などで需要が高まっている。また家庭における魚の調理においても、骨を抜く手間が省けるため、ファストフィッシュは重宝するだろう。スーパーでも販売されているため、気になる人は一度チェックしてみてほしい。
この記事もCheck!







