1. 夏目漱石とは
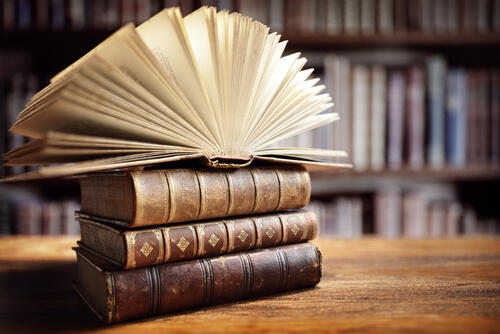
夏目漱石は東京都新宿区生まれ。名家の5男として誕生するが、時は江戸時代末期。幕府が潰れたことで、夏目家も没落しつつあり、5男であるがゆえに、夏目漱石は生後数ヶ月で里子に出される。その後、父の友人宅に養子に出されるなど数奇な運命を辿ることとなる。9歳で生まれた家に戻るもののさまざまな因縁があり、夏目の姓を名乗ることができたのは20歳を過ぎてからだったと言われている。
堪能な英語
安定した幼少期とは程遠い暮らしをしていたこともあり、学校も入退学を繰り返していたが、高校時代に正岡子規に出会い、人生が一変する。勉学にも励み、ほぼすべての教科を首席で卒業。とくに英語は優れていたようで東京帝国大学を卒業後、英語教師としての人生を歩み始める。
我々がよく知る名作を生み出したのは、30代後半になってから。胃潰瘍を患っており、結果的には49歳で亡くなってしまう。
我々がよく知る名作を生み出したのは、30代後半になってから。胃潰瘍を患っており、結果的には49歳で亡くなってしまう。
数ある名作
『我輩は猫である』を執筆、発表したのが、夏目漱石38歳、1905年。翌年には『坊ちゃん』『枕草』を発表。1907年には教師を辞して、朝日新聞社に入社し、執筆に専念するようになる。『それから』『三四郎』など、日本文学史に名を残す数々の傑作を世に送り出すこととなる。
2. 夏目漱石は大の甘党

夏目漱石の傑作には、要所要所に甘いものが登場することからも自身が甘党だったことが伺える。漱石は下戸で知られ、お酒はほんのひとくちしか嗜まなかったらしい。朝ごはんのトーストにはバターと砂糖をたっぷり。シュークリームやアイスクリームなど、洋風菓子にも目がなかったようだ。紅茶にも砂糖をたっぷり入れていたらしい。
イギリス生活と洋菓子
夏目漱石が洋菓子を食べるきっかけとなったのが、文部省の計らいで始まったイギリス留学。現地でパンやジャムを口にすることも多く、紅茶文化もこの期間に習得したと考えられる。
3. 夏目漱石の実在する好物

空也の『空也もち』
『吾輩は猫である』に登場するのが、銀座にある老舗和菓子店空也の空也もち。こちらは11月と1〜2月にしか販売されない幻の和菓子とも呼ばれる存在。非常にシンプルに作られているもので、今も昔ながらの製法を守り、手作業で作っているので1 日に200個ほどしか作ることができないという。普段から買うことのできる空也もなかも実際には、予約だけで売り切れになることもしばしば。空也の焼印とミニマルなサイジング、包装も印象的。一度は食べてみたい銘菓である。
羽二重団子の『羽二重団子』
日暮里にある羽二重団子の『羽二重団子』も『吾輩は猫である』に登場する。初代が「藤の木茶屋」という茶屋をオープンしていたが、のちに団子専門店となる。創業は文政2年なので、その歴史は非常に古い。団子はむっちりとしていて、なめらかな口当たり。醤油と餡子の2種から選ぶことができる。醤油はこんがりと焼き上げた香ばしい味わいがなんともたまらない。今も茶屋時代と変わらず、日本酒を頼むこともできる。
藤むらの『羊羹』
『草枕』に登場する羊羹の描写は、本郷の藤むらのモノを指していると言われることが多い。もともと文豪から愛される和菓子店で、森鴎外の『雁』にも田舎まんじゅうが登場する。こちらも創業は古く、江戸城への献上品にも名を連ねていたと言われているほどだ。しかし、10年ほど前にシャッターを閉めたきりで、今は食べることができない。
結論
夏目漱石は、妻に隠れて食べるほどに甘いものが好きだったと言われている。持病の胃潰瘍にはあまり甘いものはよくないとわかっていてもやめられなかったのだろう。今でも食べることができる銘菓も多いので、ぜひ名著を読みながら味わってみてはいかがだろう。
この記事もCheck!







