1. 【あいこまち】の魅力とは?
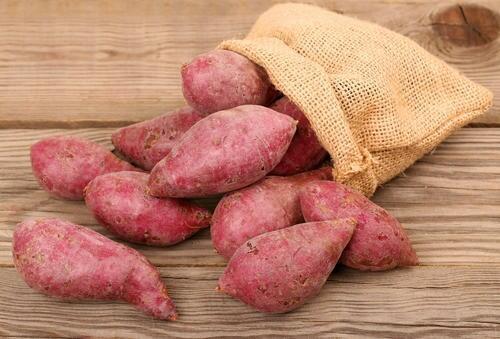
研究の末に生まれたさつまいも
新しい品種が生まれるパターンは2つある。1つは、遺伝子の突然変異や自然交雑によって生まれた品種を人が発見し、栽培に成功したパターン。もう1つは、優れた品種を人工的に交雑させ、より優れた品種を生み出すパターンだ。「あいこまち」は後者のパターンによって生まれた。そのため、数あるさつまいもの中でも新しい品種だといえる。
あいこまちの特徴
あいこまちは、「紅あずま」が抱えていた問題を克服した品種だ。紅あずまは、しっとりとした食感と甘さが人気のさつまいもで、広い地域で栽培されている。しかし、育ちすぎによって外観が悪くなる、糖度が安定しない、病害虫への抵抗性が弱い、といった問題があった。また、調理後に黒っぽくなることから、色鮮やかな菓子類に使うことも難しいとされていた。そのため、これらの問題を克服したあいこまちは、より安定したさつまいもの生産を可能にしたといえる。紅あずまと同様の食感、味を保ちながら、サイズの均一化、糖度の安定化、病害虫への抵抗性亢進、さらには調理後の変色も防げるようになったということが、あいこまちの特徴である。また、調理後の変色がないことから、紅あずまでは作れなかった菓子類も作れることも、あいこまちならではのメリットだ。
2. あいこまちの旬と選び方

あいこまちの旬
品種改良によって生まれたあいこまちだが、ほかのさつまいもと同様、秋に旬を迎える。ここでいう旬とは、収穫の最盛期のことを指す。あいこまちは9~11月にもっとも収穫されるため、必然的にこの時期に流通量は増える。しかし、12月以降も市場に出回るので、購入することは可能だ。さつまいもは貯蔵性が高く、収穫直後のさつまいもを一度に出荷する必要がないからだ。あいこまちも同様で、旬を過ぎても貯蔵されていた分が出回るため、通年手に入れることができる。
あいこまちを選ぶときのポイント
紅あずまに比べ、均一に育ちやすいことが特徴のあいこまち。そのため、サイズのばらつきは少ないといえる。しかし、あいこまちを選ぶときには、サイズ以外にも見ておかなければいけない部分がある。まず、あいこまちの形だ。表面にでこぼこがなく、かつふっくらとしているかどうかをチェックする。次に皮の状態だ。皮の色つやがよいか、黒い斑点が出ていないか、じっくり観察しよう。さらに切り口も見ておくと、なおよい。切り口周辺に、蜜が流れ出た跡である黒い跡があれば、蜜がたっぷり入った甘いあいこまちだと判別できる。形、皮の状態、切り口の3点をチェックしておけば、美味しいあいこまちがゲットできるだろう。
3. あいこまちのおすすめの食べ方

あいこまちのしっとりした食感と甘さは、焼きいも、干しいも、そのほかあらゆる料理で美味しくたべることができる。そのため、たくさん買ったらさまざまな食べ方を試してみるとよい。食べ方を迷っているならば、まずはスイートポテトなど、さつまいもを使ったお菓子にして食べるのがおすすめだ。色鮮やかな黄色が食欲をそそる。
スイートポテトの作り方
あいこまちの皮をむき、やわらかくなるまで茹でる。つぶせる硬さになったら、熱いうちに裏ごしをして、なめらかな状態にする。そこにバター、砂糖、牛乳、卵黄を加え混ぜる。均一に混ざったら、成型して表面にツヤ出しの卵黄を塗る。オーブンで焼けば、スイートポテトの完成だ。
大学いもの作り方
まず、乱切りまたはスティック状に切ったあいこまちを油で揚げる。その際、油はねが起きないよう、あいこまちの水気はしっかりふき取っておくことが重要だ。竹串が通るくらいに火が通ったら、砂糖と水を煮詰めて作った蜜にくぐらせる。仕上げにごまをかければ、あいこまちの大学いもの完成だ。
結論
紅あずまと同じ食感、甘みをもちながら、紅あずまが抱えていた問題を克服した、あいこまち。育てやすくなったのはもちろん、調理後の色味も鮮やかであり続けるため、さまざまな料理への応用が期待できる。あいこまちの鮮やかな黄色を活かして、秋の訪れを感じさせる食卓を作ってみるのも、四季の味わい方としておすすめだ。
この記事もCheck!







