目次
- ※1.文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)果実類/(かんきつ類)/はっさく/砂じょう/生」 https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=7_07105_7
- ※2※3.平凡社世界大百科事典「ビタミン」 https://kotobank.jp/dictionary/sekaidaihyakka/
- ※5.集英社情報・知識imidas「フラボノイド」 https://imidas.jp/
- ※6.公益社団法人日本生物工学会「青い柑橘類果実でアンチエイジング」 https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/8806_daigakuhatsu.pdf
- ※7.集英社情報・知識imidas「ヘスペリジン」
1. はっさくとはどんな果物?
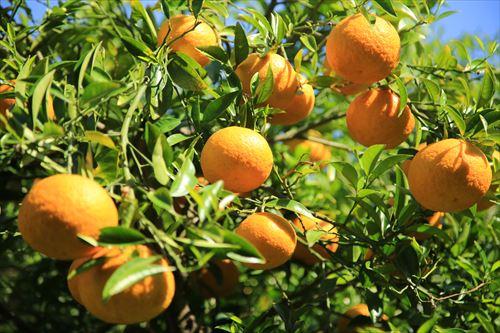
まずは、はっさくの起源や名前の由来について紹介する。普段はあまり思いを馳せることもないはっさくの特徴もふくめて、その概要を見てみよう。
発見された背景と特徴
はっさくは、広島県因島にある恵日山浄土寺の敷地内において見出された偶然実生である。1860年に発見されたはっさく、旧暦8月の朔日(1日)には口にできるという意味から八朔の名がついたとされているが、実際には旧暦の8月1日では、まだ実が熟していない。明治時代の終わりごろから栽培が普及し始め、温州みかん、デコポン、イヨカン、夏みかんに次ぐ生産量を誇っている。やや固めの砂瓤 、独特の芳香、やや苦味を含んだ品のよい味わいが愛され続けている。生食で食べられることが多い。
2. はっさくが食べごろの時期

冬の風物詩というイメージがあるはっさく、その旬はいつだろうか。はっさくが美味しく食べられる時期を見てみよう。
旬の時期
はっさくは寒さに強く栽培が難しくないとされている。現在ははっさくが生まれた広島県をはじめ、和歌山県、愛媛県、徳島県が主要産地となっている。はっさくの旬は2月から4月とされているが、収穫は12月ごろから始まる。1か月ほど貯蔵し酸味を抜いてから出荷されることが多いが、完熟させて収穫するタイプは3月中旬が旬となる。その名の由来となった旧暦の8月1日は秋にあたり、はっさくは未熟であるため食べることは難しい。
3. はっさくの栄養成分

生食でも美味しく食べることができるはっさく。寒い時期の栄養補給にぜひ活用したい。はっさくにはどんな栄養が含まれ、どんな効能が期待できるのか。はっさくの栄養について説明する。
栄養素と効能
文部科学省の食品成分データベースを参照にして(※1)、はっさくに含まれる主な栄養素とその効能を紹介する。数値は生食のはっさく100g中の含有量である。
・ビタミンC
柑橘類の例にもれず、はっさく100g中には40mgのビタミンCが含まれている。(※1)美容や健康を語る場合に必ず名があがるビタミンCは、コラーゲンの合成に深く関与する栄養素である。また免疫作用を増強し、白血球の作用を強化することも報告されている。(※2)
・葉酸
水溶性ビタミンの1種である葉酸。はっさく100g中には、16μgの葉酸が含まれている。(※1)葉酸は動物の細胞内では合成不可能の栄養素である。葉酸はアミノ酸の代謝やタンパク質の合成に不可欠の要素であり、赤血球の補給のために妊婦はとくに摂取が必要とされている。(※3)
・ナリンギン
はっさくの特徴のひとつであるほのかな苦味は、ナリンギンという要素によるものである。ナリンギンはミカン科の果物に含まれるフラボノイドである。フラボノイドとはベンゼン環にグルコースが結合した高分子化合物であり、血圧を下げる効能が期待できる。(※5)ナリンギンははっさくの果皮にも多いため、無農薬のタイプを選んで砂糖漬けなどにするとよいかもしれない。
・ヘスペリジン
はっさくの果皮にはヘスペリジンと呼ばれるポリフェノールが含まれている。(※6)ヘスペリジンは未熟な果皮により多く含まれる栄養素である。(※7)ヘスペリジンは肝臓における中性脂肪の合成を抑止し、血中の中性脂肪を低下させるといわれている。
4. はっさくの美味しい食べ方

日本の冬の風景に根づいているはっさく。生食でじゅうぶん美味しく食べることができる果物であるが、厚い皮はどのように処理すべきだろうか。また、はっさくを大量に入手した場合、美味しく消費しきるにはどんな方法があるのか。はっさくの美味しい食べ方を見てみよう。
切り方
生食で食べることが多いはっさくであるが、厚い皮は手ではむきにくいのが難点である。はっさくをむく場合には、放射線状に縦の切り込みをいくつか入れるとむきやすくなる。その場合に、上下の中央部分を円状に切り取っておくとさらに処理が楽になる。
加工して食べる
はっさくが大量にある場合、加工してさまざまな方法で楽しみたい。ジューサーでドリンクにすれば一気に消費できるほか、果皮の栄養分も摂取したい場合には、ピールも含めたジャムにするとよいだろう。ゼリーや砂糖漬けにすればおやつの一品にもなる。はっさくを使ったタルトやチーズケーキなどの洋菓子はもちろん、餅を使ってはっさく大福にしても新鮮である。
結論
はっさくは、江戸時代に広島県の因島で発見された柑橘類を祖としている。旧暦の8月1日にちなんだ名前がついているが、旬は2月から4月である。独特の香りや食感は日本人に愛されて、生産量は多い。ビタミンCをはじめフラボノイドやポリフェノールも豊富であり、加工して果皮も摂取することをおすすめする。生食だけではなく、スイーツとしても大いに堪能してほしい。
(参考文献)







