目次
- ※1 厚生労働省 農林水産省 食品期限表示の設定のためのガイドライン https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/expiration_date/pdf/syokuhin23.pdf
- ※2 消費科学研究所 食品の消費期限・賞味期限設定のための検査(保存検査)のご案内 - 品質管理・衛生管理の消費科学研究所/大阪・東京・名古屋 https://www.shoukaken.co.jp/news/1635/
- ※3 農林水産省 消費期限と賞味期限:農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html
1. 消費期限とはどんな意味?

食べ物や飲み物を購入すると、パッケージに消費期限が記載されていることがある。この消費期限とはどのような意味があるのだろうか?消費期限の定義を詳しくチェックしてみよう。
食品を安全に食べられる期限のこと
消費期限は、年月日で記載されていることが多い。消費期限の定義は、その食品が安全に食べられる期限のことをいう。(※3)消費期限は、食品が入っている容器や袋などのパッケージに表示されている。食品を購入した際は、消費期限をチェックしてもらいたい。
品質劣化が早い食品に記載される
加工食品には、必ず消費期限か賞味期限のどちらかを表示することが決められている。とくに品質劣化が早い食品には、消費期限が表示されている。品質の劣化が早い食品として弁当やケーキ、生肉などが挙げられる。そのような食品の場合は消費期限をチェックして期限内に食べきるようにしよう。
消費期限切れの食品は食べない方が良い
消費期限が記載されている食品は、劣化が早いものが多い。つまり1日でも消費期限切れの食品は、食品の安全が保障されていないので、いつまでも食べない方がいいだろう。消費期限切れの食品を食べてしまうと、思わぬ体調不良などを起こすことがある。
保存条件によっても安全性は変わる
食品の安全性は、保存条件によっても異なる。管理状況や保存環境によって食品の状態は大きく変わってしまうので、保存状態が悪いものは食べないようにしよう。また、一度開封した食品は、劣化が早まってしまうのでできるだけ早く食べきるようにしたい。食品を保存する場合は、それぞれの食品に合った正しい方法で保存しよう。
2. 消費期限の設定方法とは
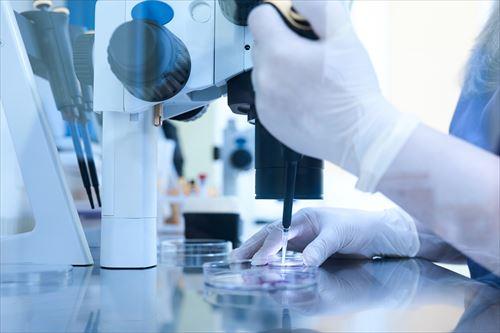
消費期限の設定方法は、国のガイドラインに沿って定められている。どのように消費期限が決められるのか見てみよう。
国のガイドラインに沿って設定されている
消費期限は国のガイドラインに沿って設定されている。(※1)消費期限を記載する食品の検査を行い、菌の繁殖状況や微生物試験などを実施し、さまざまな変化を数字化させる。それを元に安全係数をかけて日付を設定するのだ。国のガイドラインでは、表示する期限は、各種試験や検査の結果から客観的な指標に基づいて設定することが示されている。(※2)
賞味期限は実際の安全期限より短い
賞味期限を設定する際に使われる安全係数は、1未満の数字が使われるので、実際の安全期限よりも短い賞味期限が設定される。(※2)賞味期限は実際の安全期限より短い年月日が記載されているが、それは食品の安全を考慮してのことなので、その期限を守るようにすることで、食の安全と美味しさを確保することができるだろう。
3. 消費期限と賞味期限の違いとは

賞味期限は、消費期限とは違い、品質が変わらず美味しく食べられる期限のことをいう。消費期限と比べると、傷みにくい食品に関しては長期間の賞味期限が表示されている。賞味期限は食品の品質に対する期限なので、切れても食べることは可能だ。しかし消費期限も賞味期限も開封してしまうと食品の安全性や美味しさが劣化しはじめてしまうので、できるだけ早めに食べきるようにしたい。(※3)
結論
消費期限は、劣化の早い食品に記載されており食品を安全に食べられる期限なので、守るようにしたい。一方、賞味期限は美味しく食べられる期限のことをいうので多少過ぎても食べることが可能だ。しかし消費期限も賞味期限も保存状況によって食品の安全性が変わってきてしまうので、正しい保存方法を行い期限を守るようにしたい。食品を購入したら、消費期限や賞味期限をチェックしてできるだけ期限内に食べきるようにしよう。
(参考文献)







