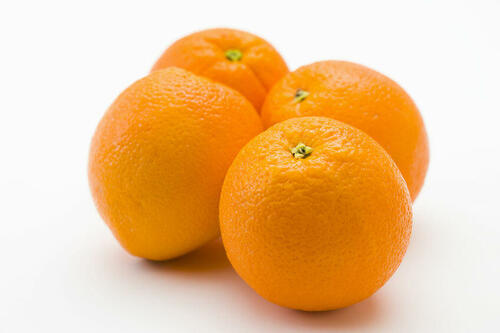1. ハレヒメの特徴

ハレヒメは、見た目からしてみかんとオレンジの中間といった感じだ。扁球形の果実に橙色の表皮、1玉あたり150~200gほどの重さである。ただ、どれも同じというわけではなくバラツキが見られ、ハレヒメの中でもよりみかんに近いものもあれば逆にオレンジに近いものもあり、それがまた面白い。果肉はどちらかといえばみかんに近いが、オレンジのような香りがあり果汁も多い。甘みは強くなくさっぱりとした印象だが、酸味が少ないため食べやすい。
さらにハレヒメはオレンジっぽい見た目から皮が硬そうに見えるが、意外にも手で簡単にむくことができる。さらに袋(じょうのう膜)も薄くはないが柔らかいため、みかんのようにまるごと食べられるのが魅力だ。美味しさだけでなく食べやすさも兼ね備えている品種なのである。
2. ハレヒメの誕生と由来

ハレヒメは「清見タンゴール」「オセオラオレンジ」の交配種を母親とし、父親は温州みかんである「宮川早生」。これらを交配し育成した交雑種だ。ちなみにオセオラはアメリカで生まれたマンダリンとタンゼロの交配種である。ハレヒメの誕生は平成に入ってからで、静岡県静岡市の果樹研究所・興津支場で育成された。命名登録は2001年、品種登録は2004年という比較的新しい柑橘である。
ハレヒメは漢字で記載すると「晴姫」。ネーミングの由来は、「夏と秋に晴天が続くと甘く香り高い果実になる」ということからこのように名付けられた。ちなみに生まれは静岡県だが、現在の主な生産地は愛媛県で全国出荷の約8割を占める。愛媛ではハレヒメの中でも一定の食味基準をクリアしているもののみ、「瀬戸の晴れ姫」というブランド名が付けられている。
3. ハレヒメの旬と入手方法

ハレヒメの旬は12~1月にピークを迎える。露地栽培のものは12月上~中旬にかけ完全着色するため、12月下旬には収穫がほぼ完了する。出回る時期も食べごろの旬も、11月下旬~1月中旬ごろまでだ。
愛媛県での生産が圧倒的に多いが、広島県愛知県などでも栽培・出荷されている。旬になれば生産地を中心に多く出回るため、付近のスーパーや青果店、直売所でも購入できるだろう。ただし生産地が集中しているため、東日本などではあまり見かけない品種でもある。確実に入手するには、通信販売での取り寄せを利用することをおすすめする。
4. ハレヒメの美味しい食べ方

ハレヒメを選ぶ際には、外皮の色が鮮やかで張りがあるか、重みがしっかりと感じられるかという点をチェックしよう。ヘタが枯れていないことも鮮度を見るポイントだ。保存は風通しのよい冷暗所で1週間。箱買いの場合は傷んでいるものがないかチェックし、湿気がこもらないようふたを開けておこう。なるべく早く食べきってしまったほうが美味しく鮮度のよい状態を楽しめる。
ハレヒメの果皮はやや厚めに感じるが、みかんのように手でむけるためナイフは必要ない。一房ずつはがして袋ごといただこう。ちなみに種は基本的にはないが、入っている場合もある。生の果実をそのまま食べるのが一番美味しいが、大量買いした場合などは、ジュースやゼリーにするのもおすすめだ。また、皮もマーマレードに加工して食べられる。
結論
みかんとオレンジのよさを一度に味わえるハレヒメ。一度食べたらやみつきになる人も多いのではないだろうか。味ももちろんだが、オレンジの香りとみかんの食べやすさを兼ね備えているのが魅力だろう。いつもとは違ったみかんを食べたいと思ったら、ぜひハレヒメを試してみてほしい。
この記事もCheck!