目次
- 1. ひき肉の消費期限:冷蔵庫の場合
- 2. ひき肉の消費期限:チルドの場合
- 3. ひき肉の消費期限:冷凍の場合
- 4. 消費期限切れのひき肉を食べるのは危険!
- 5. 消費期限内でも要注意!ひき肉が食べられるかの見分け方
- 6. 消費期限が短いひき肉の正しい保存方法
1. ひき肉の消費期限:冷蔵庫の場合

美味しい料理の材料として登場率が高いひき肉。まずは、ひき肉を冷蔵保存した場合には、消費期限がどのくらいになるのか見てみよう。ひき肉の消費期限は、肉の種類によっても異なるのだろうか。まずはパッケージに書かれている消費期限の日付を参考にするのが第一だが、ここではそれぞれの消費期限を詳しく紹介する。
豚ひき肉の消費期限
そもそも、消費期限とは「期限を過ぎたら食べないほうがよい」期限を指す。(※1)豚ひき肉を冷蔵で保存した場合、消費期限は最大で3日といわれている。
鶏ひき肉の消費期限
ひき肉のなかでも、鶏肉はとくに消費期限に注意が必要である。ほかの肉よりも水分が多い鶏肉は、消費期限が短い。保っても2日で、できれば購入日に消費するのが望ましい。
牛ひき肉の消費期限
傾向としては、牛肉のひき肉は鶏肉や豚肉よりは日持ちがする。しかし豚肉と同様、冷蔵保存した牛ひき肉は3日が消費期限の限度である。
2. ひき肉の消費期限:チルドの場合

ひき肉の保存温度は、10℃以下がルールである。チルド室に入れた場合、その温度は0℃~1℃と冷蔵室よりも低いため、冷蔵室もより日持ちする傾向がある。
とはいえ、ひき肉は肉類の中ではとくに傷みやすい性質を有している。冷蔵保存よりも1日は消費期限が伸びるという説もあるが、チルド室での保存は鮮度の保持が可能になるだけである。パッケージに明記されている消費期限は守るようにしよう。つまり、チルド室に保管しても、ひき肉の消費期限が伸びることはないということを覚えておくべきである。
3. ひき肉の消費期限:冷凍の場合

購入したひき肉が使い切れない量であれば、即冷凍するとよい。冷凍すれば、消費期限を過ぎても食べることはできる。ただし、冷凍保存中にひき肉が劣化しないというわけではないため、いずれにしても忘れることなく早めに消費するのがお約束である。調理前のひき肉も加熱したものも、2週間をめどに使い切るとよいだろう。
4. 消費期限切れのひき肉を食べるのは危険!

食品衛生法やJAS法によって明記が義務付けられている消費期限。(※1)消費期限を過ぎた食品は、劣化や腐敗によって安全が保障できないという意味である。消費期限を過ぎたひき肉は、安全性を欠くことから廃棄するのが妥当である。
消費期限を1日過ぎただけのひき肉は、外観は期限内のものと変わらないかもしれないが、2日~3日後には明らかに肉の色が変わり、5日後には異臭を放つようになる。消費期限は守ってこそ、安全が保持できることをよく覚えておこう。
5. 消費期限内でも要注意!ひき肉が食べられるかの見分け方
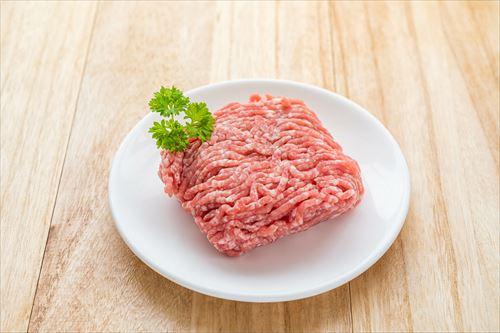
消費期限内でありながら、ひき肉がいつもとは異なる様相を呈している場合はどうしたらよいのか。ひき肉を安全に食べるための注意点をまとめる。
臭いで見分ける
消費期限内のひき肉であっても、パックを開けた途端にアンモニアのような刺激的な臭いを感じる場合、食べるのはNGである。また、酸っぱいような臭いがしているときも腐敗が進んでいる可能性があるため、食べないほうがよい。
見た目で見分ける
ひき肉は時間が経つと茶色っぽくなることがよくある。これは酸化によっておこる現象である。この程度であれば、食べてもほぼ問題はない。一方、ひき肉が黒や緑に変色している場合は完全にアウトである。これは典型的な腐敗の症状であるため、即廃棄してほしい。
6. 消費期限が短いひき肉の正しい保存方法

肉のなかでも消費期限が短いひき肉。ひき肉の質を落とさずに保存するには、どんな工夫が必要なのだろうか。美味しくひき肉を食べるための保存方法を説明する。
冷蔵庫保存の場合
ひき肉を冷蔵で保存する場合、冷蔵庫内でもより温度が低いチルド室やパーシャル室に入れるのがベターである。また酸化防止のために、パックから取り出してラップにくるんでおくのも手である。
冷凍庫保存の場合
ひき肉を冷凍保存する場合は、パックから取り出して小分けにしておこう。酸化を防ぐために、ラップでぴっちりと包んで冷凍する。このときに平たく包んでおけば、冷凍庫内のスペースを有効に使えるだろう。使用時には、冷蔵庫に移したりレンジの解凍モードで半解凍し、そのまま料理に投入する。
この記事もチェック!
結論
日々のおかずを作る場合によく使用するひき肉。ひき肉は、肉類のなかでも消費期限が短いという特徴がある。消費期限は食の安全を守るために定められているため、見た目は変わらなくても1日でも過ぎた場合は食べないようにしよう。消費期限内のひき肉も正しく保存し、食べる際には異常がないか確認することをおすすめする。
(参考文献)
この記事もcheck!







