目次
1. 卵はすごい!アミノ酸スコア100点の栄養豊富な食べ物

人間の身体には、5大栄養素と呼ばれる栄養素が必要である。たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルの5つだ。このうちたんぱく質はアミノ酸によって構成されている。
卵の栄養について優秀な点を挙げる際に欠かせないのが、このアミノ酸の存在。卵は、アミノ酸スコアがすごいのである。
卵の栄養について優秀な点を挙げる際に欠かせないのが、このアミノ酸の存在。卵は、アミノ酸スコアがすごいのである。
アミノ酸スコアとは?
人間の身体は、食事から摂取しなければならないアミノ酸が9つある。この9つのアミノ酸は、必須アミノ酸と呼ばれる。必須アミノ酸の理想的な摂取量に対し、その食品に含まれている必須アミノ酸の割合を示したものが「アミノ酸スコア」だ(※1)。
卵のアミノ酸スコアは100点
9つすべての必須アミノ酸が必要な摂取量を満たしている場合、アミノ酸スコアは100。卵はアミノ酸スコアが100で、栄養豊富な食材なのである。
2. 卵1個あたりに含まれるエネルギー産生栄養素
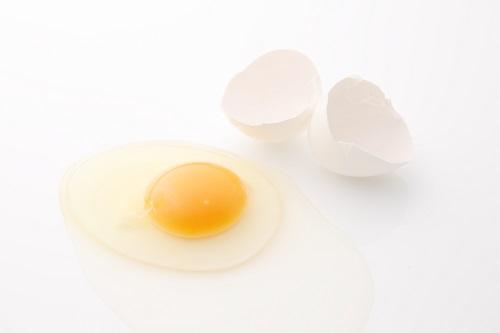
卵の栄養(※2)は、アミノ酸スコアがすごいだけではない。ここでは、たんぱく質や脂質などをとりあげてみてみよう。なお、卵1個=Mサイズ正味50g(殻なし)としている。
カロリー
卵1個のカロリーは71kcal。kcalはエネルギーの単位である。人間のエネルギー源は食事なので、その食材や料理がもつエネルギーがkcalとして表される。
たんぱく質
卵1個のたんぱく質は6.1g。たんぱく質は、筋肉や血液など、身体を作るのに必要な主要栄養素だ。
脂質
卵1個の脂質は5.1g。力や熱といったエネルギー源となる栄養素だ。脂質1gあたり9kcalで、効率よくエネルギーを得ることができる。
炭水化物
卵1個の炭水化物は0.2g。炭水化物は運動時や脳のエネルギー源となる栄養素だ。
3. 卵白に含まれる栄養

卵は、卵白と卵黄で含まれる栄養素が異なっている。ここでは卵白の栄養成分に注目してみたい(※2)。
卵白100gあたりの栄養成分一覧
卵白100gに含まれている栄養成分は、次の通りだ。卵黄と比べると炭水化物やカリウムが多く含まれている。
- たんぱく質:10.1g
- 炭水化物:0.5g
- ナトリウム:180mg
- カリウム:140mg
- カルシウム:5mg
- マグネシウム:10mg
- リン:11mg
- 銅:0.02mg
- ビタミンK:1μg
- ビタミンB2:0.35mg
たんぱく質
卵白100gあたりに含まれるたんぱく質は10.1g。卵黄にも含まれており、100gあたりのたんぱく質量は、卵黄のほうがわずかに多い。
カリウム
卵白100gあたりに含まれるカリウムは140mg。カリウムは細胞の浸透圧の調整や筋肉の収縮にかかわる栄養素だ。ナトリウムを体外に排出して血圧を下げる働きもある(※3)。
4. 卵黄に含まれる栄養

料理に彩りを与えてくれている卵黄は、色だけでなく栄養面でも多くのメリットがある。ここでは卵黄の栄養成分に注目してみたい(※2)。
卵黄100gあたりの栄養成分一覧
卵黄100gに含まれている栄養成分は、次の通りだ。卵白と比べるとビタミンが多く含まれている。
- たんぱく質:16.5g
- 脂質:34.3g
- 炭水化物:0.2g
- ナトリウム:53mg
- カリウム:100mg
- カルシウム:140mg
- マグネシウム:11mg
- リン:540mg
- 鉄:4.8mg
- 亜鉛:3.6mg
- 銅:0.13mg
- ビタミンA(レチノール):690μg
- ビタミンD:12.0μg
- ビタミンE:4.5mg
- ビタミンK:39μg
- ビタミンB1:0.21mg
- ビタミンB2:0.45mg
- ビタミンB6:0.31mg
- ビタミンB12:3.5μg
- 葉酸:150μg
ビタミン
卵黄に多く含まれるビタミンは身体の働きを調整する栄養素で、体内でほとんど合成することができない。エネルギーの代謝を助けるのがビタミンB群で、ビタミンA・Eは抗酸化作用をもつ。ビタミンDは骨の形成を助けてくれる。
卵白に含まれるビタミンA(レチノール)は100gあたり690μgと多く、皮膚や粘膜の健康を維持する。また、ビタミンDも100gあたり12.0μgと多く、カルシウムの吸収サポートや骨の強化に役立つ(※1・3)。
卵白に含まれるビタミンA(レチノール)は100gあたり690μgと多く、皮膚や粘膜の健康を維持する。また、ビタミンDも100gあたり12.0μgと多く、カルシウムの吸収サポートや骨の強化に役立つ(※1・3)。
ミネラル
人間には身体のために必要な必須ミネラルが16種類あり、なかでも不足しがちなミネラルが卵黄にはすべて含まれている。カリウム100mg、カルシウム140mg、鉄4.8mg、亜鉛3.6mg。いずれも卵黄100gあたりの含有量である。
カリウムは血圧を調整する働きがあり、カルシウムは歯や骨の形成にかかわる重要なミネラルだ。不足すると貧血になりやすいと聞くことも多い鉄は、赤血球のなかで酸素を運んでいる。亜鉛は身体の中のさまざまな酵素をつくっている(※3)。
カリウムは血圧を調整する働きがあり、カルシウムは歯や骨の形成にかかわる重要なミネラルだ。不足すると貧血になりやすいと聞くことも多い鉄は、赤血球のなかで酸素を運んでいる。亜鉛は身体の中のさまざまな酵素をつくっている(※3)。
アミノ酸
卵黄は数多くのアミノ酸が含まれており、さまざまな効果が期待できる。卵黄100gあたりに含まれている量と働きは次の通り。今回は、必須アミノ酸9つをまとめた(※5)。
体力アップなどの働きがあるとされているのが、イソロイシン830mg、ロイシン1400mg、バリン950mg。イソロイシンは成長サポートにも役立ち、ヒスチジン430mgも同様の働きがある。リジン1200mgは脂肪燃焼や成長をサポート。メチオニン390mgも同じく脂肪燃焼の働きがある。トリプトファン230mgは脳機能を活性化してくれるほか、リラックス効果も。フェニルアラニン680mgは血圧上昇などに機能する。
5. 全卵に含まれる栄養

卵の調理方法の多くは、卵白と卵黄を合わせた全卵である。ここでは全卵の栄養成分についてみていこう(※2)。
全卵100gあたりの栄養成分一覧
全卵100gに含まれている栄養成分は、次の通りだ。
- たんぱく質:12.2g
- 脂質:10.2g
- 炭水化物:0.4g
- ナトリウム:140mg
- カリウム:130mg
- カルシウム:46mg
- マグネシウム:10mg
- リン:170mg
- 鉄:1.5mg
- 亜鉛:1.1mg
- 銅:0.05mg
- ビタミンA(レチノール):210μg
- ビタミンD:3.8μg
- ビタミンE:1.3mg
- ビタミンK:12μg
- ビタミンB1:0.06mg
- ビタミンB2:0.37mg
- ビタミンB6:0.09mg
- ビタミンB12:1.1μg
- 葉酸:49μg
卵にはビタミンC、食物繊維以外の栄養素が含まれている。卵だけでほとんどの栄養素を網羅しており、栄養豊富な優れた食材であるといえるだろう。
6. 卵の栄養に期待できる効果・効能

栄養豊富な卵。食べることで期待できる効果や効能にはどのようなものがあるだろうか。ここでは主な2つを紹介しよう(※2)。
疲労回復
たんぱく質が豊富な卵は、十分な量を摂ることで疲労回復の効果が期待できる。卵は、日々の身体づくりだけでなく、疲れた身体にも効く栄養食材だ(※1)。
老化防止
卵はビタミンも多く含み、これには抗酸化作用があるため、老化防止にも。脳を活性化するコリンという栄養素も含んでいるため、脳の老化・認知症の防止にも有効であるとされている(※4・6)。
7. 卵の栄養価は食べ方によって変わる?

卵は、調理方法によって栄養価が変わるのだろうか。ここでは、代表的な3つの食べ方による栄養価の違いについてまとめた。
生食の栄養価
卵を生で食べると、卵に含まれる栄養素をまるごと摂ることができる。ビタミンB群など、加熱すると減少してしまう栄養素もある。これらの栄養素を減少させずに摂るためには生食がおすすめだ。
茹で卵の栄養価
茹で卵は、生で食べる卵とほとんど栄養価は変わらないが、ビタミンはわずかに減少する。
卵焼きの栄養価
卵焼きの栄養価は、生食や茹で卵と比べると3つのなかでは最もビタミンが減少する。ほかの栄養価はほとんど変わらない。
8. うずらの卵や烏骨鶏卵の栄養は?

卵と聞くと鶏卵が一般的だが、ここではうずらや烏骨鶏卵の栄養についてみてみよう(※2)。
うずらの卵の栄養成分一覧
うずらの卵100gあたりに含まれる栄養成分は次の通りだ。
- たんぱく質:12.6g
- 脂質:13.1g
- 炭水化物:0.3g
- ナトリウム:130mg
- カリウム:150mg
- カルシウム:60mg
- マグネシウム:11mg
- リン:220mg
- 鉄:3.1mg
- 亜鉛:1.8mg
- 銅:0.11mg
- ビタミンA(レチノール):350μg
- ビタミンD:2.5μg
- ビタミンK:15μg
- ビタミンB1:0.14mg
- ビタミンB2:0.72mg
- ビタミンB6:0.13mg
- ビタミンB12:4.7μg
- 葉酸:91μg
ビタミンB12は鶏卵の約4倍含まれており、貧血予防の効果が期待できる。また、ビタミンAは鶏卵の1.5倍以上の含有量なので、アンチエイジングに有効といわれている(※3・4)。
烏骨鶏卵の栄養成分一覧
烏骨鶏卵100gあたりに含まれる栄養成分は次の通りだ。
- たんぱく質:12.0g
- 脂質:13.0g
- 炭水化物:0.4g
- ナトリウム:140mg
- カリウム:150mg
- カルシウム:53mg
- マグネシウム:11mg
- リン:220mg
- 鉄:2.2mg
- 亜鉛:1.6mg
- 銅:0.08mg
- ビタミンA(レチノール):160μg
- ビタミンD:1.0μg
- ビタミンE:1.3mg
- ビタミンK:4μg
- ビタミンB1:0.10mg
- ビタミンB2:0.32mg
- ビタミンB6:0.10mg
- ビタミンB12:1.1μg
- 葉酸:6μg
鉄の含有量はほうれん草の約9.6倍なので貧血予防におすすめだ。普段の食事ではとりづらい亜鉛は鶏卵よりも多いうえ、大豆の約3.3倍含まれている。亜鉛は、免疫力アップなどの働きをもつ(※3)。
9. 卵は1日何個まで?コレステロールは大丈夫?

卵を食事に取り入れる際、1日何個食べていいのか気になる人も多いはず。栄養豊富な食材だが、食べ過ぎがコレステロールの値の上昇につながることはないのだろうか。
1日1個を目安としよう
卵は1日1個までという明確な基準は存在しない。たしかに卵には栄養素としてコレステロールが含まれているが、体内でも合成されており、摂取量によってその合成量が調節されるのだという。一方で、卵の摂取がコレステロール値の上昇につながった人もいたという研究報告もある。
卵は1日1個を目安に、栄養豊富な食材としてバランスのとれた食事づくりに役立てるのがよいだろう。
卵は1日1個を目安に、栄養豊富な食材としてバランスのとれた食事づくりに役立てるのがよいだろう。
10. 栄養満点の卵を取り入れて元気に過ごそう

卵は栄養満点で、さまざまな効果が期待できる食材だ。たった1つの卵でも、ほかの食材の何倍にもなる栄養素もある。朝食に卵を取り入れる「朝たま習慣」には、栄養をまるごと摂れる卵かけごはんもおすすめだ。ぜひ栄養豊富な卵を取り入れて、毎日の活力としてほしい。
結論
卵はそれ1つでおかずにもなるし、ごはんにかけるだけで卵かけごはんという一品料理にもなる。こんなにも簡単に食事に取り入れられて、栄養豊富でバランスが取れている食材はなかなかないだろう。1日1個の卵で、健康生活をはじめてみてはどうだろうか。
(参考文献)
※1 厚生労働省「特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム Ⅲ栄養指導」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03k-04.pdf
※2 文部科学省「第2章 日本食品標準成分表」
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365419.htm
※3 公益財団法人 長寿科学振興財団「栄養素」
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/index.html
※4 公益財団法人 長寿科学振興財団「抗酸化による老化防止の効果」
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/rouka-yobou/kousanka-zai.html
※5 一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所「栄養素の説明 - タンパク質」
https://www.orthomolecular.jp/nutrition/amino/
※6 公益財団法人 長寿科学振興財団「レシチン・コリンの効果と摂取量」
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/lecithin.html
※1 厚生労働省「特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム Ⅲ栄養指導」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info03k-04.pdf
※2 文部科学省「第2章 日本食品標準成分表」
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365419.htm
※3 公益財団法人 長寿科学振興財団「栄養素」
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/index.html
※4 公益財団法人 長寿科学振興財団「抗酸化による老化防止の効果」
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/rouka-yobou/kousanka-zai.html
※5 一般社団法人オーソモレキュラー栄養医学研究所「栄養素の説明 - タンパク質」
https://www.orthomolecular.jp/nutrition/amino/
※6 公益財団法人 長寿科学振興財団「レシチン・コリンの効果と摂取量」
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shokuhin-seibun/lecithin.html







