1. ういろうとは

そもそもういろうを知らない人もいるかもしれない。ういろうは、饅頭や大福、羊羹のようにコンビニに置かれるほど、ポピュラーな存在とはいい難い。通に好まれる和菓子のひとつである。羊羹と同じく、棹物(さおもの)、棹菓子(さおがし)に分類されるものだ。棹とは長い棒などを意味する言葉で、その名の通り元々は羊羹のように長いフォルムであったと推測されるが、現在では三角やスティックタイプなど食べやすいフォルムも多く存在する。そんな似た者同士の羊羹と大きく異なるところは、寒天が入っていないところ。全国各地で作られているが、名古屋や山口、宮崎、小田原などに、名店が多くあることで知られている。
ういろうの原料
ういろうは、非常にバリエーションの多い和菓子のひとつ。穀物粉に砂糖やお湯を加えて練り、蒸したもののことを指すが、穀物粉もうるち米、もち米、小麦粉、わらび粉、砂糖も白砂糖、黒砂糖など、それぞれ店や地方によって組み合わせが異なる。さらに小豆や抹茶、栗など、さまざまなフレーバーが存在する。
ういろうの味
ういろうは、むっちりとした独特の食感が持ち味。羊羹と違い寒天が入っていない=固める要素は蒸すという工程だけなので、このような食感になる。外郎餅と呼ばれることもあるくらいで、もちもち感がクセになるという人も多い。
2. ういろうと外郎

ういろうのルーツ
ういろうが外郎と書かれるのには、諸説あるが、最も広く伝えられているのが、人の名前からつけられたというもの。そもそもの始まりは、600年ほど前。中国は元王朝が栄えた時代に薬を調達する官僚のなかに陳という人がいた。彼は元が明に倒されたタイミングで、日本に帰化。その名を陳外郎と名乗り、漢方薬や医学を日本に伝えたとされている。以後この家は、外郎家として知られることになる。とくに咳や痰にきく薬を伝えたという説が有力で、その薬は息子にも引き継がれ、時の将軍足利義満にも献上され、「とうちんこう」という名前がつけられた。しかし便宜上なのか、外郎家がつくったものなので外郎と呼ばれるようになった。これが和菓子の外郎のルーツといわれている。
薬と外郎
薬がなぜ、和菓子の名前になったのか?陳外郎の息子である宗奇は朝廷で外国との付き合いをするいわば、外務官僚のような役割を担っていたが、その接待のときに用いられていたのが外郎のルーツとされるお菓子だ。宗奇自らが発案したものだったようで、見ためが薬の外郎に似ていたことから、外郎(ういろう)と名付けられたのだ。当時は京都にあった外郎家は、小田原に移転。以後もういろう家として外郎と薬を販売している。
3. ういろうと外郎売り
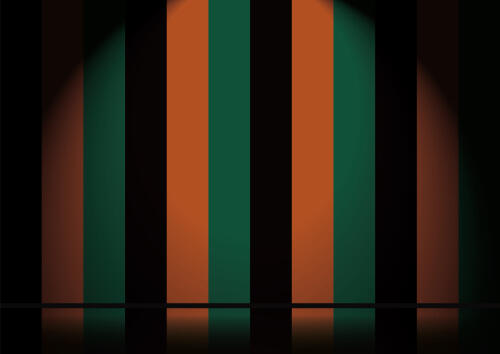
歌舞伎の有名な演目に「外郎売」がある。早口でまくし立てることから、早口言葉の練習などに使われることもある。こちらの題材になっているのは、薬の外郎のほう。そもそもは、江戸時代に2代目の市川團十郎が、せきや痰に悩まされ、セリフをうまくいえなかった時に、外郎と呼ばれる漢方薬を飲んだことで、症状が緩和された逸話を元にしたもの。実際に江戸時代、外郎は広く伝わる万能薬として知られるようになったそうだ。
外郎売の内容
滑舌がよくなる外郎を販売するために早口で外郎のよさをまくし立てる、この口上こそ、外郎売の醍醐味でもある。実際の内容は、じつは仇討ちの話。外郎売に扮するのは、父を工藤左衛門祐経に討たれた曽我五郎時致という人だ。彼と外郎を飲めば、遊女を口説けるかもしれないと目論んだ茶道珍斎の早口が作品の見どころといえるだろう。
結論
今回は、ういろうの漢字の由来を紹介した。ういろうが外郎と書かれる理由は、ういろうを作った人の家が外郎家だったから。その外郎家の作るういろうは、小田原でいまも買うことができる。機会があればぜひ、時代に思いを馳せて食べてみてはいかがだろうか。
この記事もCheck!







