1. 緑豆もやしの特徴

緑豆もやしは、もやしの中で最も多く流通している品種のひとつである。緑豆は、鮮やかな緑色が特徴的で小豆の仲間。中国では春雨の原料として使用されたり、おかゆなどに使われたりすることもあるほど、ポピュラーな植物だ。日本ではほとんど栽培されておらず、主に中国やミャンマーから輸入している。シャキシャキとした食感とみずみずしさが特徴で、炒め物や和え物などさまざまな料理に幅広く使うことができる。ちなみに緑豆は、日本では「やえなり」とも呼ばれる。
もやしはなぜ安い?
もやしは節約料理に欠かせない食材のひとつである。1袋30円程度、安い場合は10円代でも販売されている。なぜ、これほどまでに安いのだろうか。その理由は栽培方法にある。もやしの栽培には太陽光や土が不要で、かつ1週間程度で収穫できる。そのため、工場で大量生産することが可能となり、低価格で安定的に供給できるのだ。
しかし、現在の安すぎる価格とは適正とはいえず、生産者が生産コストの高騰と販売価格の下落との板挟み状態になっているのが現状である。適正価格での販売を実現し、今後も美味しいもやしを食べられるようにするには、我々消費者の意識から変えていく必要があるだろう。
しかし、現在の安すぎる価格とは適正とはいえず、生産者が生産コストの高騰と販売価格の下落との板挟み状態になっているのが現状である。適正価格での販売を実現し、今後も美味しいもやしを食べられるようにするには、我々消費者の意識から変えていく必要があるだろう。
2. 緑豆もやしの旬や選び方
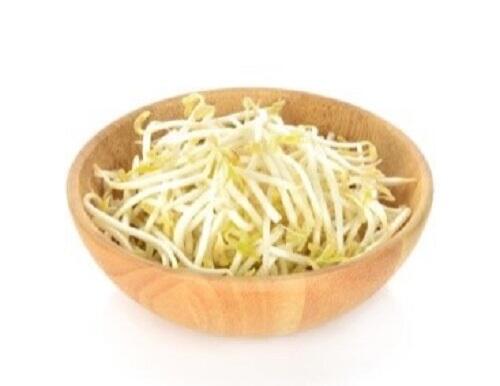
緑豆もやしは温度や明るさの管理された屋内で栽培されるため、とくに旬というものはなく、一年中購入することができる。天候不良などでほかの野菜の価格が高騰しているときでも、安価で安定的に生産できる緑豆もやしは家計の強い味方だ。ただし、水分を多く含むため傷みやすく日持ちしないので、1~2日で使いきれる分ごとに買うようにしよう。購入する際は次の点に注意して選ぶとよい。
茎が綺麗な白色で、ツヤのあるもの
茎やひげ根が茶色く変色しているものは、古くなっているので注意しよう。また、茎がしっかりとした太さのあるもののほうがシャキシャキとした歯ごたえが感じられてよい。
茎にハリがあり、豆が開いていないもの
豆が開いているものは鮮度が落ちている証拠なので注意しよう。また、茎がしなしなになっていたり、折れたりしているものも避けるようにしよう。
袋の中に水分が溜まっていないもの
緑豆もやしはみずみずしいのが特徴。組織が壊れて袋に水が溜まっているものは、古くなっているので気をつけよう。
3. 緑豆もやしの食べ方

緑豆もやしはクセがなく、どんな料理にも合うのが特徴だ。サッと茹でて和え物にしたり、肉と一緒に炒めたりしても美味しい。ラーメンの具材としてもよく使われる。やや手間ではあるが、調理する際にひげ根を取り除くと見栄えや食感がよくなる。最近では「根切りもやし」も売られているので、一度試してみるとよいだろう。
茹でて和え物やトッピングに
シャキシャキの食感を残すため、茹で時間は短めにするのがポイントである。和風の和え物のほか、韓国風ナムルにしても美味しい。また、熱々のラーメンや汁物に入れる場合は、食べている最中にもどんどんやわらかくなってくるので、やや固めに仕上げるとよいだろう。
肉と一緒に炒めてがっつりスタミナ系に
緑豆もやしは長時間炒めると食感が悪くなるだけでなく、水分が出てきて全体がベチャっとするので注意しよう。強火で短時間で仕上げるのが美味しく調理するコツである。緑豆は中国では料理やお菓子の材料として広く親しまれているとあって、緑豆もやしもとくに中華料理との相性がよい。中華風の味付けにするとより美味しく食べられるだろう。
結論
庶民の味として日本の食卓に欠かせない存在となっている緑豆もやしについて紹介した。主張しすぎない控えめな味のなかにもほんのりとした豆の甘みがあり、シャキッとした食感も料理の旨みを底上げする。緑豆もやしだけでも立派な一品ができあがるのでさまざまな調理方法を試してみてほしい。料理の脇役としてのみ利用するなんてもったいない。
この記事もCheck!







