1. 柿の種は大正生まれ

大正12年の秋のこと。新潟県長岡市の郊外にある住まいと店舗を兼ねた小さな米菓工場で、柿の種の生みの親である今井與三郎氏とその奥方が、懸命にあられ作りに取り組んでいた。
このあられが、のちに大ヒット商品となる柿の種にとって代わることになろうとは、その当時、夫婦は夢にも思わなかったに違いない。
当時、米菓子といえば、うるち米を使って作る「せんべい」が主流だった。今井氏も最初は、せんべい作りに取り組んでいたようだ。しかし、今井氏は、ある日店にあらわれた、大阪であられ職人をしていたという青年から、うるち米よりも高価なもち米で作るあられのことを聞き、あられ作りに取り組むことにしたのだった。
あられの製法については、大阪であられ職人をしていたという青年から、教わったようだ。しかし、実はその青年は、あられ職人とは名ばかりで、あられ屋に奉公していただけで、職人でもなんでもなかったということがのちに判明した。当然、あられ作りを教えるに値するような知識も持ち得ず、指導もそこそこに、いつのまにか姿をくらましてしまった。
このあられが、のちに大ヒット商品となる柿の種にとって代わることになろうとは、その当時、夫婦は夢にも思わなかったに違いない。
当時、米菓子といえば、うるち米を使って作る「せんべい」が主流だった。今井氏も最初は、せんべい作りに取り組んでいたようだ。しかし、今井氏は、ある日店にあらわれた、大阪であられ職人をしていたという青年から、うるち米よりも高価なもち米で作るあられのことを聞き、あられ作りに取り組むことにしたのだった。
あられの製法については、大阪であられ職人をしていたという青年から、教わったようだ。しかし、実はその青年は、あられ職人とは名ばかりで、あられ屋に奉公していただけで、職人でもなんでもなかったということがのちに判明した。当然、あられ作りを教えるに値するような知識も持ち得ず、指導もそこそこに、いつのまにか姿をくらましてしまった。
2. 柿の種を誕生させたハプニング
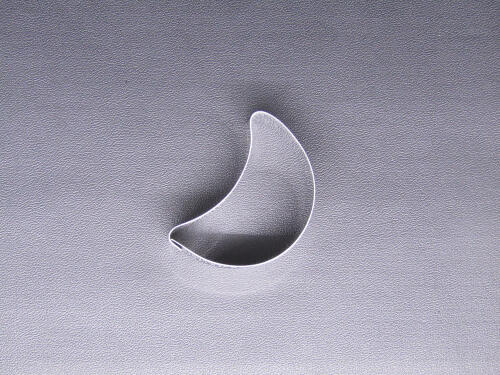
さあ大変!あられ作りの教えを乞う相手がいなくなったのだから、当時の夫婦はさぞかし慌てたに違いない。
しかし、すでにあられ作りに取り組んでしまった以上、もう後戻りはできない。今井氏は奥方と二人して、試行錯誤を繰り返し、その後も、あられ作りに懸命に取り組み続けることとなった。
今井夫婦が取り組んでいたあられは、薄くスライスしたもちをいくつか重ねて、小判型をした型抜きで、型をとって作られていた。しかし、ある日のこと、今井氏の奥方が、ちょっとした不注意で、小判型の型抜きを踏みつぶしてしまった。踏みつぶされた型抜きは、およそ小判型とはほど遠い形に歪んだ。
ああ、とんでもないことになった、これではあられが作れない!慌てた今井氏は、必死で型抜きを元の小判型に戻そうとした。しかし、元には戻らなかった。当時、型抜きは、とても高価なもので、また新しいのを導入するとなると、えらい出費になってしまう。それはやはり避けたいとばかりに、仕方なくその歪んだ状態の型抜きを使って、あられ作りを続けることになったようだ。
試行錯誤を繰り返し、苦心に苦心を重ねあられ作りを続けた結果、ようやく商品として出せるレベルのあられに仕上げることができた。
しかし、すでにあられ作りに取り組んでしまった以上、もう後戻りはできない。今井氏は奥方と二人して、試行錯誤を繰り返し、その後も、あられ作りに懸命に取り組み続けることとなった。
今井夫婦が取り組んでいたあられは、薄くスライスしたもちをいくつか重ねて、小判型をした型抜きで、型をとって作られていた。しかし、ある日のこと、今井氏の奥方が、ちょっとした不注意で、小判型の型抜きを踏みつぶしてしまった。踏みつぶされた型抜きは、およそ小判型とはほど遠い形に歪んだ。
ああ、とんでもないことになった、これではあられが作れない!慌てた今井氏は、必死で型抜きを元の小判型に戻そうとした。しかし、元には戻らなかった。当時、型抜きは、とても高価なもので、また新しいのを導入するとなると、えらい出費になってしまう。それはやはり避けたいとばかりに、仕方なくその歪んだ状態の型抜きを使って、あられ作りを続けることになったようだ。
試行錯誤を繰り返し、苦心に苦心を重ねあられ作りを続けた結果、ようやく商品として出せるレベルのあられに仕上げることができた。
3. インパクトのあるネーミング柿の種の由来

さて、今井夫婦の苦心の作である、歪んだ小判型のあられは、よくよく見ると、三日月形のその形が、新潟名産の大河津と呼ばれる甘柿の種にとてもよく似ていた。それで、「柿の種」と命名されることになった。命名のヒントをくれたのは、当時の取引先の主人だったとのこと。
さらに、屋号は、あられを作るきっかけをもたらしてくれた、自称あられ職人の青年に敬意を払い、青年の出身である大阪にあやかり、浪花屋と名付けられた。かくしてここに、「浪花屋製菓の元祖柿の種」が誕生した。
苦心に苦心を重ね、ようやくできあがった商品だけあって、柿の種は、評判となり、爆発的といえるほど売れに売れ、大ヒット商品になった。
昭和の初めには、新潟市への進出を果たし、売店や工場を開設することになった。創業からわずか数年で、小さな工場から、その後100年近く続く老舗の米菓子メーカーへと目覚ましい進展を遂げることになった。
柿の種は、浪花屋の登録商標ではない。そのため、現在、多数の菓子メーカーが、「柿の種」を販売している。そのことが功を奏して、柿の種は、世に幅広く認知され、米菓子の定番中の定番としてのゆるぎない地位を獲得することになったと考えられている。
さらに、屋号は、あられを作るきっかけをもたらしてくれた、自称あられ職人の青年に敬意を払い、青年の出身である大阪にあやかり、浪花屋と名付けられた。かくしてここに、「浪花屋製菓の元祖柿の種」が誕生した。
苦心に苦心を重ね、ようやくできあがった商品だけあって、柿の種は、評判となり、爆発的といえるほど売れに売れ、大ヒット商品になった。
昭和の初めには、新潟市への進出を果たし、売店や工場を開設することになった。創業からわずか数年で、小さな工場から、その後100年近く続く老舗の米菓子メーカーへと目覚ましい進展を遂げることになった。
柿の種は、浪花屋の登録商標ではない。そのため、現在、多数の菓子メーカーが、「柿の種」を販売している。そのことが功を奏して、柿の種は、世に幅広く認知され、米菓子の定番中の定番としてのゆるぎない地位を獲得することになったと考えられている。
結論
この記事では柿の種の誕生秘話を紹介した。まさに偶然の産物として生まれた柿の種。創業者の奥方が、型抜きを踏まなかったら、果たして、いま頃、どのようになっていたか?あれこれと想像しながら、柿の種をいただくのもまた感慨深いものがある。
この記事もCheck!







