1. レバーとは?どこの部位なの?
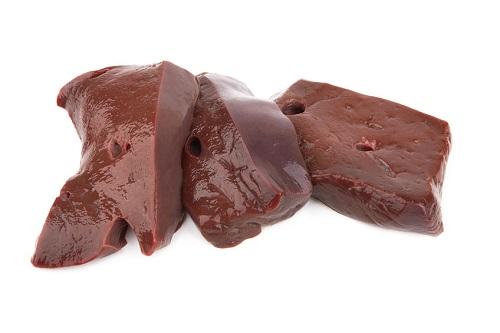
レバーとは、家畜の肝臓のことである。食肉として販売される豚・牛・鶏をはじめ、羊や馬などのレバーも食用として取り扱われている。本記事では一般的に食べられることの多い豚・牛・鶏のレバーについて見ていこう。
レバーの栄養とは
レバーの特徴の一つとして、カロリーや脂質、糖質が低く、ビタミン・ミネラル類が豊富に含まれていることが挙げられる。「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(※1、2、3)によると、100g当たりのカロリーでは、豚レバーが114kcal、牛レバーが119kcal、鶏レバーが100kcalとなっている。
ビタミン類でとくに多いのがビタミンAで、豚レバー100g当たりに13000μgRAE、鶏レバーでは14000μgRAEも含まれる。成人の1日当たりの耐容上限量が2700μgRAEとされていることから、不足どころか過剰摂取に注意が必要である(※4)。牛レバーは1100μgRAEと比較的少ない。またビタミンB群や鉄などの栄養素も豊富に含まれるため、ビタミンAの過剰摂取に気を付けつつ効果的に食事に取り入れたい。
レバーの味や特徴とは
レバーには肝臓特有の血生臭さがあるが、調理前に下処理を行うことで解消される。レバー全般としては、濃厚な風味や粘り気のある食感が大きな特徴だ。豚・牛・鶏、それぞれの異なる特徴も見ていこう。
豚レバーは弾力が強く、レバニラ炒めなどの炒め物や竜田揚げなどの揚げ物によく使われる。牛レバーは豚よりも柔らかい肉質で旨味や風味が強いのが特徴だ。現在は生食が禁止されているため、豚レバーと同様に炒め物や揚げ物にするのが一般的である。鶏レバーは3つのレバーのなかでは最も臭みが少なく、比較的食べやすいといわれる。柔らかくしっとりとしており、甘辛煮などの煮物やペーストにして食べることが多い。
2. 鶏の白レバーとは

一般的なレバー豚・牛・鶏の3種類について紹介したが、鶏には白レバーというものも存在する。鶏の白レバーとはどのようなレバーなのだろうか。
白レバーとは脂肪肝のこと
生の鶏レバーは赤みの強い色をしているが、白レバーは一般的なものよりも白っぽく、ピンク色である。脂肪分がたっぷりと含まれており、なめらかでトロッとした肉質が特徴だ。臭みがほとんどなく、濃い旨みとコクがあり、フォアグラに近い味といわれ人気を集めている。
白レバーが希少な理由とは
フォアグラは計画的にエサを与えることで生産されるが、白レバーは自然と脂肪肝となることによりできるものである。そのため、鶏をさばいてみて初めて発見される希少な食材なのだ。鶏をさばいて白レバーが見つかる確率自体も低く、流通量がかなり少ない。スーパーなどに出回ることはほとんどなく、限られた店において焼き鳥やパテ、炙りなどの料理で楽しむことができる。
3. レバーを美味しく食べる方法とは

レバーの調理前に行う必要があるのが、血抜きと臭み取りだ。臭みのあるまま調理すると料理全体の風味が悪くなってしまうため、次のような下処理を行うのが基本である。
血抜きの方法とは
まずは、レバーを包丁で切り分ける。鶏レバーにハツ(心臓)がついていたら、まずハツとレバーを切り離そう。ハツは縦半分に切って血を包丁でかき出し、レバーは一口大に切る。白い脂肪や筋も取り除いておく。豚と牛は、1cm幅ほどの厚さにそぎ切りにする。
ボウルに切ったレバーを入れ、水を溜めて手でかき混ぜながら洗う。濁りがなくなるまで水を入れ替えながら洗うと、血抜きができる。
臭み取りの方法とは
新鮮な鶏レバーは、血抜きが済んだらそのまま使ってもよい。臭みが気になる場合は、牛・豚と同様に次のような方法で臭み取りを行おう。
牛乳に漬ける
ボウルに牛乳を入れレバーを漬け、冷蔵庫で30分~1時間ほど置く。
醤油と酒に漬ける
レバニラや竜田揚げなどに使う場合におすすめだ。下味を付けながら臭み取りができる。
氷水、塩水に漬ける
長時間漬けると栄養や旨味が流出するため、臭みが弱い場合に適用できる。
塩と酢でもむ
ポリ袋などにレバーと塩、酢を入れてもみ込んでしばらく置く。
レバーは常温に放置すると傷むため、時間を置く場合は必ず冷蔵庫に入れる。また、牛乳に漬けた場合と塩と酢でもんだ場合は、調理前にレバーを流水で洗い流してから使おう。
レバーを美味しく調理するポイントとは
レバーは火を通し過ぎるとパサパサの食感になってしまう。食中毒を防ぐ目的の加熱は必要だが、焼き過ぎや煮込み過ぎにならないよう気を付けながら調理しよう。
結論
レバーとは、美味しいだけでなく栄養面でも優れた食材である。やや手間はかかるが下処理でしっかり臭みを抜くことで、レバーのもつ美味しさを最大限に楽しむことができる。また、豚・牛・鶏それぞれのレバーの特徴をおさえて調理や食べ方を工夫するとよい。
(参考文献)
※1出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/肝臓/生
※2出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/肝臓/生
※3出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」肉類/<鳥肉類>/にわとり/[副品目]/肝臓/生
※4出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」1-6ビタミン(1)脂溶性ビタミン、ビタミンAの食事摂取基準(p205)
この記事もCheck!







