目次
1. そもそもタンパク質とは

まず、タンパク質とは、どのような栄養素なのか見てみよう。(※1)
体内のタンパク質量
人体の約60%は水でできており、水をのぞいた残り40%の半分の約15~20%がタンパク質である。
アミノ酸とタンパク質の関係
タンパク質は、全部で20種類のアミノ酸が多数結合してできている。
アミノ酸とは
アミノ酸には11種類の非必須アミノ酸と9種類の必須アミノ酸がある。必須アミノ酸は体内で合成できないので、食品から摂取する必要がある。
2. タンパク質の働き

タンパク質は筋肉・臓器・骨・髪・皮膚など身体を構成する材料になる。また消化吸収や、代謝のサポート、免疫機能などに関わり、生命維持に欠かせない働きがある。(※2)
3. タンパク質の1日の摂取量

1日に必要なタンパク質の量は、摂取エネルギーの約13~20%が望ましいとされている。1日当たりの摂取量は、成人男性で約60-65gで、成人女性で約50gが推奨されている。(※3)
4. タンパク質が不足したらどうなる?

タンパク質の働きや1日の摂取量が分かったところで、次はタンパク質が不足するとどうなるかを見ていこう。(※3)
筋力の低下
タンパク質は、その多くが筋肉に蓄えられている。必要なエネルギーを十分補給しないでいると、身体は筋肉を分解することでエネルギーを作り出すようになるので、筋力が低下する可能性がある。
免疫機能の低下
タンパク質は、身体の機能を調節するホルモンや酵素の材料でもある。したがって、タンパク質が不足すると、免疫機能が低下する可能性がある。
5. タンパク質を摂りすぎたらどうなる?

タンパク質が不足するとどうなるか分かったところで、次は摂取しすぎるとどうなるかを見てみよう。
内臓に負担がかかる
タンパク質を過剰に摂取すると、身体に必要でない分を排出するために、肝臓や腎臓に多く負担がかかる。そのため内臓疲労が起こる可能性があるといわれている。
結石ができる
動物性のタンパク質を摂取すると、身体の中にシュウ酸や尿酸が蓄積する。シュウ酸は尿に含まれるカルシウムと結合すると石のようになり、これが尿管を詰まらせる原因になることもある。
カロリーを過剰に摂取してしまう
タンパク質を多く含む食品のなかには、高カロリーなものも多い。食べすぎると肥満の原因になるので注意しよう。
6. タンパク質が多い食べ物

タンパク質を摂りすぎるデメリットが分かったところで、ここではタンパク質の多い食べものを見てみよう。以下では、食品名と可食部100gあたりの含有量を紹介する。(※4)
肉類
- 鶏ささみ...23g
- ローストビーフ...21.7g
- 豚ロース...19.3g
卵類
- 生たまご...12.3g
- 茹でたまご...12.9g
- ウズラのたまご生...12.6g
魚介類
- 魚肉ソーセージ...11.5g
- スルメ...69.2g
- イワシ丸干し...32.8g
乳製品
- 乳...3.3g
- パルメザンチーズ...44g
- ヨーグルト...4.3g
大豆製品
- きな粉...35.5g
- 納豆...16.5g
- 豆腐...6.6g
7. コンビニで買えるタンパク質が多い食べ物
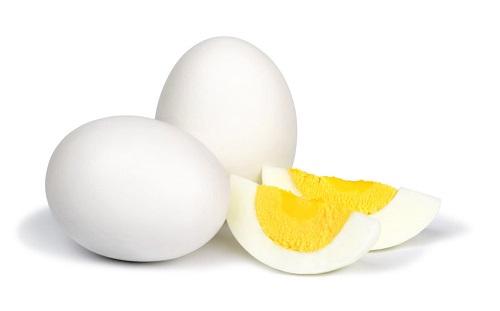
以下では、コンビニで買えるタンパク質の多い食べ物を記載する。
- サラダチキン
- サラダフィッシュ
- 茹でたまご
- プロテインバー
8. タンパク質の働きを助ける食べ物

ここではタンパク質の働きを助けてくれる栄養素と、多く含まれる食品を紹介しよう。(※5)
ビタミンB6
ビタミンB6はタンパク質の分解や合成を助ける働きをしてくれる。そのほか、皮膚や粘膜の健康維持にも役立つ。ビタミンB6は、くるみ・まぐろ・バナナなどに多く含まれている。
ビタミンC
ビタミンCはコラーゲンの生成に欠かせない栄養素で、コラーゲンとは骨と筋肉をつなぐタンパク質である。ビタミンCは、アセロラやピーマンなどに多く含まれている。
結論
タンパク質とは人体の大部分を構成する大切な栄養素だということが分かった。また、肉類・卵類・大豆製品・魚介類・乳製品に多く含まれており、ビタミンB6やビタミンCと一緒に摂るのがよい。このことを、日々のタンパク質摂取の際に役立ててはいかがだろうか。
(参考文献)
※1参照:森永製菓 「タンパク質とは【タンパク質の種類、機能、働きなどを解説】」
※2参照:大塚製薬 「タンパク質」
※3参照:健康長寿ネット「三大栄養素のたんぱく質の働きと1日の摂取量」
※4参照:グリコ 「タンパク質の摂りすぎは危険!?過剰摂取による影響とは」
※5参照:健康長寿ネット「ビタミンCの働きと1日の摂取量」
この記事もCheck!







