目次
1. 和食の懐石料理とは?

まずは懐石料理の定義から見ていこう。懐石料理はもちろん和食のひとつであるが、なぜその名があるのか、どのような特徴があるのかは知らない人も多い。懐石料理の概略を見ていこう。
懐石料理とはお茶の前に頂く食事のこと
懐石料理の歴史は古く、その誕生は鎌倉時代に由来するといわれている。当時は禅宗の僧たちが晩に食する軽食のことを懐石と呼んでいた。これが茶道と結びつき、茶懐石という料理が誕生した。室町時代中期に茶道と料理道いずれも目覚ましく発展し、質素を旨としながらも現代まで残る茶懐石料理はこの時代に生まれたとされている。懐石料理は旬の食材を使うのがルールであり、茶席の次の間で作られるのが基本である。茶事の一部として供される懐石料理は、暁、朝、正午、夜咄 (よばなし)など時間によってメニューや器が異なる。茶事の前に供される軽食といった趣である。
懐石料理は和食の基本の一汁三菜
懐石料理といえば豪華な和食を思い浮かべることが多いが、本来の茶懐石料理は非常に質素である。一汁三菜で構成される懐石料理は、味噌仕立ての汁に向付、煮物、焼き物が供される。
懐石料理の「懐石」の意味とは
それでは懐石という言葉はなにに由来するのだろうか。焼いた石を布に包んで懐に温める温石という風習が鎌倉時代に存在していたが、温石で懐を温めるように腹も満たすという意味から懐石という言葉が生まれたとされている。これは安土時代の茶の湯伝書である南方録に記された説である。
2. 懐石料理とそのほかの和食との違いとは?

懐石料理は本来質朴なものである。しかし現在では、料亭などで供される豪華な懐石料理も隆盛である。ここで和食のなかでも格の高いいくつかの料理と懐石料理を比較し、その相違を明確にしてみよう。
懐石料理と会席料理の違い
同じ音を持つ懐石料理と会席料理。懐石料理が茶の湯とともに発展したのに対し、懐石料理の起源は俳席にある。江戸時代に京都で行われた俳句の会に供された酒食が元祖とされ、やがて酒量が増えた結果、俳席料理は宴会本位へと変化した。会席料理と呼ばれるようになったのは延宝年間という説がある。明治時代になって会席料理の内容はより高級になり複雑化し現在に至る。懐石があくまで質素を旨とするのに対し、会席は酒が供される豪華な食事であることが多いのである。
懐石料理と本膳料理の違い
本膳料理とはあまり耳にしない言葉であるが、和食の中でも最も格式のある供応料理が本膳料理である。本膳料理が確立したのは室町時代とされるがその内容は非常に複雑で、流派や年代によってかなりの相違が存在する。江戸時代中期の本膳料理は品数も非常に多く形式ばったモノとなったため、明治時代以降に簡略化された経緯がある。会席料理は本膳料理の後身とされているが、侘びた茶席の料理である懐石とは起源も成り立ちも異にするといえるだろう。
懐石料理と割烹料理の違い
街中でもよく見かける割烹料理。割烹とは中国語に由来し、本来は食材を下ごしらえして生で食べられる料理と加熱して味付けした料理を指す。前者は刺し身や酢の物、塩からやこのわた等であり、後者は焼き物や蒸し物が該当する。つまり食材を調理することを割烹と呼んでいたのが、現在は高級な和食店の趣がある。懐石料理とは異なり、コースではなくアラカルトで注文できるのが大きな違いといえるだろう。
3. 現在の懐石料理の流れや内容とは?
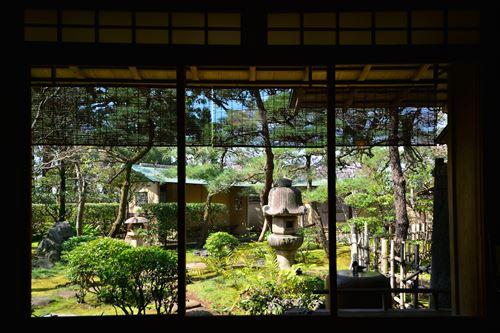
現在我々が料亭などで食べる懐石料理は一汁三菜にとどまらず、品数も多く豪華である。それらはそのような順番で供されてくるのだろうか。一般的な懐石料理の流れとマナーについて概略を紹介する。
折敷
懐石料理の最初に茶事の亭主が運んでくるのが折敷である。折敷とは木製方形の盆を指し、飯、汁、向付が乗せられている。これらは日と月と星の象徴として三光ともいう。本来の向付は膾仕立てであったが、現在は刺し身なども用いられる。折敷はまず汁物から口をつけて、飯と汁だけ食べる。食べ終わった後は、箸を折敷の左側に出るように置く。
酒
次に主人が運んでくるのが酒である。銚子と盃が運ばれてくるので、客は盃を右手にとり左手を添えるようにして酌を受ける。盃はもとの位置に戻す。懐石料理の酒は淡白な味わいに合わせて穏やかな香味のものが多い。
向付
会食者と乾杯した後に、折敷に乗っている向付を食べる。
煮物
懐石のメインの始まりは煮物椀である。椀盛とも呼ばれるこの料理は汁物と混同しがちだが、一汁三菜の菜のひとつである。真薯などの具が椀の中に鎮座しているのが常で、それなりのボリュームがある。冷めないようにふた付きの椀が運ばれてくるため、外したふたは右側に置き、食べ終わったら再びふたをする。
焼物
一汁三菜の最後の一品とされるのが焼物である。焼物は通常、ひとつの器に会食者の人数分が盛りつけられて、取り箸が添えられていることが多い。ただしこれも流派によって多少スタイルを異にする。正客から次客へと順番に皿がまわって来たら、向付用の皿に取る。
預鉢
茶懐石の基本はあくまで一汁三菜であるが、現在の茶事ではさらに預鉢と呼ばれる一皿が供されることが多い。炊き合わせなどがそれに当てられる。焼物と同じように大皿で運ばれて取り皿に取るのがルールであるが、これも流派によって異なる。
吸物
上記の食事が終わった頃に吸物が運ばれる。この吸物の量はほんの一口、そのため箸荒いとか小吸物などとも呼ばれる。この後に続く八寸のために口を清める意味があるため、あっさりとした味のものが多い。吸物の椀のふたは向付の上中央において食する。
八寸
八寸は主人が運んでくる酒のための肴である。たいていは海のものと山のものが一種ずつ盛られていることが多い。竹箸でそれらを取ったら吸物のふたに取り分ける。酒を互いに注ぎ合ってくつろぐ場である。
湯桶
懐石料理の一連の流れを締めくくるのが湯桶である。お湯と香の物、つまりつけもので器を清めてそれを飲むという動作には禅の影響があるとされている。湯の子と呼ばれる焦げ飯が運ばれてくるため、これを飯椀によそい汁椀に湯を注ぐ。湯を飲んだあとは懐紙で清めて、飯椀も汁椀も逆さにしておくのである。
菓子とお茶
懐石料理の一連の流れが終了すると、「粗茶一服差し上げたく」という亭主の言葉とともに茶を喫する流れへと変わっていく。折敷が下げられると主菓子が運ばれるが、席改めのため客は一時退席することもある。亭主が準備を整えたのち、菓子と茶を喫することになるのである。
結論
和食のなかでも格式のある懐石料理は、会席料理と混同されることも多い。懐石料理は禅宗や茶道と深い関連がある料理であり、本来はその精神を尊んだ質朴なものであった。現在は料亭などで豪華な懐石料理を食することも多いが、正式な茶席では基本を遵守することが多い。礼儀作法を心得て参加するようにしよう。和食にはそのほか、会食や本膳といった文化がある。その相違とともに和食を楽しみたい。
この記事もCheck!







