目次
1. 鶏ささみってどこの部位でどんな肉?
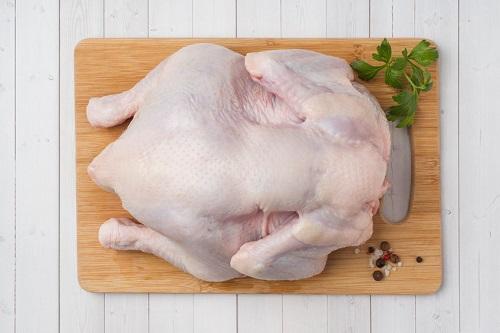
ヘルシー食材として人気が高まっているささみ。白っぽい見た目だが、形が笹の葉に似ていることからささみという名前になったとされる。ここでは、ささみの基本情報を確認していこう。
鶏ささみは胸肉の奥の部位
鶏ささみは厳密にいえば胸肉の一部だが、胸肉の奥にあり胸骨にくっついているため、区別される。鶏1羽からわずか2枚のささみしか取れないため、当然ながら胸肉よりも取れる量は少ない。牛肉の部位として考えると、ささみはヒレ肉に相当する。ヒレ肉とささみが同じと考えるとイメージが変わってくるだろう。
鶏ささみは淡白で柔らかい部位
鶏ささみは胸肉と同様に淡白な味わいを楽しめる。また、胸肉は加熱するとパサパサになってしまうが、ささみは加熱しすぎなければほどよい柔らかさとしっとり感を堪能できる。サラダや和え物に使う場合は、蒸したり茹でたりするのがおすすめだ。ささみは加熱すれば手でさけるので調理も簡単だ。また、チキンカツなど揚げ物にするのもおすすめだ。サクサクの衣とささみのしっとりとした食感の両方を楽しめる。
2. 鶏ささみはダイエットに人気の部位

「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」には、生のささみについて「若どり」と「親」の2種類の栄養価が収録されている。このうち以下で紹介しているのは、一般的に食べられている「若どり肉」の100gあたりの栄養価である。また、ささみの栄養面の特徴についてもあわせて確認しておこう。
ささみ(生)の100gあたりの栄養価
エネルギー:98kcal
たんぱく質:23.9g
脂質:0.8g
炭水化物:0.1g
たんぱく質:23.9g
脂質:0.8g
炭水化物:0.1g
脂肪酸
- 飽和脂肪酸:0.17g
- 一価不飽和脂肪酸:0.22g
- 多価不飽和脂肪酸:0.13g
ビタミン
- レチノール:5μg
- ビタミンD:0μg
- ビタミンE:0.7mg
- ビタミンK:12μg
- ビタミンB1:0.09mg
- ビタミンB2:0.11mg
- ナイアシン:12.0mg
- ビタミンB6:0.62mg
- ビタミンB12:0.2μg
- 葉酸:15μg
- パントテン酸:2.07mg
- ビオチン:2.8μg
- ビタミンC:3mg
ミネラル
- ナトリウム:40mg
- カリウム:410mg
- カルシウム:4mg
- マグネシウム:32mg
- マグネシウム:32mg
- リン:240mg
- 鉄:0.3mg
- 亜鉛:0.6mg
- 銅:0.03mg
- マンガン:0.01mg
- ヨウ素:0μg
- セレン:22μg
- クロム:0μg
- モリブデン:4μg
食物繊維:0g
鶏ささみは鶏胸肉より低カロリーな部位
鶏ささみのカロリー量は100gあたり98kcalであり、同じく低カロリーとして知られている「鶏胸肉(若どり/皮なし)」の105kcalよりも低い数値となっている(※1)。また、成分表に糖質量の記載はないが、炭水化物の含有量が0.1gであることを考えると相当少ないといえそうだ。ほかにも脂質量も少ないため、カロリー制限や糖質制限をしている人にとっておすすめの食品だといえる。
たんぱく質量や必須アミノ酸のバランスも優秀な部位
鶏ささみは100gあたり23.9gのたんぱく質量を含んでいる。成人男性(18~64歳)の1日あたりのたんぱく質の推奨量は65gであるため(※2)、鶏ささみを100g食べれば1食分のたんぱく質量を摂ることができる。また、鶏ささみはアミノ酸のバランスがよいのも特徴(※1)。必須アミノ酸はもちろん、非必須アミノ酸もバランスよく含むため、鍛えている人などにもおすすめである。
ささみはヘルシーな部位だが焼き鳥はタレに注意
ささみは焼き鳥でも人気だが、味付けによってカロリーが異なるので注意が必要だ。たとえば、塩の場合はカロリーは変わらないためヘルシーなままだが、タレ味の場合はカロリーが高くなってしまう。焼き鳥のタレによってカロリーは異なるため一概にはいえないが、ささみにタレを5g(小さじ1杯)かけると6~10kcalほどカロリーが高くなる。そのため、ささみ1本(50g)が49kcalでもタレをつけると約60kcalになってしまう。
3. 淡白な部位の鶏ささみを美味しく食べる方法

ささみは柔らかくしっとりとした食感を楽しめるが、下処理を誤ってしまうとせっかくの味わいや食感を損なってしまう。ここでは、ささみを美味しく食べるためのポイントを紹介する。
鶏ささみは筋取りの下処理が必要
ささみには、1本筋が通っている。丁寧に取り除くと口当たりが格段によくなる。筋取りは、まず筋を確認する。筋の端に切り込みを入れ、筋の端を掴めるくらい、取り出す。筋が下にくるようまな板にのせ、包丁の刃先を斜めにするよう筋に当て、しごくように筋を取っていく。初めはなかなか包丁が動かないので、ノコギリのように前後に小刻みに動かすといい。そのほか、筋を取り除いてから、観音開きにして、身の厚みを薄く仕上げるのもおすすめ。これなら、初心者でも簡単に行える。
しっとりと調理するコツ
ささみを簡単にしっとりとした食感にしたいなら、電子レンジで酒蒸しにするのがおすすめだ。ささみに酒と塩をふり、ふんわりラップをかけて、600Wの電子レンジで2分ほど加熱し、あとは冷めるのを待つだけ。もし、まだ中に火が通っていないようなら30秒ほど電子レンジにかけよう。冷ます時は必ず汁の中で冷ますのがポイントだ。焼くときは筋を取ったら、そのまま焼くとよい。また、表面に少し小麦粉をふってコーティングするのもおすすめだ。パサつきを防ぐという意味では、塩麹を利用するのもひとつの手。塩麹は、肉のたんぱく質を分解する酵素をもっているので、漬けておくだけでふんわり柔らかに仕上がる。
4. 鶏のささみとほかの部位との違い

ここまでは、ささみの特徴を挙げてきたが、ほかの部位と比べたときの違いも気になる。ここでは、鶏肉の中でも食べられる頻度が高い胸肉ともも肉と比較してみる。
鶏肉の部位:胸肉
鶏の胸部分の肉。脂肪が少なく、たんぱく質が多い胸肉は、味わいも淡白。ささみよりも肉厚だが、もも肉に比べるとかなりあっさりとしている。もも肉よりもさらにリーズナブルで、多くの場合は、1枚肉で販売されている。油脂の多い皮を取り除くとさらにヘルシーだ。脂肪がなくあっさりしているので、油と組み合わせた調理法、またはその淡白な味わいを活かした蒸し物がいいだろう。ささみと同じくヘルシーだが、ささみよりもパサつきやすいのが難点。どうしてもパサつきがちなので、片栗粉をまとわせる、塩麹などで下味を付けるなど、ひと手間加えるとぐっと美味しさが増す。また、大きいものは身が厚いので、観音開きや、そぎ切りにするなど、切り方にも工夫をするといい。
鶏肉の部位:もも肉
鶏のもも肉は、脚のもも部分。筋肉質で、旨みとコクがある。ささみと異なり、脂肪もたっぷりとついているので、どんな料理に使ってもジューシーに仕上がる。ささみと比べると肉は少し硬めだが、弾力が楽しめる。骨つきやぶつ切りで売られていることもあるが、最もポピュラーなのは骨なしの1枚肉だ。みんなが大好きな唐揚げに使われるのも、もも肉が多い。前述の通り、ジューシーなので煮る、焼く、揚げるなど、幅広い調理法に活用できる。黄色い余分な油は、キッチンバサミで取り除くとより美味しくいただくことができる。1枚で焼く場合、どうしても縮みやすい。その際はあらかじめ、皮目にフォークなどで穴を空けるといい。味のしみも早くなって一石二鳥だ。
5. 鶏ささみとは別物!焼肉の和牛のささみはどんな部位?

ささみと呼ばれる部位が実は牛肉にもある。とはいっても、鶏ささみのように一般的に浸透していない。その理由はささみ以外の呼び方で呼ばれることにある。日本ではささみと呼ばれる部位だが、海外では「フランク」と呼ぶのが一般的だ。
牛のささみは腿の付け根の部位
牛のお腹部分の肉はバラ肉と呼ばれるが、なかでも腿の付け根に位置するのが牛ささみだ。バラ肉は内側を中バラ、外側を外バラと区別するが、牛ささみは外バラに近い。牛の大部分を占めるバラ肉だが、牛ささみはわずかしか取れないため、非常に希少価値が高い。
牛のささみは霜降りの部位
バラ肉は脂が多いイメージだが、牛ささみは比較的赤身が多く、美しい霜降りが入っているのも特徴だ。赤身肉だが肉質は柔らかく、バラ肉ならではの甘さや濃厚なコクも楽しめる。脂っこい肉が苦手な人にはぜひ食べてほしい肉だ。食べ方はシンプルに焼き肉がおすすめで、肉本来の味わいをそのまま楽しめる。
牛のささみのカロリーや栄養
牛ささみは希少な部位であるため、残念ながら食品成分表には記載がない。そのため、バラ肉の値で代用する(※3)。主な栄養素の値(100g当たり)は以下のようになる。
エネルギー:338kcal
たんぱく質:14.4g
脂質:32.9g
炭水化物:0.2g
鉄:1.5mg
亜鉛:3.0mg
ビタミンB12:1.3μg
たんぱく質:14.4g
脂質:32.9g
炭水化物:0.2g
鉄:1.5mg
亜鉛:3.0mg
ビタミンB12:1.3μg
牛ささみはバラ肉の一部なので、カロリーは高めだ。一方、鉄や亜鉛など普段の食生活で不足しがちな栄養素が多く含まれている。
結論
鶏肉は、部位によって味わいがかなり異なる。ただ、比較的どの部位も和洋中問わず、オールラウンドに使うことができる。骨つきのものは出汁が出るので、汁物やスープのベースにも向いている。美味しく食べるには、下処理が大切。しっかり覚えて美味しくいただこう。
(参考文献)
※1 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
https://fooddb.mext.go.jp/
※2 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年)」
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
※3 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11074_7
※1 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
https://fooddb.mext.go.jp/
※2 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年)」
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
※3 文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=11_11074_7







