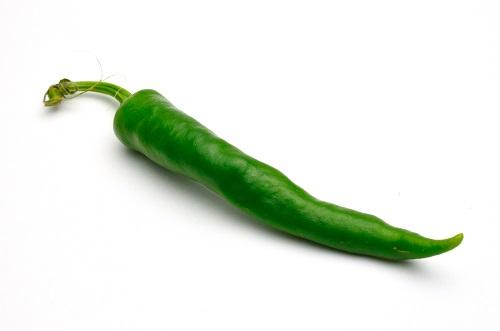1. ししとうは生食できる!

いままでは当たり前のように炒めたり煮たりしてから食べていたししとうを、次はぜひ生のまま食べてみてもらいたい。少し違う食感やフレッシュさを、堪能してもらいたい。
生のししとうの食感は?
生のししとうの食感はというと、皮が硬めで噛み切りにくいというのが正直なところになるだろう。よくいえば、シャキシャキしているともいえるが、子どもにとっては少し食べにくいと感じるかもしれない。
生のししとうはどんな味?
生のししとうは、加熱したものと比べると少し苦みがあるのが特徴といえる。味覚の好みによって、賛否両論分かれるところだろう。
生のししとうの種やヘタは食べられるのか?
生のししとうの種とヘタは、可食部なので食感さえ気にならなければ問題なく食べることができる。むしろ、皮の硬さからは想像できないくらい、種とヘタは柔らかくて食べやすいのでおすすめしたい。
2. ししとうを生で美味しく食べる方法

生食ししとうの、美味しい食べ方とメニューをいくつか紹介していく。
ししとうの生姜味噌添え
<材料>
ししとう、しょうが(チューブ)、味噌
<作り方>
ししとうは水でよく洗ってから、茎の部分を切り落としておく。しょうが(チューブ)と味噌を、混ぜ合わせておく。ししとうを生姜味噌につけて食べる。生姜味噌との相性がクセになる美味しさである。
ししとうの生ハム巻き
<材料>
ししとう、生ハム
<作り方>
ししとうは水でよく洗ってから、茎の部分を切り落としておく。ししとうを生ハムで巻いたら、完成となる。生ハムの塩味がよいアクセントになる一品である。
・ししとうの生姜醤油和え
<材料>
ししとう、しょうが(チューブ)、醤油
<作り方>
ししとうは水でよく洗い、茎の部分を切り落としてから、輪切りにしておく。しょうが(チューブ)と醤油を合わせたところに、ししとうを絡めたら完成となる。佃煮に近い食感と味わいになっている。
奴のししとうのせ
<材料>
ししとう、豆腐、めんつゆ、かつお節
<作り方>
ししとうは水でよく洗い、茎の部分を切り落としてから、粗みじん切りにしてめんつゆと合わせておく。豆腐を食べやすい大きさに切ってから、ししとうをのせてかつお節をちらしたら完成。
韓国風ししとう和え
<材料>
ししとう、しょうが(チューブ)、にんにく(チューブ)、コチュジャン、豆板醤
<作り方>
ししとうは水でよく洗い、茎の部分を切り落としてから、粗みじん切りにする。しょうが(チューブ)、にんにく(チューブ)、コチュジャン、豆板醤を合わせてから、ししとうと和えたら完成。豆板醤の辛みとコチュジャンの甘みがよく合う1品となっている。
ししとうとカニカマのサラダ
<材料>
ししとう、カニカマ、鶏ガラスープの素、塩昆布、ゴマ油
<材料>
ししとうは水でよく洗い、茎の部分を切り落としてから、縦に細めに切る。カニカマは、ほぐしておく。鶏ガラスープの素、塩昆布、ゴマ油を合わせてから、ししとうとカニカマと和えたら完成。塩昆布の塩味が、美味しいアクセントになっている。
3. 生で美味しいししとうの選び方

生食向けのししとうの種類を紹介していく。合わせて、なるべく避けたい辛いししとうを見抜くコツを提案していく。
生食向けのししとうとは
生食向けのししとうの種類として、伏見とうがらしや万願寺とうがらしなどが挙げられる。この2つについて、紹介しよう。
<伏見とうがらし>
伝統的な京野菜で、甘みが強いという特徴があり、「伏見甘長とうがらし」とも呼ばれている。
<万願寺とうがらし>
同じく京野菜で甘みが強く、伏見とうがらしよりも果肉が大きく肉厚である。
・辛いししとうを見抜くコツ
購入時に辛いししとうを判断できるのであれば、避けていきたいことであろう。以下に解説することを、参考にしてもらいたい。
<ししとうが辛くなる理由>
辛いししとうが作られてしまうことには、それなりに理由がある。その理由として最も多いのが、生産時にストレスを受けているということである。具体的にストレスというのは、乾燥や水不足といった天候不良のことを指す。
<見分け方のポイント>
辛いししとうの特徴として挙げられることは、次のようになる。
- 全体的に光沢がない
- 全体的にしわが少ない
- 形がいびつ、小さいなど
購入時には、よく見て気をつけてもらいたい。
結論
本記事では、ししとうは生食できるということを伝えてきた。いままでは加熱して食べることが多かったことであろうししとうを、ぜひ生食として食べることにチャレンジしてみてもらいたい。多くのメニューも併せて紹介しているので、参考にしてもらい、新しいししとうの魅力に気付いてもらえたら幸いである。
この記事もCheck!