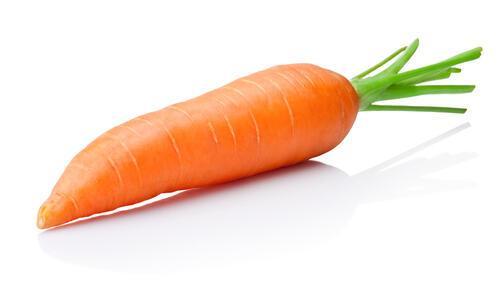目次
- 炭水化物:9.3g
- たんぱく質:0.7g
- 脂質:0.2g
1. にんじんの栄養成分
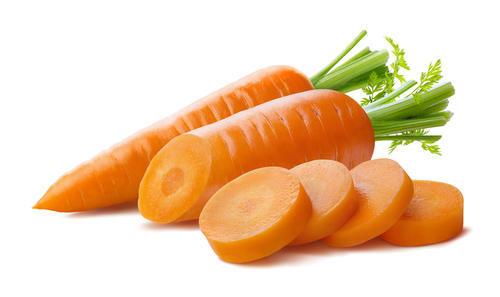
「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(※1)によると、にんじん(皮付き、生)100gあたりに含まれる主要な栄養素は下記の通りである。
ビタミン類ではβ-カロテン、ミネラル類ではカリウムが多い。また、食物繊維が含まれている点もにんじんの特徴である。各栄養素の特徴と含有量を紹介する。
β-カロテン
にんじん100gあたりには、6900μgのβ-カロテンが含まれている(※1)。β-カロテンは、体内でビタミンAに変換される栄養素だ。ビタミンAは脂溶性ビタミンの一つとして、さまざまな働きをする。(※2)
カリウム
にんじん100gあたりのカリウム含有量は300mgである(※1)。カリウムは大部分が細胞内に存在し、主に細胞の浸透圧を調整する役割をもつ。また、ナトリウムの排出を促す作用、心臓や筋肉の機能を調節する作用などもある。(※3)
食物繊維
にんじん100gあたりに含まれる炭水化物9.3gのうち、2.8gを食物繊維が占めている。その内訳は、水溶性食物繊維が0.7g、不溶性食物繊維が2.1gである。(※1)
食物繊維は人間の消化酵素で分解されない栄養素のため、吸収されず大腸まで到達しさまざまな働きをする(※4)。
2. にんじんの栄養の効果

にんじんに含まれる栄養素のうち、とくにβ-カロテン、カリウム、食物繊維による効果効能が期待できる。どのような効果があるのか、詳しく紹介する。
目の健康を保つ
β-カロテンから変換されたビタミンAの主要成分レチノールには、目の粘膜を健康に保つ働きがある。また、視細胞での光刺激反応に関与する物質の合成にも使われており、薄暗い場所で視力を保つ効果も期待できる。(※2)
肌の健康を保つ
ビタミンA(β-カロテン)には皮膚の粘膜を健康に保つ働きもある。抗酸化作用により、細胞の酸化が抑制されるため、肌の老化を防ぐ効果も期待できる。β-カロテンの適度な摂取は、肌の健康を維持することに役立つのだ。(※2、5)
生活習慣病の予防
β-カロテンの抗酸化作用により、人体に有害となる活性酸素の発生や働きを抑える効果がある。活性酸素が増えると生活習慣病を引き起こす要因となる。抗酸化物質のβーカロテンを摂取することで活性酸素の働きが抑制されるため、生活習慣病の予防にもつながる。(※5)
発がん物質の効果低減
β-カロテンをはじめとする抗酸化物質は、がんの予防にも効果があるといわれる(※5)。また、ビタミンAの主成分であるレチノールは、上皮細胞にて発がん物質の効果を軽減するという研究もあるようだ(※2)。
むくみ防止
ナトリウムの摂り過ぎはむくみの原因となる(※6)。カリウムにはナトリウムの排出を促す作用があるため、塩分量を控えるとともにカリウムを摂取することがむくみ防止に効果的である(※3)。
便秘解消
食物繊維には、主に便通を促す働きがある。とくににんじんに多く含まれる不溶性食物繊維は、水分を吸収し便のかさを増すため、排便がスムーズになる。また、水溶性食物繊維も含め、腸内の善玉菌のエサとなることにより、整腸効果と便秘解消が期待できる。(※1、4)
3. にんじんの栄養は調理によって変化する?

にんじんには、さまざまな健康効果が期待できる栄養素が含まれていることがわかった。では、これらの栄養素の含有量は調理の仕方により変化するのだろうか。にんじん100gあたりの含有量を比較してみよう。
皮の有無(※1、7)
・β-カロテン
・皮付き(生):6900μg
・皮なし(生):6700μg
・カリウム
・皮付き(生):300mg
・皮なし(生):270mg
・食物繊維
・皮付き(生):2.8g(水溶性食物繊維0.7g、不溶性食物繊維2.1g)
・皮なし(生):2.4g(水溶性食物繊維0.6g、不溶性食物繊維1.8g)
いずれの栄養素も、同じ重量で比較すると皮付きのほうが多い。
茹で(※1、8)
・β-カロテン
・生(皮付き) :6900μg
・茹で(皮付き):6900μg
・カリウム
・生(皮付き) :300mg
・茹で(皮付き):270mg
・食物繊維
・生(皮付き) :2.8g(水溶性食物繊維0.7g、不溶性食物繊維2.1g)
・茹で(皮付き):3.0g(水溶性食物繊維1.0g、不溶性食物繊維1.9g)
同量で比較すると、β-カロテン量は茹でても変化しない。カリウム、不溶性食物繊維は生のもののほうが多い。水溶性食物繊維は茹でたほうがやや多くなる。
冷凍(※1、8、9、10)
・β-カロテン
・生(皮付き) :6900μg
・冷凍(生) :9100μg
・茹で(皮付き):6900μg
・冷凍(茹で) :10000μg
・カリウム
・生(皮付き) :300mg
・冷凍(生) :200mg
・茹で(皮付き):270mg
・冷凍(茹で) :130mg
・食物繊維
・生(皮付き) :2.8g(水溶性食物繊維0.7g、不溶性食物繊維2.1g)
・冷凍(生) :4.1g
・茹で(皮付き):3.0g(水溶性食物繊維1.0g、不溶性食物繊維1.9g)
・冷凍(茹で) :3.5g
同量で比較すると、β-カロテンは冷凍のにんじんのほうが生のものより2200μg多い。また、茹でる場合も冷凍のほうが3100μg多い。また、食物繊維量も冷凍にんじんのほうが多い。ただしカリウムは、生のにんじんがもっとも多い。
油いため(※7、11)
・β-カロテン
・生(皮なし) :6700μg
・油いため(皮なし):9900μg
・カリウム
・生(皮なし) :270mg
・油いため(皮なし):400mg
・食物繊維
・生(皮なし) :2.4g(水溶性食物繊維0.6g、不溶性食物繊維1.8g)
・油いため(皮なし):3.1g(水溶性食物繊維1.0g、不溶性食物繊維2.1g)
同量で比較すると油で炒めたにんじんは、β-カロテン、カリウム、食物繊維のすべてが生のにんじんより多い。とくにβ-カロテン量は3200μgも多い。
4. にんじんの効果的な食べ方

にんじんの栄養素は、同量で比べると調理の仕方によって栄養価が異なる。そのため、栄養素を効果的に摂取するには調理法を工夫することが大切だ。おすすめの食べ方をまとめて紹介する。
冷凍してから調理する
冷凍にんじんのほうが、同量で比べるとβ-カロテンと食物繊維が多い(※1、8、9、10)。にんじんの冷凍保存は長期保存が可能になるほか、下処理して冷凍することにより調理がスムーズになるというメリットもある。食感の変化を避けるには下茹でして冷凍する方法がおすすめだが、生でも薄切りにして急速冷凍すれば、劣化を最小限にすることができる。
スムージーにする
にんじんは皮ごと食べたほうが栄養素をより多く摂取できる(※1、7)。皮付きの生にんじんの食べ方の一つとして、スムージーにする方法がおすすめだ。ただし、にんじんのみで作ると飲みづらいため、りんごジュースを加えるとよい。
油いためにする
にんじんを油いためにすると、β-カロテンを効率よく摂取することができる(※5)。生食よりもかさが減り一度に多く食べられるうえ、ほかの具材を加えたり味付けを変えたりすれば、さまざまなアレンジができる。
結論
にんじんに含まれる栄養素のなかで、とくに含有量が多く健康効果が期待できるのは、β-カロテン、カリウム、食物繊維である。これらの栄養素をより効率よく摂取するには、皮付きのまま食べる、油いためにするなどの食べ方がおすすめだ。求める健康効果に合わせて食べ方を工夫してみよう。
(参考文献)
※1、7~11出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
※1:野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮つき/生
※7:野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/生
※8:野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮つき/ゆで
※9:野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/冷凍
※10:野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/冷凍/ゆで
※11:野菜類/(にんじん類)/にんじん/根/皮なし/油いため
※2~5出典:公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット
※2:ビタミンAの働きと1日の摂取量
※3:カリウムの働きと1日の摂取量
※4:食物繊維の働きと1日の摂取量
※5:抗酸化による老化防止の効果
※6出典:厚生労働省e-ヘルスネット「ナトリウム」
この記事もCheck!