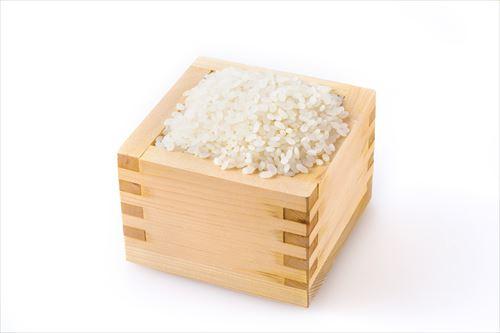1. そもそもお米に賞味期限はあるの?

お米を購入するときに、賞味期限や消費期限が表記されているかどうか確認したことはあるだろうか?実際に見てみるとお米には、精米日は記載されているが賞味期限や消費期限は、表記されていない。
賞味期限と消費期限は、どちらも安全に美味しく食べることのできる期間を表記したものである。消費期限は劣化が比較的早いものにつけられるもので、賞味期限は劣化が比較的緩やかな商品につけられる。店で販売されている加工品には、およそどちらかが記されている。
お米は生鮮食品
消費期限や賞味期限が記されていないものもある。たとえば、野菜類だ。カット野菜を除いて、その多くは消費期限も賞味期限も記されていないことが多い。これらは生鮮食品と呼ばれているもので、そのなかでも種類により分類があり、詳しく表示が定められている。米は「玄米及び精米」の部類で、調整時期や精米時期を記すことは義務付けられているが、賞味期限は記載が定められていない。(※1)
気温や保存方法で食べられる期間は異なる
お米はほかの生鮮食品同様、気温や気候、保存状態によって、食べられる期間は異なる。このため、賞味期限を定めるのは、非常に難しいとも言えるのだ。
2. お米に賞味期限はないが注意したい日付とは?

賞味期限がない=長持ちするという解釈は非常に危険である。野菜をみてもわかるように、保存状態が悪ければ、あっという間に劣化して食べられなくなってしまう。そこでお米の賞味期限を考えるうえで、参考になる日付をまずは学んでいこう。
精米年月日とは?
お米に記されている精米年月日とは、まさに精米をした日、米糠を取り除いた日である。お米といっても玄米にはこの日付ではなく、調整時期が記されている。また年月日ではなく、年月旬(上旬、中旬、下旬)で記されている場合もある。精米年月日は賞味期限ではないが、お米を美味しく食べるためのひとつの指標となる年月日だ。
精米後はできるだけ早めに食べる
お米は精米後は、どんどん水分が蒸発しやすくなる。また酸化も進む。野菜でいうところの皮を剥いた状態といえばわかりやすいだろう。精米後、急激にではないものの確実に劣化するため、開封・未開封に限らずなるべく早めに食べるのがベターだ。
3. お米に賞味期限はないがおいしく食べられる目安とは?

賞味期限はないものの精米後のお米は劣化していく。賞味期限とはいえないが、美味しく食べられる目安をご紹介していこう。お米の購入時に精米年月日を確認し、目安の期間内に食べ切れるか判断するといい。
春と秋の場合
比較的、湿度が低く、涼しい春と秋は、精米年月日から1ヶ月以内に食べ切るといいだろう。
夏の場合
湿度、そして温度が上がりやすい夏は、カビや劣化の心配が大きい。精米年月日から3週間で食べ切るといい。
冬の場合
比較的、気温の低い冬は、精米年月日から2ヶ月以内に食べ切るといいだろう。
賞味期限はないが、どんなに長くとも精米したお米は、2ヶ月以内に食べ切るといいといえそうだ。
4. お米の保存方法とは?

賞味期限のない米は、精米年月日からの推測した目安を基準に食べ切るといいということがわかった。しかし、いくら精米年月日からの目安を守っても正しい保存方法ができていなければ、元も子もない。ここでは正しいお米の保存方法についておさらいしていきたい。
容器に入れて冷蔵庫で保存する
常温保存をしている人が多いお米だが、実はお米の酸化を防ぐためには10℃以下の環境での保存がベストだ。現在の住環境は、冷暖房を使っていることもあり、室温が10℃以上になっていることも多いので、冷蔵庫で保存するほうが安心だ。賞味期限がないとはいえ、適切な保存方法でないと虫がわいたり、カビが生えたりする危険性が高い。
また米は乾燥にも弱いので、密閉した容器、または袋に入れて保存する必要がある。温度としては野菜室がベターだ。におい移りの危険もあるので、周りににおいの強いものを置かないことも重要だ。
こうやってみるとお米の保存には、ひと手間かかることがよくわかる。しかし、賞味期限がない生鮮食品であると考えれば、確かに納得のいく話でもある。
結論
お米は生鮮食品なので、賞味期限の表示が義務付けられていない。このため、賞味期限が曖昧になりがちでもある。基準とすべきは、明記の必要がある精米年月日だ。なるべく早く食べ切ること、そして正しい保存方法でお米を保存することも忘れてはならない。
(参考文献)
※1出典:食品表示法|東京都福祉保健局
この記事もCheck!