目次
1. 壁紙にカビが生える原因と放置するリスク

カビは条件さえ整えば壁紙だけでなく部屋中に発生する。まずはその条件を知ることが大切だ。壁紙に生えてしまう理由や放置するリスクとあわせて解説する。
カビが好む環境
- 湿度:75%以上
- 室温:25℃以上
- 栄養:ホコリ、汚れ、食べカスなど
これらの条件が揃うと、カビが爆発的に繁殖するおそれがある。とくに湿度がポイントで、湿気の高いところではカビの発生率が大幅に上がる。そのため浴室や洗面所、トイレなど水回りの壁紙はとくに注意が必要だ。もちろん、条件さえ揃えば寝室やリビングの壁紙でも油断はできない。
壁紙にカビが生える原因
- 換気が十分でない
- 結露を放置している
- 雨漏りや漏水が生じている など
乾燥する冬場でも加湿器を焚いたりすれば湿度が上がる。換気が不十分だったり結露を放置したりすれば部屋の湿度が上がり、壁紙などへのカビの発生を招くおそれがある。洗濯物の部屋干しもそうだ。室内の湿度を上げることでインフルエンザ予防になるという側面もあるが、同時に換気も意識しよう。このほか雨漏りや水漏れが原因で壁紙が湿気を含み、カビが発生することもある。
カビを放置するリスク
目に見えるだけでも気持ち悪いが、それよりも怖いのは胞子を吸い込むことだ。人によっては喘息やアレルギーなどを招きかねない。また壁そのものがダメージを負うおそれもある。ひどくなれば壁紙だけでなく、壁そのものの補修費用が必要になることも考えられる。カビは早めに撃退するに越したことはない。
2. 水を吸わない壁紙に生えたカビの落とし方

壁紙のカビを落とすには、まず素材に着目する必要がある。水を吸わない素材と吸ってしまう素材に分けられ、それぞれ落とし方が異なるためだ。まずは水を吸わない壁紙だった場合のカビの落とし方から見ていこう。
重曹・酢・エタノールなどでカビを落とす方法
まずはスプレーボトルに酢を適量入れ、その2〜3倍ほどの量の水を加えてよく混ぜておこう。次に、小皿に重曹と酸素系漂白剤を1:1の割合で盛り、数滴の水を加えてよく混ぜてペーストを作る。
用意ができたら、まずは酢をカビにスプレーし、数分待ってキレイな雑巾で優しく拭き取る。次に、使い古しの歯ブラシなどでペーストをカビに塗り、ラップでパックをしたら2時間ほど放置する。時間がきたら水に濡らして固く絞ったキレイな雑巾でペーストを拭き取り、乾いたキレイな雑巾で乾拭きをする。最後にエタノールを吹きかけて乾燥させれば完了だ。ペーストが残るとシミになるおそれがあるため、拭き残しのないように気をつけよう。
用意ができたら、まずは酢をカビにスプレーし、数分待ってキレイな雑巾で優しく拭き取る。次に、使い古しの歯ブラシなどでペーストをカビに塗り、ラップでパックをしたら2時間ほど放置する。時間がきたら水に濡らして固く絞ったキレイな雑巾でペーストを拭き取り、乾いたキレイな雑巾で乾拭きをする。最後にエタノールを吹きかけて乾燥させれば完了だ。ペーストが残るとシミになるおそれがあるため、拭き残しのないように気をつけよう。
白い壁紙なら塩素系漂白剤でもOK
ビニールクロスなど水を吸わない素材で、かつ色が白なら塩素系漂白剤を使ってもよい。水に浸けて固く絞った雑巾でカビを拭き取ったら、使い古しの歯ブラシなどに塩素系漂白剤を少量垂らしてカビに塗っていこう。パッケージに記載された時間だけ放置し、新たな雑巾を水に濡らして固く絞って拭き取ろう。このとき、漂白剤が残らないように丁寧に拭き取るのがコツだ。最後は、乾いたキレイな雑巾で仕上げの乾拭きをすれば完了だ。
白以外ならアルコールスプレーがおすすめ
白以外の壁紙だったときは、消毒用のアルコールをスプレーして拭き取ろう。酸素系漂白剤を使う方法もあるが、色落ちのリスクがあるためあまりおすすめできない。どうしてもというときは、事前に目立たない場所で試してからにしよう。
3. 水を吸う壁紙に生えたカビの落とし方
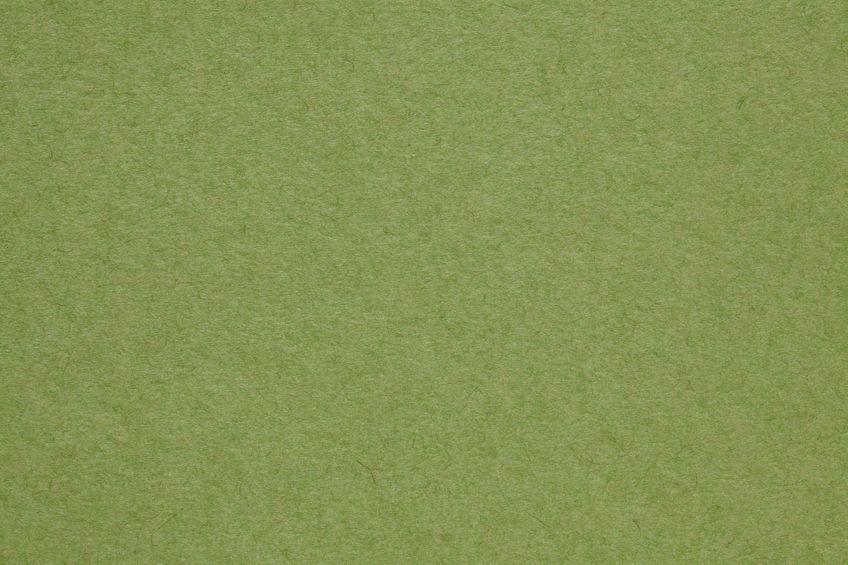
続いて、布や和紙など水を吸いやすい壁紙に生えたカビの落とし方を解説する。
水を吸う壁紙のカビの落とし方
液体が染み込んでしまうおそれがあるため、酢をスプレーしたりペーストを塗ったりする方法は使えない。この場合、まずは水に濡らして固く絞った雑巾で優しく擦ってみよう。それで落ちないときは、布や土壁などに使える「カビホワイト」などのカビ取り剤を使うとよい。直接吹きかけるだけで拭き取る必要がないので手軽にできる。それでも落ちないカビは、一度ハウスクリーニング業者に相談することをおすすめする。
4. 珪藻土や漆喰、木製の壁に生えたカビは?

壁紙は貼られておらず素材のままの壁もある。たとえば珪藻土や漆喰、それに木製などだ。これらも水を含むため、スプレーやペーストなどを使ったカビ取りの方法は使えない。
珪藻土や漆喰の壁に発生したカビの落とし方
水に濡らして固く絞った雑巾で優しく擦る。それで落ちなければ、先ほど紹介したようにカビホワイトなどを使って落とせるか試してみよう。
木製の壁に発生したカビの落とし方
同じく水に濡らして固く絞った雑巾で擦り落とすか、カビホワイトの木材用などを使うとよいだろう。
5. 壁紙のカビを落とすときの注意点
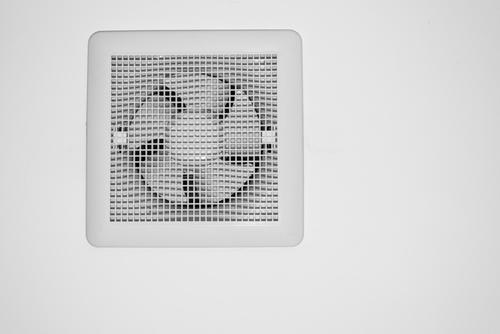
壁紙のカビの多くは、お伝えしたやり方で意外と簡単に落とすことができるはずだ。ただし作業に際しての注意点もある。中には危険なものもあるので、必ず覚えておこう。
塩素系と酸性系のアイテムは絶対に混ぜない
パッケージなどに「まぜるな危険」と分かりやすく書かれているはずだが、塩素系の洗剤と酸性のアイテムは絶対に混ぜてはいけない。酸性はクエン酸や酢であっても同様だ。有害なガスが発生するおそれがあるため、必ず守ろう。
換気をしながら作業する
カビの胞子が舞ったり、酢や薬剤のにおいが充満したりするのを防ぐため、必ず換気をしながら作業に当たろう。
マスク・ゴーグルを着用する
カビの胞子を吸い込んだり粘膜に付着したりするのを防ぐため、マスクとゴーグル(メガネ)などを着用することをおすすめする。
ゴム手袋を着用する
人によっては塩素系漂白剤や消毒用アルコールで肌荒れを起こすこともある。念のために手袋も着用するとよい。
ゴシゴシと強く擦らない
目に見えないカビの胞子をまき散らすことになってしまうため、壁紙のカビを直接素手で触る、ゴシゴシ強く擦る、叩く、吹くといった行為はNGだ。
壁の奥深くまで根を張っているカビは?
汚れが広範囲にわたる場合、表面だけでなく壁の奥深くにまでカビが入り込んでいることが考えられる。撃退するには壁紙を剥がして、壁の下地のカビを除去する必要が出てくるわけだが、素人では難しいうえ、胞子をまき散らすリスクも増大する。この場合は無理をせず、ハウスクリーニング業者に相談しよう。
6. 壁紙のカビを予防するには

せっかく壁紙のカビをできても、油断すればすぐに再発してしまう。きれいな壁紙をキープするためにも、以下のようなカビ予防策を実践しよう。
十分に換気する
こまめに換気して部屋の湿度を上げないことが、壁紙のカビを予防するうえでもっとも重要だ。窓を開けたり換気扇を回したり、扇風機やサーキュレーターなどで湿気を飛ばしたりするとよいだろう。
結露を放置しない
壁紙にできた結露は放置せずにしっかり取り除いておこう。こまめに拭くだけでも大きく違うし、結露防止シートや新聞紙を貼り付けておくといった方法もおすすめだ。
壁紙と家具の間隔をあける
壁紙と家具の間隔が狭いと湿気が溜まりやすくなる。しかも掃除もしづらくなるため、カビの栄養源となるホコリが溜まりやすくなる。できれば5〜10cmなど、間隔をあけるようにしよう。
湿度をコントロールする
室内の湿度は40〜60%くらいが快適とされている。間をとって50%を目安にし、除湿機などでコントロールしよう。除湿機を使用していれば、たとえ部屋干しをしても湿気が溜まりにくくなるはずだ。
結論
壁紙のカビを放置すると徐々に広がって壁そのものを傷めたり、胞子を撒き散らして健康被害をもたらしたりする恐れがある。壁紙のカビは発見し次第、お伝えした撃退法で速やかに落とそう。同時に、カビが発生しにくい環境を保つことも大切だ。







